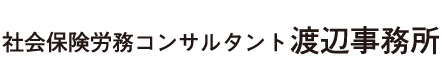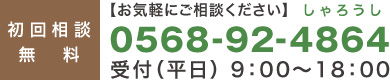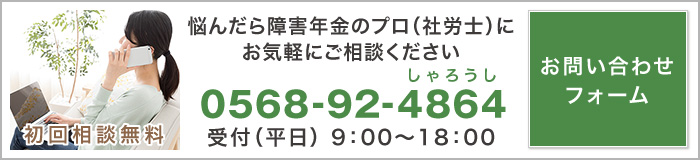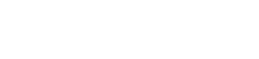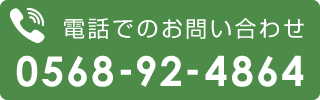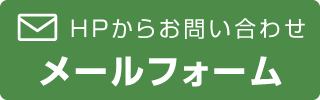2年に一度、あるいは5年に一度、あなたのもとに届く一枚の封筒。「障害状態確認届」。
いわゆる、障害年金の「更新」手続きのお知らせです。
その封筒を見るたびに、「少し調子が良くなったと書かれたら、打ち切られるかもしれない…」という、冷たい恐怖に心が重くなっていませんか?
生活を守るための、かけがえのない命綱であるはずの障害年金が、いつしか、あなたの回復への道を縛る“呪い”になってはいないでしょうか。
こんにちは。愛知県春日井市で、精神疾患の障害年金を専門とする社会保険労務士の渡邊智宏と申します。そして私自身も、双極性障害を患い、この「更新」という名の見えないプレッシャーと闘ってきた、一人の当事者です。
この記事は、単なる更新手続きの解説書ではありません。
更新制度が、私たち当事者に与える「回復してはいけない」という残酷な矛盾を、私自身の経験も交えて正直に語り、専門家としてその構造的な課題を分析し、そして、私たちが本当に安心して治療に専念できるための「あるべき姿」を、あなたと一緒に考えるための、未来への提言です。
〈目次〉
- はじめに:希望の年金証書が、“恐怖の通知”に変わる日
- 【第一部:当事者の告白】“良くなってはいけない”という、見えない檻
- 【第二部:専門家の分析】なぜ、これほどまでに「更新」は怖いのか?
- 【第三部:未来への提言】私たちが本当に“安心して”社会復帰できる制度へ
- まとめ:安心して「良くなる」権利を、社会全体で考えるために
はじめに:希望の年金証書が、“恐怖の通知”に変わる日
障害年金の受給が決まった、あの日のことを覚えていますか。
何ヶ月もの間、「果たして認定されるだろうか」という不安な夜を過ごし、ようやく届いた年金機構からの封筒。震える手でそれを開け、中に「年金証書」を見つけた時の、あの深い安堵感。
「これで、ようやく一息つける」
「何とか、生きていける」
あの時、私たちは、確かに未来への希望を繋いだはずでした。
しかし、その希望は、次の「更新」という日付が近づくにつれて、少しずつ薄れていきます。そして、いつしか「次は通らないかもしれない」という、新たな不安へと姿を変えていくのです。
「最初の請求から何年も経った。病状が良くなっていると書かれてしまうのではないか」
「最近、少し調子がいい日が増えたから、もう打ち切られてしまうのではないか」
あなたの心の中にも、今、そんな思いが渦巻いているのではないでしょうか。
【第一部:当事者の告白】“良くなってはいけない”という、見えない檻
正直に話せない診察室:「元気のないフリ」をしてしまう心理
障害年金の更新日が近づくと、私たちの心は、診断書の内容のことで頭がいっぱいになります。「以前より良くなった」と書かれたら、どうしよう。その不安が、無意識のうちに、私たちの言動を歪めていきます。
誰もが考えるのは、「調子が悪いこと」を医師にアピールすることです。
それまで、少しでも回復してきたことを素直に喜んでいたはずなのに、「良いことばかり伝えたら、マズいかもしれない」という計算が働いてしまう。そして、無意識のうちに、医師の前で「調子が悪い自分」を演じてしまうのです。
回復を喜ぶべきなのに、喜べない。
生活を支える命綱を失う恐怖が、私たちの心を、そんな矛盾した状態に追い込むのです。
私にも、経験があります。
社労士として開業したばかりの頃、仕事だけでは到底生活できず、障害年金が本当に頼りでした。そんな中、更新の時期が近づくと、やはり身構えました。
少しずつとはいえ、仕事を始めた。この事実が、どう評価されるのだろう。
その不安が、常に頭の片隅にありました。
もちろん、仕事が完全に軌道に乗り、年金がなくても十分に食べていけるようになっていれば、話は別です。「打ち切りは寂しいけれど、これが社会復帰ということだな」と、納得できたかもしれません。
しかし、現実は、そこまで甘くありません。
少しずつ良くなっているのは確かでも、ふさぎ込んで一日中外出できない日も、まだたくさんある。その、まだら模様の現実が、診断書一枚で、白か黒か、どう判断されてしまうのか。それが、ただただ不安でした。
だから、医師には、症状が悪いことを書いてほしい。と同時に、「余計なことは書かないでくれ」とも願ってしまう。
「今週はどうでしたか?」という医師の問いに、以前なら「まあまあでした」と答えていたところを、更新が近づくと、曖-昧な返答は避けるようになります。良かったことは心の奥にしまい込み、悪かったことだけを、少しだけ強調して伝えてしまう。
嘘をついているわけではない。しかし、何か釈然としない。
なぜなら、心のどこかで「回復することが、悪いことだ」と考えてしまっている自分に、気づいてしまうからです。
治ってほしい、と願いながら、今回の診断書には、その「回復」を書いてほしくない。
この痛切なジレンマ。
障害年金の更新を経験したことがある方なら、きっと、この気持ちを分かっていただけるのではないでしょうか。
社会復帰へのブレーキ:挑戦をためらわせる「打ち切り」の恐怖
長い闘病生活の中で、少しずつ心が回復してくると、誰しもが「社会復帰」について考え始めます。
「少し、アルバイトをしてみようかな」
「興味のある資格の勉強を、始めてみようかな」
それは、暗いトンネルの先にようやく見えてきた、ささやかで、しかし何よりも尊い希望の光です。
しかし、その光に手を伸ばそうとした瞬間、私たちの頭を、冷たい恐怖がよぎります。
「“働ける”と判断されたら、年金が打ち切られてしまうのではないか?」
この恐怖が、せっかく芽生えた前向きな気持ちを、無惨にも踏みにじってしまうのです。
障害年金2級の認定基準には、「労働によって収入を得られない程度のもの」という一文があります。このため、現実問題として、「仕事ができている」という事実があると、2級の認定は非常に難しくなります。私も、どう見ても2級に該当するほど症状が重い方が、ただ「働いている」という、たった一つの理由だけで、不支給となった事例を、これまで嫌というほど見てきました。
障害年金の審査において、「就労」は鬼門なのです。
その現実を知っているからこそ、私たちは、仕事を始めることに、ためらいを覚えてしまう。
もちろん、社会復帰が叶い、しっかりと安定して働けるようになったのなら、年金の打ち切りは当然のことです。
しかし、私たちが踏み出そうとしているのは、そんな確固たる一歩ではありません。
「続くかどうか分からないけど、少しだけ、挑戦してみたい」
「いつまた、挫けてしまうか分からないけど、それでも、前に進みたい」
そんな、おっかなびっくりで、震えるような、ささやかな一歩なのです。
最初の1ヶ月は、無理をしてでも頑張れるかもしれない。でも、半年、一年というスパンで見れば、その無理がたたって、再発してしまうかもしれない。
それなのに、たった一度の更新が、その尊い挑戦の芽を摘み取ってしまうかもしれない。
生活を支える命綱であるはずの障害年金が、皮肉にも、社会復帰への道を阻む「障害」になってしまう。
この、あまりにも大きな矛盾が、今の更新制度には、存在しているのです。
【第二部:専門家の分析】なぜ、これほどまでに「更新」は怖いのか?
ここまで、当事者としての感情的な側面をお話ししてきました。
しかし、私たちが抱えるこの不安は、単なる気のせいではありません。それは、現行の更新制度が抱える、3つの構造的な課題に起因しているのです。ここからは、社会保険労務士として、その課題を冷静に分析していきます。
課題①:たった一枚の診断書で未来が決まる「一点評価」の危うさ
うつ病や双極性障害は、「症状の波」があることが、その本質です。調子の良い時期もあれば、悪い時期もある。その波の中で、私たちは生きています。
しかし、障害年金の更新審査は、原則として、提出された診断書一枚で完結します。
もちろん、医師はその波を考慮して診断してくれるはずです。しかし、診断書には「過去1年の経過」といった長期的な視点で症状を記述する欄はなく、どうしても「診断書作成時点」という「点」での評価に偏りがちです。
「たまたま、調子が良かった1ヶ月」に書かれた診断書が、その後のあなたの数年間の生活を、左右してしまう。その危うさが、今の制度には内在しているのです。
課題②:「良くなる=不支給」という、回復と矛盾する0か100かの判定
症状が少し改善した、という事実が、「支給」か「不支給」かという、あまりに極端な判断に直結してしまう。これも、大きな問題です。
特に、国民年金(障害基礎年金)の対象者にとって、この問題はより深刻です。
障害厚生年金には、比較的症状が軽い場合でも支給される「3級」がありますが、国民年金にはそれがなく、原則「2級」以上でなければ支給されません。
つまり、2級という重い状態から、少しでも回復の兆しが見えると、即「不支給=収入ゼロ」という崖っぷちに立たされてしまうのです。
これでは、自身の回復を素直に認めることなど、到底できません。その恐怖が、回復へのブレーキとなり、社会復帰を遅らせる原因にもなっているのです。
課題③:申立の機会がない!声なき声が届かない、一方的な審査構造
そして、私が最も大きな制度上の欠陥だと考えているのが、この点です。
初めて障害年金を請求する時、私たちは、医師の診断書だけでなく、自分自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」を提出します。これは、自分の言葉で、これまでの苦しみや、日常生活の困難さを、審査官に直接伝えることができる、唯一の機会です。
しかし、更新時には、この最も重要な「申立の機会」が、制度として保障されていません。
提出を求められるのは、原則、医師が書いた診断書一枚だけなのです。
その結果、どうなるか。
「働いている」という、たった一行の事実。その裏にある、どれほどの苦労、どれほどの無理、どれほどの周囲の支援があるのか。診断書に書ききれない、そのリアルな声を、私たちは伝える術を持たないのです。
これでは、あまりに一方的ではないでしょうか。
当事者の「言い分」を聞く場がないまま、未来が決められてしまう。この構造こそが、私たちの更新への不安を、決定的なものにしているのです。
【第三部:未来への提言】私たちが本当に“安心して”社会復帰できる制度へ
問題点を指摘するだけでは、何も変わりません。
当事者として、そして日々現場で格闘する専門家として、私が考える「あるべき更新制度」の姿。それは、「0か100か」の思考から脱却し、私たちの“ゆるやかな回復と社会復帰のプロセス”そのものを、丸ごと肯定してくれる制度です。そのための具体的な提言を、3つの視点から述べさせていただきます。
提言①:「就労=即不支給」の思考停止をやめ、「継続性」を評価する仕組みへ
現行制度の最大の欠陥は、「就労」という“点”で物事を判断しすぎることです。
そうではなく、その働き方が「持続可能」なものなのか、“線”で評価する視点が必要です。例えば、少なくとも1年間、安定して就労を継続できているか。その上で、判断を下すべきです。
「お試し」の就労という、尊い一歩を、制度が邪魔してはなりません。もし、数年に一度の見直しでは追いきれないというのなら、就労している場合は1年更新にするなど、その人の状況に合わせた、きめ細やかな対応をすればいいのです。
提言②:オール・オア・ナッシングからの脱却と、「中間的な評価」の創設
「支給」か「不支給」かという、極端な判定をやめるべきです。
例えば、老齢年金の「在職老齢年金」のように、就労による収入額に応じて、年金額がゆるやかに減額されるような仕組みがあっても良いはずです。
特に、3級のない国民年金においては、社会復帰を目指す人々を支えるための、新たな「中間的な等級」の創設が、急務だと考えます。
このような「中間地帯」が保障されて初めて、私たちは「打ち切り」の恐怖なく、「もう少しだけ、働いてみようかな」という一歩を踏み出すことができるのです。
提言③:更新制度に「申立」と「証言」の機会を!
最初の請求時と同様に、更新時にも「病歴・就労状況等申立書」の提出を必須とすべきです。本人の「言い分」を聞く機会がないまま、審査を進めるべきではありません。
さらに、必要に応じて、就労移行支援事業所や、勤務先の上司などからの「証言(意見書)」も提出できる環境が欲しいものです。
診断書という「医学の光」だけでなく、申立書という「当事者の魂の叫び」と、意見書という「社会の現実」を組み合わせる“三位一体の評価”こそが、私たちを安心して社会復帰へと導く、未来の更新制度の姿であると確信しています。
まとめ:安心して「良くなる」権利を、社会全体で考えるために
ここまで、障害年金の更新制度が私たち当事者に与える、複雑なプレッシャーと構造的な課題について、私なりの分析と提言を述べさせていただきました。
この記事を読んで、あなたは何を感じましたか?
「自分だけが不安なわけではなかった」という安堵でしょうか。それとも、「制度そのものが変わらなければ、根本的な解決にはならない」という、ある種の無力感でしょうか。
私自身、この問題について考えを深めるほどに、これは単なる手続き論ではなく、「私たちの社会が、病や障害からの回復というプロセスを、どう捉え、どう支えていくのか」という、より大きな哲学的な問いなのだと感じています。
「良くなること」を、素直に喜べない社会。
挑戦する勇気よりも、打ち切りの恐怖が勝ってしまう制度。
本当に、それで良いのでしょうか。
私がこの記事で提示した「提言」は、まだ小さな声でしかありません。しかし、当事者であり、専門家である私たちが、声を上げ続けること。そして、この記事を読んでくださったあなたが、この問題を「自分ごと」として考え、周りの誰かと共有してくれること。その小さな波紋が、いつか社会全体を動かす大きなうねりになると、私は信じています。
私たちに必要なのは、安心して「良くなる」権利です。
その権利が当たり前になる社会を目指して、私はこれからも、専門家として、そして同じ痛みを分かち合う同志として、考え、発信し続けていきたいと思います。
どうか、更新という大きな不安の波に、独りで飲み込まれないでください。
あなたの苦しみは、あなた一人のものではありません。社会全体で向き合うべき、私たちの共通の課題なのですから。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。