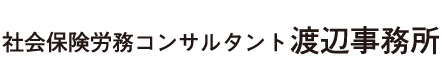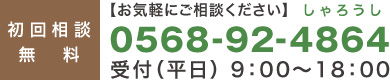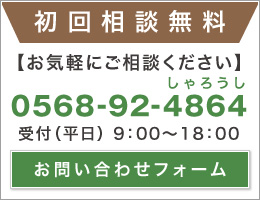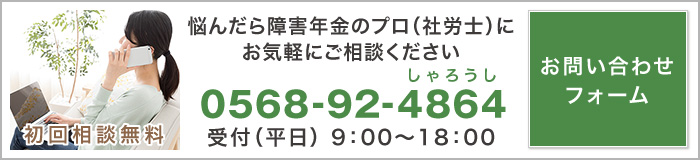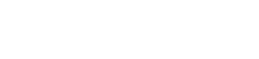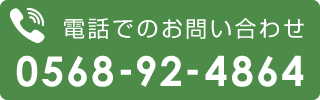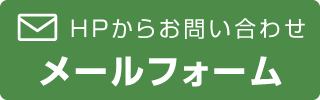「毎日、不安で胸が押しつぶされそうです」
「悲しくて涙が止まりません」
そう書きたくなる気持ちは、痛いほど分かります。
ただ、障害年金の審査(特に精神)で最も見られるのは、あなたの“気持ち”そのものよりも、
その病気によって日常生活がどれだけ破綻しているか(事実)です。
このページは、障害年金の申請(請求)を進めるための“完全ガイド”であると同時に、
あなたの「辛い」を、審査側が理解できる「生活の事実」へと変換するための教科書です。
このページで分かること
- 申請の全体像(準備→診断書→申立書→提出→審査→決定)
- 初診日・納付要件でつまずかない要点
- 診断書を軽くしないために、依頼前にやること
- 申立書で「整合性」を作る方法(NG/OK例あり)
≪もっと知りたい!!≫
○この完全ガイドは「制度と書類の全体像」です。
窓口の分岐や電話番号など、地域の動き方は地域別ページが早いです。
○「初診日が曖昧」「診断書が軽くなりそう」「何から手をつけるか不安」な方へ。
診断書を医師に依頼する前に、受診歴と生活実態メモを一緒に整理し、手戻りを減らします。
電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。
最短3ステップ(迷ったらこれ)
- 初診日と受診歴をメモ(病院名/時期/転院順)
- 加入年金と納付状況を確認
- 日常生活の「できていない事実」を整理して、医師へ依頼→提出へ
目次
第1章 障害年金は「順番」で決まる
第2章 最大の関門:初診日と納付要件
第3章 必要書類:ケース別チェックリスト
第4章 就労だけでは弱い。まず「生活の崩壊」を出す
第5章 「辛い」を「事実」に変換する
第6章 7つの日常生活動作を「事実」で埋める
第7章 診断書は”依頼前”が勝負(医師とのすり合わせ術)
第8章 病歴・就労状況等申立書の書き方
第9章 等級を分けるのは”病名”より”生活の事実”
第10章 今日からできる申請準備チェックリスト
第11章 よくあるつまずきと対処法
第12章 まとめ:事実を伝えることは、自分を守ること
第1章 全体像:障害年金は「順番」で決まる(迷いを消すフロー)
障害年金の申請で迷子になる最大の原因は、最初にやる順番を間違えることです。
いきなり「診断書を書いてください」と医師に頼んでしまったり、逆に書類集めに時間をかけすぎて疲弊したり。
このガイドの基本方針はシンプルです。
①初診日(起点) → ②加入年金(窓口) → ③生活の事実(診断書) → ④申立書(整合性)
あなたの「辛い」を、審査側が判断できる「事実」に翻訳して届けるには、この順番が一番手戻りが少ないです。
1-1 まずは全体の流れ(テキスト図解)
【STEP0】初診日と受診歴をメモ(病院名/時期/転院順)
↓
【STEP1】初診日の加入年金を確認(国民年金/厚生年金/共済)
↓
【STEP2】納付要件の確認(足りないと、ここで止まる)
↓
【STEP3】生活実態メモを作る(=「辛い」を「事実」に翻訳)
↓
【STEP4】医師に診断書を依頼(依頼前のすり合わせが勝負)
↓
【STEP5】病歴・就労状況等申立書を作成(診断書の評価をエピソードで補強)
↓
【STEP6】提出(窓口へ)→ 受付 → 審査
↓
【STEP7】結果(支給/不支給/等級)→ 必要なら次の手(審査請求など)
「どこが勝負か?」というと、STEP3〜5です。
ここで“事実の出し方”がズレると、診断書と申立書が噛み合わず、審査側に伝わりません。
1-2 最初の分岐:「初診日」が全ての起点になる
障害年金は、最初に医師にかかった日(初診日)が起点です。
この初診日で、主に次の3つが決まります。
- どの年金制度が対象か(国民年金/厚生年金/共済)
- 提出先(窓口)がどこか(市役所・区役所・年金事務所など)
- 必要書類がどれくらい増えるか(受診状況等証明書が必要になる等)
だから、申請の最初は「感情の説明」ではなく、初診日と受診歴のメモから始めます。
正確な日付まで完璧にしなくて構いません。ただし、まったく不明だと窓口では一般論になりがちです。
最低限、これだけはメモしてください。
- 最初に受診した医療機関名
- 時期(○年○月ごろ/転職前後/季節でも可)
- 転院の順番(分かる範囲で)
1-3 次の分岐:「加入年金」で窓口が変わる(原則と実務のおすすめ)
初診日の時点で加入していた年金によって、窓口は原則として次のように分かれます。
- 初診日が 国民年金(第1号) 側 → 原則:市役所・区役所の国民年金担当
- 初診日が 厚生年金(第2号)/第3号 側 → 原則:年金事務所(または街角相談センター)
- 初診日が 共済 → 各共済組合
ここで大事なのは、原則と実務は分けて考えることです。
国民年金の窓口は原則として市役所・区役所ですが、
実務上は年金事務所で相談・手続き(提出まで)を進めることが可能で、そちらの方がおすすめです。
理由はシンプルで、年金事務所は年金業務の専門部署であり、相談の精度が安定しやすいこと、そして――
一度話して「信頼できそう」と思える担当者に当たったら、
その場で次回予約を取り、同じ担当者のまま提出まで進められる(担当者固定)からです。
毎回説明がリセットされにくく、手戻りが減ります。
一方で、市役所・区役所には住民票や戸籍などを同じ庁舎で揃えやすい(ワンストップ)メリットもあります。
迷う場合は、まず年金事務所で相談し、必要に応じて「どこに提出するのが最短か」を確認して進めるのが現実的です。
≪もっと知りたい!!≫
1-4 「辛い」を書く前にやるべきこと:生活実態メモ(これが診断書を変える)
ここからが、このガイドの核心に繋がります。
多くの人は、医師にこう言いたくなります。
「とにかく辛い」「不安でたまらない」「毎日絶望している」
でも、審査で伝わるのは、「感情」そのものではなく 生活がどう壊れているかという「事実」です。
そして医師が診断書に落とし込みやすいのも、やはり「事実」です。
だから、診断書を依頼する前に、まず“素材”を用意します。
それが 生活実態メモです。
- 入浴:週○回/誰が促すか/入れないとどうなるか
- 食事:1日○回/内容/買いに行けるか
- 金銭:支払い遅延/衝動買い/管理を誰がしているか
- 対人:インターホンに出られるか/電話が取れるか
- 安全:火の管理/希死念慮があるときの行動
- 通院:一人で行けるか/服薬の抜け
こういう“生活の数字と行動”が揃うと、医師との認識ズレが減り、診断書が「軽め」になりにくい。
逆に言うと、ここが曖昧なままだと、診察室の短い会話だけで診断書が作られ、あなたの生活の地獄が反映されません。
≪もっと知りたい!!≫
1-5 この章の結論:申請は「順番」と「素材」で勝つ
第1章で言いたいことは、これだけです。
- 障害年金は、順番で進める(初診日→加入年金→生活実態→診断書→申立書)
- 「辛い」は大事だが、そのままでは比較できない
- だから、「辛い」を 生活の事実に翻訳する素材(生活実態メモ)を先に作る
次章では、このフローの最初の関門である
「初診日」と「納付要件」を、分かりやすく整理します。
ここを押さえると、申請が止まりにくくなります。
第2章 最大の関門:初診日と納付要件(ここで止まる人が一番多い)
障害年金の申請は、実は「診断書」より前に、2つの関門があります。
- 初診日(起点)
- 保険料の納付要件(資格)
ここが曖昧だと、どれだけ生活が崩壊していても、申請が前に進まなかったり、途中で止まります。
だから第2章では、あなたの「辛い」を語る前に、申請の土台を固めます。
2-1 初診日とは「最初に医師にかかった日」(※診断がついた日ではない)
初診日という言葉が、まず混乱のもとになります。
ここでいう初診日は、基本的に次の意味です。
その症状(障害の原因となった傷病)について、最初に医師の診療を受けた日
よくある勘違いはこれです。
- × 診断名がついた日
- × 休職した日
- × 退職した日
- × 障害年金を知った日
- × 生活が限界になった日
あなたの苦しみの“ピーク”の日ではなく、最初に医療につながった日が起点になります。
この初診日で「どの年金(国民/厚生/共済)」か、そして原則の窓口が分かれます。
2-2 初診日が大事な理由は3つだけ覚えてください
初診日が確定すると、次が決まります。
- 加入年金が決まる(国民年金なのか、厚生年金なのか)
- 提出先(原則窓口)が決まる(市役所/区役所/年金事務所等)
- 必要書類の方向性が決まる(受診状況等証明書が必要になる等)
だから、初診日が曖昧なまま動くと、窓口で一般論になりやすい。
逆に、正確な日付まで完璧でなくても、病院名と時期の目安があるだけで話が一気に具体化します。
2-3 初診日が分からない人へ:まずは“受診歴メモ”でOK(正確な日付は後から詰める)
「何年も前で覚えていない」
「転院が多くてぐちゃぐちゃ」
これは本当に多いです。ここで止まらないでください。
まずは、受診歴メモを作ります。最低限これだけ。
- 最初に行った医療機関名(分かる範囲で)
- 時期(例:2020年冬ごろ/転職の前後/子どもの入学の頃…でもOK)
- 転院の順番(分かる範囲で)
- 「心療内科」「精神科」「内科」などの科の種類
受診歴メモは必須ではありません。
でも、初診日が全く分からないと、窓口では一般的な説明で終わりやすく、
「初診日が分かったらもう一度来てください」となりがちです。
正確な日付は不要でも“当たり”をつけてから行く方が効率的です。
2-4 カルテがない・閉院・転院が多い場合の考え方(ここで詰まらない)
初診日が分からない原因は、だいたい次の3つです。
- ① 初診の病院が閉院している/カルテが残っていない
- ② 転院が多く、最初がどこか分からない
- ③ 最初は内科など別科で、精神科に繋がるまで時間がある
この場合、結論はこうです。
「記録で追える範囲」から固めていき、初診日に近づけていく
具体的には、
- いま通っている病院(最新)の紹介状・診療情報提供書
- お薬手帳(いつ頃から何の薬か)
- 健康保険の受診履歴(分かる範囲)
- 手元に残っている領収書、予約票
など、“残っている証拠”から順に辿ります。
≪もっと知りたい!!≫
2-5 次の関門:保険料の「納付要件」(ここがOKなら先に進める)
障害年金は「困っているから誰でももらえる」制度ではなく、
一定の保険料要件(納付要件)があります。
ここでは細かい数字の暗記は不要です。要点だけ。
- 原則として、初診日の時点で 保険料を一定期間きちんと納めていること が求められる
- 免除・猶予など、制度上の手続きをしている期間は評価されることがある
- 未納が多いと、ここで止まる
「納付要件が不安」という人は、先にここを確認すると手戻りが減ります。
2-6 納付要件の確認はどこでやる?(最短ルート)
確認方法は大きく2つです。
- ねんきんネット等で履歴を確認する
- 窓口で確認する
国民年金の原則窓口は市役所・区役所ですが、
実務上は年金事務所で相談・手続き(提出まで)を進める方がおすすめです。
年金業務の専門性があり、担当者固定(次回予約をその場で)もしやすいからです。
市役所・区役所のメリットは、住民票や戸籍などを同じ庁舎で取りやすい点。
ただ、申請全体をスムーズに進めるなら、まず年金事務所で相談し、必要に応じて証明書を区役所等で取る、という動き方が現実的です。
≪もっと知りたい!!≫
2-7 第2章の結論:初診日と納付要件が固まれば、あとは「事実」を集めるだけ
ここまでで土台は完成です。
- 初診日の“当たり”がついた
- 受診歴メモができた
- 納付要件の見通しが立った
次章では、いよいよ核心に入ります。
あなたの「辛い」を、審査側が判断できる「事実」に翻訳するために、
まず 必要書類と準備(ケース別チェック) を整理します。
第3章 必要書類:ケース別チェックリスト(先に“全体像”を掴む)
障害年金は、書類が多く見えて不安になります。
でも、最初から全部揃えようとすると、疲れて止まります。
ここでは、手戻りを減らすために
- まず必要になりやすい書類(共通)
- ケースによって増える書類
- 初回相談で持っていく“最小セット”
を整理します。
ポイント:申請は「全部揃えてから窓口」ではなく、
窓口で段取りを決めてから集めるほうが前に進みます。
3-1 まず結論:書類は3つの山に分けると迷わない
① あなたの情報(本人確認・年金番号・銀行口座)
② 医師の書類(診断書)
③ あなたが書く書類(病歴・就労状況等申立書)
+(必要に応じて)初診日の証明・添付書類
このうち、いきなり動かしにくいのは②の診断書です。
診断書は“依頼前”が勝負。先に生活実態メモ(事実)を固める。
3-2 共通で出やすい書類(基本セット)
A:あなたの情報(まず揃う)
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、ねんきん定期便など)
- 本人確認書類(運転免許証、住民票、戸籍謄本等)
- 振込先口座情報(通帳の控え等)
B:医師の書類(核)
- 障害年金用の診断書
※精神の場合は精神の診断書様式。身体・知的は様式が異なります。
C:あなたが書く書類(核)
- 病歴・就労状況等申立書(精神の場合特に重要)
- (ケースにより)就労状況に関する資料(勤務状況のメモなど)
ここまでが“主役3点”。
あとは「初診日」と「ケース」で追加書類が増えます。
3-3 ケースによって増える書類(増えるポイントだけ押さえる)
① 初診日を証明する書類が必要になるケース
- 初診の医療機関が現在の病院と違う
- 初診日が古い/転院が多い
- 初診が別科(内科等)から始まっている
→ この場合、受診状況等証明書(初診の証明)が必要になることがあります。
(※ここが詰まりやすいので、初診日と受診歴メモが効きます)
② 家族が代理で動くケース
- 体調的に本人が窓口に行けない
→ 委任状が求められることがあります。
③ 同居家族や支援者の情報が重要になるケース
- 日常生活の援助がある
→ 「誰が何をどれだけ助けているか」が申立書の核になります。
(※家族に“生活の事実”を確認しておくと強い)
3-4 初回相談で持って行くもの(最小セット)※ここが最重要
「相談に行くのに、何を持って行けばいい?」
結論:全部は不要です。最低限これで話が進みます。
初回相談・最小セット
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、ねんきん定期便など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 受診歴メモ(初診日メモ) ←できれば持参
- 初診日のころの働き方メモ(会社員/扶養/自営/無職/学生)
- 現在の病院名・通院頻度・服薬状況のメモ
受診歴メモは必須ではありません。
ただし、初診日がまったく不明だと一般論の説明で終わりやすく、
「初診日が分かったらもう一度来てください」となりがちです。
正確な日付まで不要でも「病院名+時期の目安+転院順」くらいは把握して行くのがおすすめです。
3-5 どこに相談・提出する?(原則と、実務上のおすすめ)
国民年金の原則窓口は市役所・区役所です。
ただし実務上は年金事務所で相談・手続き(提出まで)を進めることが可能で、そちらの方がおすすめです。
年金業務を専門に扱っており、次回予約をその場で取りやすく、担当者固定で進められるため手戻りが減ります。
一方で、市役所・区役所のメリットは、住民票や戸籍などの証明書を同じ庁舎で揃えやすい(ワンストップ)点です。
迷う場合は、まず年金事務所で相談し、「このまま提出まで年金事務所で進められるか」を確認した上で、必要な証明書だけ市役所・区役所で取る、という動き方が効率的です。
≪もっと知りたい!!≫
○この完全ガイドは「制度と書類の全体像」です。
窓口の分岐や電話番号など、地域の動き方は地域別ページが早いです。
3-6 診断書を依頼する前に“必ずやること”
書類で一番重いのは診断書です。
- 診断書を書いてもらってから「思ってたのと違う」となるケースは多い
- でも、一度書いた診断書の大幅修正は難しいことがある
- だから、相談のタイミングは 診断書を依頼する前が望ましい
次章では、あなたの「辛い」をそのまま書くのではなく、
医師と審査に届く形に翻訳するための“素材”――
生活実態メモ(事実のログ)の作り方に入ります。
第4章 【戦略の核】就労“だけ”では弱い。まず「生活の崩壊」を出す
障害年金の相談で、最初に出てくる悩みは多くが「仕事」です。
- ミスが増えて叱責される
- 人間関係がつらくて出社できない
- 休職を繰り返し収入が不安
- もう働けない気がする
これらは切実です。ここを否定するつもりはありません。
ただ、等級(2級・3級など)を左右する場面では、就労の話“だけ”だと弱くなることが多い。理由はシンプルです。
就労は「結果」であり、審査が見たいのは「土台(生活)」だからです。
4-1 審査のモノサシは「日常生活能力」(仕事の項目は主役ではない)
精神の障害の審査では、診断書にある 日常生活能力(生活の維持や対人関係など)が重要な軸になります。
要するに、審査側が知りたいのはこういうことです。
- 生活の基本動作がどれくらい崩れているか
- 援助(家族・支援者)がどれくらい必要か
- 危機対応(安全保持)がどれくらい危ういか
- 社会性・対人関係がどれくらい保てないか
もちろん、就労状況が無関係という意味ではありません。
実際、就労できているかどうかは判断に影響します。
ただし、それは「生活の土台が崩れている」ことが書類で示されている前提で、はじめて強い意味を持ちます。
4-2 なぜ「仕事ができない」だけだと通りにくいのか(審査側の見え方)
仕事のつらさだけを書くと、審査側にはこう見える余地が残ります。
- 職場環境(人間関係)が悪いだけでは?
- 配置転換や業務調整で対応できるのでは?
- 休職で回復すれば戻れるのでは?
- “仕事”以外の生活は維持できているのでは?
つまり、「仕事がつらい」は本当でも、
障害(病気)によって生活能力がどれだけ落ちているかが見えないと、判断材料として弱くなります。
4-3 一番強いのは「生活が壊れている → だから仕事も無理」という順番
審査側のロジックは極めて現実的です。
生活が崩れている人が、安定して就労できるはずがない
たとえば、次のような情報は、仕事の話より強く刺さります。
- 入浴は週1回、促されないと入れない
- 食事は1日1回以下、買いに行けない日がある
- 服薬を自己管理できず、家族がセットしている
- 役所や病院の電話に出られない/手続きができない
- 公共料金の支払いができず停止した
- 火の管理が不安で調理を避けている
- インターホンに出られず宅配が受け取れない
これらは「感情」ではなく「事実」です。
そして、事実は審査側が比較・判断できる共通言語になります。
4-4 就労の話を捨てる必要はない。ただし“書き方”がある
ここで誤解してほしくないのは、就労の話を消せと言っているわけではない、ということです。
大事なのは順番と書き方です。
- ×「上司が怖い」「職場がつらい」だけ
- ○「生活がこう崩れている」→「その結果として就労がこう崩れている」
就労を書くなら、「感情」より「機能の低下(できない事実)」で書きます。
就労のOK例(“能力の低下”に寄せる)
- 身支度に2時間以上かかり遅刻を繰り返す
- 指示内容が頭に入らず、メモを取れない
- 電話が鳴ると動悸で受話器を取れず、隠れてしまう
- 通勤途中でパニックになり引き返す
- 帰宅後は反動で翌日まで寝込む
「つらい」ではなく、何ができなくなったかを出す。
これが“生活→就労”の順番とセットになると、説得力が跳ね上がります。
4-5 第4章の結論:等級の勝負は「生活の事実」をどれだけ出せるか
まとめます。
- 就労の悩みは切実。でも、それ“だけ”だと弱いことが多い
- 審査は「生活能力」という土台を見る
- だから、まず「生活の崩壊(事実)」を出し、就労は結果として書く
- 感情ではなく、頻度・時間・援助・失敗の結果で示す
次章では、この方針を具体的な技術に落とします。
あなたの「辛い」を、審査が判断できる「事実」に翻訳する――
“ロボット視点”で生活を記録する方法を解説します。
第5章 【思考法】「辛い」を「事実」に変換する(ロボット視点で書く)
ここまでで、等級判断の土台は「生活」だと分かりました。
では、その生活の崩壊を、どうやって診断書・申立書に落とし込むのか。
結論はシンプルです。
「辛い」と書く前に、行動(または不行動)を書き、
それを 数字 と 援助の有無 で固定する。
これが、審査に届く文章の基本形です。
5-1 審査官はあなたの心の中を見られない(見ているのは紙だけ)
障害年金の審査をする人は、あなたに会いません。
見ているのは、診断書と申立書という「文字情報」だけです。
だから、あなたがどれほど苦しいかは、本来わかりようがありません。
- Aさんの「辛い」とBさんの「辛い」は、同じ強さなのか
- 「不安でたまらない」は、どれくらい生活に影響しているのか
- 「死にたい」は、危険行動につながっているのか
感情だけでは比較ができません。
審査側が判断できるのは、生活への支障として現れている事実だけです。
5-2 感情の罠:「辛い」と書くと不利になりやすい3つの理由
理由① 重症度が伝わらない(比較できない)
- ×「とても不安です」
- ○「不安でインターホンに出られず、宅配便を3回連続で受け取れなかった」
後者は、生活の機能がどれだけ落ちているかが一発で伝わります。
理由② 矛盾が生まれやすい(診断書が軽くなる)
「こんなに辛いのに診断書が軽い」
このズレの原因は、医師に「感情」ばかり伝えて「動けなさ(事実)」を伝えていないことが多いです。
医師は診察室で見える材料で判断します。
材料が「辛い」だけだと、診断書に落とし込みづらい。
理由③ 原因が“環境問題”に見える余地が残る
「職場が辛い」「人間関係が辛い」だけだと、
審査側には「環境が変われば改善するのでは?」という解釈の余地が残ります。
だから、生活の崩壊を“機能の低下”として出す必要があります。
5-3 「ロボット視点」を入れる:感情を消して“行動ログ”にする
ここで使うのが、ロボット視点です。
ロボットには感情がありません。あなたの行動だけを記録します。
変換例(人間視点 → ロボット視点)
- ×「何もやる気が起きなくて、一日中布団にいて情けなかった」
- ○「起床14:00。トイレ以外で布団から出たのは水を飲む1回のみ。着替えなし。発語なし。」
このように、“感情語”を削り、行動(または不行動)だけを抜き出す。
これが「辛い→事実」翻訳の核心です。
5-4 事実に必要な4要素(これが揃うと強い)
事実には、次の4つを入れてください。
- 頻度:週○回/月○回
- 時間:○分/○時間
- 援助:独力/助言があれば/介助が必要
- 結果:放置すると何が起きるか(ガス停止、未受診、事故リスク等)
書き方の型(テンプレ)
「○○は(頻度)。所要時間は(時間)。(援助)がないとできない。結果として(具体的な困りごと)。」
例:
「入浴は週1回。準備から終了まで2時間以上かかる。家族が声をかけて湯を張らないと動けない。結果として、数日同じ服を着続け、皮膚トラブルが出ることがある。」
5-5 1週間ログテンプレ(ここから書き始めればOK)
申請準備の期間だけでいいので、まずは7日間、これを書いてください。
(完璧でなくていい。穴があってもOK)
【1日テンプレ】(コピペして使えます)
- 起床: 時 分(※昼夜逆転があればそのまま)
- 睡眠: 時間(途中覚醒:有/無)
- 食事:回数(内容:例 コンビニ弁当/カップ麺/家族が用意)
- 入浴・洗面:入浴(有/無)、洗顔・歯磨き(有/無)
- 着替え:有/無(同じ服:○日目)
- 外出:有/無(理由:通院/買い物/不可)
- 服薬:自己管理できた/家族管理/抜けた(回数)
- 対人:会話(有/無)、電話(取れた/無理)、インターホン(出た/居留守)
- 家事:できたこと/できなかったこと(具体的に)
- 金銭:支払い/買い物(できた/できない、衝動買いの有無)
- 危機:火の管理・戸締り・希死念慮(行動に出たか)
- 援助:誰が何をしたか(声かけ/同行/代行)
このログがあると、医師にも審査にも届く「材料」が揃います。
診断書が軽くなりがちな人ほど、ここが効きます。
5-6 ロボット視点を“医師と審査”に使う方法(2つの出口)
出口①:医師に渡す「生活実態メモ」になる
診察室では言いにくい生活の崩壊を、メモで渡せます。
医師が診断書に落とし込みやすくなります。
出口②:申立書の“整合性”を作る根拠になる
診断書の評価(例:清潔保持が低い)に対して、
「だから低い」というエピソードで補強できます。
5-7 第5章の結論:感情は否定しない。ただ“翻訳”して届ける
あなたの「辛い」は本物です。
ただ、審査は心を読む試験ではなく、書類で判断する制度です。
だからこそ、
- 感情 → 行動(不行動)
- 行動 → 数字(頻度・時間・援助・結果)
この順番で翻訳して届ける。
それが、あなたの生活を守るための最短ルートになります。
次章では、このロボット視点を、診断書の軸に合わせて
「7つの日常生活動作」それぞれに落とし込む具体例に進みます。
第6章 【実践】7つの日常生活動作を「事実」で埋める(チェック+OK/NG)
第5章で作った「ロボット視点のログ」を、診断書の軸に合わせて整理します。
精神の審査で重要になりやすいのが、日常生活能力(生活の維持)です。
ポイントは毎回同じ。
頻度(週○回)/時間(○分)/援助(誰が)/結果(何が起きる)
この4点を入れる。
ここでは、7項目それぞれについて「何をチェックし、どう書けば強いか」を具体化します。
① 適切な食事(食欲ではなく、摂取回数と内容)
チェック(事実にする質問)
- 1日何回食べている?欠食は週何回?
- 自炊できる?火や包丁を使える?
- 買いに行ける?買い置きができる?
- 栄養は偏っている?(パン・麺だけ等)
- 食後の片付け(ゴミ捨て・洗い物)はできる?
OK例(事実)
- 「食事は1日1回。買いに行けない日は食べない(週2回)。内容は菓子パンかカップ麺が中心。自炊は火の管理が不安でできない。食後のゴミを捨てられず、空き容器が寝床周辺に溜まる。」
- 「食事の準備は自力ではできない。家族が用意したものを食べるだけ。自分で冷蔵庫から取り出すのもしんどく、声かけがないと抜くことがある。」
NG例(弱い)
- 「食欲がありません。美味しく感じません。」
② 身辺の清潔保持(気分ではなく、入浴・着替えの頻度)
チェック(事実にする質問)
- 入浴は週何回?シャワーだけ?湯船?
- 歯磨き・洗顔は毎日できる?
- 服・下着は何日で替える?
- 洗濯ができる?(回す/干す/畳む)
- 不潔が原因で問題(皮膚炎・虫歯等)は出ている?
OK例(事実)
- 「入浴は週1回。家族に促されてようやく。準備〜終了まで2時間以上かかる。歯磨きは週2回程度で抜けが多い。下着は3日同じものを着ていても気にならない。」
- 「洗濯機は回せても干せない。洗濯物が溜まり、同じ服を着続ける。虫歯の痛みがあるが受診の段取りが組めず放置している。」
NG例(弱い)
- 「お風呂に入るのが億劫です。」
③ 金銭管理と買い物(不安ではなく、管理能力の欠如)
チェック(事実にする質問)
- 家賃・公共料金の支払いはできている?
- 支払い用紙を開封できる?期限を守れる?
- 必要な買い物(食料品・日用品)ができる?
- 衝動買い・浪費・不要契約はある?(躁など)
- 通帳・カードは自分で管理できる?誰かが管理?
OK例(事実)
- 「支払い用紙を開封できず放置し、電気(またはガス)が止まったことがある。金銭管理は家族が通帳を保管している。」
- 「衝動性が強まり、必要のない物をネットで複数購入した。後から請求が来て初めて気づく。買い物は人混みでパニックになり、単独では難しいため家族が同行している。」
NG例(弱い)
- 「お金がなくて不安です。」
④ 通院と服薬(意思ではなく、実行の安定性)
チェック(事実にする質問)
- 通院を自分で予約できる?当日行ける?
- 交通機関が使える?付き添いが必要?
- 服薬は自己管理できる?飲み忘れは週何回?
- 薬を取りに行ける?(薬局で待てる?)
- 飲み過ぎ・中断など危険行動はない?
OK例(事実)
- 「通院は一人では不安で行けず、家族が同行。予約の電話は取れない。服薬は自己管理できず、家族が1回分ずつセット。飲み忘れは週2回ある。」
- 「外出の準備に時間がかかり、通院日に家を出られずキャンセルが続いた。薬が切れたが受け取りに行けず数日中断したことがある。」
NG例(弱い)
- 「通院はつらいです。薬は飲んでいます。」
⑤ 他人との意思伝達・対人関係(人付き合いの苦手ではなく、生活上の支障)
チェック(事実にする質問)
- 家族以外と会話できる?どれくらい?
- 電話に出られる?役所や病院の連絡ができる?
- インターホンに出られる?宅配を受け取れる?
- 近所・職場・友人との関係は維持できている?
- 対人場面での症状(動悸、パニック、フリーズ)は?
OK例(事実)
- 「電話は動悸がして出られない。役所や病院への連絡ができず、家族に代行してもらっている。インターホンに出られず居留守が続き、宅配便を3回連続で受け取れなかった。」
- 「会話は家族に対しても短文のみ。来客があると部屋に閉じこもり、2時間以上出られない。」
NG例(弱い)
- 「人と話すのが苦手です。」
⑥ 身辺の安全保持・危機対応(危険が“ある”ではなく、管理できない事実)
チェック(事実にする質問)
- 火の管理(コンロ・タバコ)はできる?
- 戸締り・鍵・ガス栓の確認ができる?
- 体調悪化時に助けを求められる?受診できる?
- 希死念慮があるとき、具体的行動が出る?
- 事故やヒヤリハットの経験は?
OK例(事実)
- 「コンロの火を消し忘れが不安で調理できない。家族がいるとき以外は火を使わない。」
- 「希死念慮が強い時期があり、薬を溜め込んだ/遺書を書いた/ベランダから下を見下ろしてしまう等の行動が出る。体調が急落しても自分で受診の段取りが組めず、家族が手配する。」
※ここは表現が強すぎると危険に見えるだけで、支援につながっていない印象になることがあります。
「誰が見守っているか」「安全のための対応(家族管理、受診、支援機関)」も併記すると安定します。
NG例(弱い)
- 「死にたい気持ちがあります。」(事実がない、危機管理の状況が不明)
⑦ 社会性(参加意欲ではなく、社会生活の維持ができない事実)
チェック(事実にする質問)
- 役所手続き、郵便の開封、書類管理ができる?
- 予定を立てて実行できる?(遅刻・忘れ)
- 近所づきあい、公共の場での振る舞いが保てる?
- 生活リズム(昼夜逆転)で社会生活が崩れていない?
- 支援(家族・ヘルパー・就労支援等)なしで成り立つ?
OK例(事実)
- 「郵便物を開封できず放置し、重要書類を見落とす。役所手続きは一人ではできず家族が同行・代行。」
- 「予定を守れず、準備に2時間以上かかって外出できない。昼夜逆転が続き、午前の予定はほぼ実行不能。」
- 「社会活動(地域の用事、手続き、対外連絡)を自分で回せず、支援がなければ生活が維持できない。」
NG例(弱い)
- 「社会復帰したい気持ちはあります。」
6-2 7項目を“医師と審査”に届く形にするコツ(仕上げ)
7項目を埋めたら、最後にこの2点をチェックしてください。
チェック①「できない」を“具体例”で裏打ちできているか
- 「できない」だけで終わっていないか
- 何が起きたか(結果)まで書けているか
チェック②「援助」が見えるか(ここが等級を左右しやすい)
- 独力か、助言があればできるか、介助が必要か
- 誰が、どの頻度で、何をしているか
第6章の結論:7項目は“生活の事実”のチェック表
この章でやったことは、あなたの生活を「事実の言語」に翻訳する作業です。
次章では、その事実を医師に正しく伝え、診断書の評価をズラさないための
- 診察室の“仮面”問題
- 医師に渡すメモのテンプレ
- 診断書依頼前のすり合わせ
に入ります。ここが、申請の成否を分けることが多いです。
第7章 【最重要】診断書は“依頼前”が勝負(医師とのすり合わせ術)
障害年金で一番つらいのは、ここです。
- 診断書を書いてもらった
- でも、内容が軽い/生活の困難さが反映されていない
- 「違う」と言いたいが、言いづらい
- そして、書き直しをお願いできず詰む
この流れ、本当に多いです。
だから結論から言います。
相談のタイミングは、医師に診断書を依頼する前が望ましい。
診断書が出来上がってから「思っていたのと違う」となっても、
一度書いた診断書を大幅に書き直してもらえる可能性は低いことが多いからです。
診断書は、申請の心臓部です。
ここでズレると、申立書だけ工夫しても限界があります。
7-1 なぜ診断書は「軽め」になりがちなのか(医師が悪いわけではない)
医師が意地悪しているわけではありません。現実的に、次の事情があります。
- 診察時間が短い(生活全体の聞き取りには足りない)
- 患者は“診察室の仮面”をかぶる(頑張って話してしまう)
- 医師が見ているのは「診察室のあなた」で、家でのあなたが見えない
- 「辛い」とだけ言われても、診断書の評価に落とし込みにくい
つまり、診断書が軽い原因は多くの場合、
医師の頭の中にある「あなた像」と、実際の生活実態が一致していないことです。
7-2 診察室の仮面を剥がす(ここが勝負)
あなたは診察の場で、こうしていませんか?
- 身だしなみを整えてしまう
- きちんと受け答えしてしまう
- 「調子どう?」に反射で「大丈夫です」と言ってしまう
- 本当は地獄でも、医師の前だと“それなり”に見えてしまう
その結果、医師の中ではこうなります。
「通院できている」「受け答えもできている」
=「生活はそこそこ保てているのかも」
ここをひっくり返すのが、第5〜6章で作った「事実」です。
7-3 医師に渡す「生活実態メモ」(最強の武器)
口頭で全部伝えるのは無理です。時間も、気力も足りない。
だから、紙で渡すのが最も効率的です。
メモのタイトル(おすすめ)
「日常生活の状況メモ(診断書作成の参考にしてください)」
書く内容(これだけでOK)
- 7項目(食事・清潔・金銭・通院服薬・対人・安全・社会性)
- 各項目は、必ず
頻度/時間/援助/結果 の4点を入れる - 「診察に来るために無理をしている」事実(反動で寝込む等)
例文(そのまま使えます)
先生の前では何とか話していますが、通院のために前日から準備し、薬を多めに飲んで無理して来ています。
帰宅後は反動で1〜2日寝込みます。
家では次の状態です。
・入浴:週1回。家族の声かけと準備がないとできません。
・食事:1日1回。買いに行けない日は食べません(週2回)。
・服薬:自己管理できず、家族が1回分ずつセットしています。
・対人:電話に出られず、インターホンも出られず居留守が続きます。
・危機対応:火の管理が不安で調理できません。
このメモがあると、医師は「診察室のあなた」だけで判断しなくて済みます。
診断書の評価に落とし込みやすくなります。
7-4 切り出し方(医師に嫌がられにくい言い方)
医師に「診断書をお願いします」と言うのは緊張します。
そこで、角が立ちにくい言い方をテンプレ化します。
切り出しテンプレ(おすすめ)
障害年金の申請を考えています。
診断書をお願いしたいのですが、診察室だと本当の生活状況が伝わりにくい気がして不安です。
家での様子をまとめたメモを持ってきました。診断書作成の参考にしていただけますか?
ポイントは、
- 医師を責めない
- 「不安だから補足資料を渡す」という形にする
これだけです。
7-5 診断書の“依頼前”にやるべきこと(ここで勝負が決まる)
診断書は「書く直前」の情報で形が決まりやすいです。
だから、依頼前に最低限これを整えます。
依頼前チェックリスト
- 初診日・受診歴の大枠が固まっている
- 直近1〜2週間の生活実態メモ(ロボット視点)がある
- 7項目のうち崩れているところが具体例で書ける
- 援助の内容(誰が何をどれだけ)を説明できる
- 就労の状況は「感情」ではなく「能力の低下(事実)」で書ける
社労士に相談するなら、診断書を医師に依頼する前が望ましい。
診断書が出来上がってから「違う」となっても、大幅修正は難しいことが多いからです。
7-6 診断書が出来上がった後に見るべきポイント(最低限)
出来上がった診断書を受け取ったら、感情で判断せず、次だけ見ます。
- 日常生活能力(7項目)の評価が、あなたの生活実態メモと大きくズレていないか
- 援助の必要性が反映されているか
- 就労状況が「能力の低下(事実)」として整合しているか
ズレがある場合は、次章の「申立書」で無理矢理合わせるのではなく、
まず医師の認識ズレがどこにあるかを確認し、可能なら補足メモで埋める方が安全です。
第7章の結論:診断書は“医師の認識”が全て
- 診断書が軽くなる最大の理由は、医師の中のあなた像と生活実態がズレていること
- そのズレを埋めるのが「生活実態メモ」
- そして、勝負は 診断書を依頼する前に決まる
次章では、診断書と矛盾しない形であなたの事実を補強する
病歴・就労状況等申立書のテンプレ(整合性の作り方)に入ります。
診断書は依頼前の準備で結果が変わりやすいポイントです。
「医師に何をどう伝えるか」「別紙(生活実態メモ)をどう作るか」を整理してから依頼すると、ズレが起きにくくなります。
電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。
第8章 【書類作成】病歴・就労状況等申立書の書き方(本紙+別紙で“読みやすく・書きやすく”)
診断書が「医師の評価(点数)」だとしたら、申立書は何か。
申立書は、診断書の評価を“事実(エピソード)”で補強する書類です。
よくある誤解はこれです。
- 「申立書で盛れば通る」→ ×
- 「診断書と同じ文章をコピペする」→ ×
- 「とにかく辛さを書き連ねる」→ ×
申立書の役割は、診断書の評価に対して「だからそうなる」という生活の事実を添えることです。
これがいわゆる「整合性」です。
そして、ここからが実務のコツです。
「現在の日常生活の状況」は書くべきことが多い一方、申立書の枠は狭く、無理に詰め込むと読みにくくなります。
そこでおすすめなのが、日常生活の詳細を“別紙”にまとめる方法です。
本紙(申立書)は時系列中心、別紙は生活実態中心。これが一番読みやすく、書きやすいです。
8-1 整合性とは「同じ文言」ではない(評価×根拠の関係)
整合性とは、診断書と申立書が“同じ言葉”になることではありません。
正しい整合性はこうです。
- 診断書:清潔保持が「助言・指導があればできる」/「行えない」
- 申立書(本紙+別紙):
- 本紙:現在「入浴は週1回。家族の援助が必要」と要約
- 別紙:週1回である具体例、援助の内容、できないと何が起きる(結果)
→ だから評価が低いと読める
つまり、診断書の点数を、あなたの生活ログで裏打ちする。
これが審査に届く書き方です。
8-2 最強の考え方:申立書は「本紙=時系列」「別紙=生活実態」で分ける
申立書の情報は大きく2つです。
- 病歴(時系列):発症〜初診〜現在までの流れ(本紙)
- 現在の生活:日常生活能力(7項目)の事実(別紙)
この2つを分けると、メリットが大きいです。
- 本紙が読みやすい(時系列がスッと入る)
- 別紙で生活実態を十分に書ける(枠不足問題が消える)
- 診断書と照合しやすい(7項目で対応が取れる)
- 書き手も楽(“日記/ログ”の延長で書ける)
8-3 【本紙】時系列テンプレ(改訂版・コピペ用)
以下の枠をそのまま使ってください。
(※日付は分からない時は「○年○月ごろ」でOK。正確さより順序)
【A-1】発症(症状の出始め:いつ頃から、何が起きたか)
- 症状が出始めた時期:○年○月ごろ(例:転職前後、出産後、受験期などでも可)
- 当時の状況(生活・仕事・家庭):例「残業が続いていた」「育児で睡眠不足」など
- 出ていた症状(事実で):
- 睡眠:例「寝つけない/途中覚醒が毎晩」
- 生活:例「朝起きられず欠勤が増えた」
- 食事:例「1日1回以下になった」
- 対人:例「電話が取れなくなった」
- 生活への影響(事実):例「家事が止まった」「遅刻が増えた」など
コツ:感情ではなく、行動(できなくなったこと)を中心に書く。
【A-2】初診(初めて病院に行った場面:きっかけ+受診内容)
- 初診の時期:○年○月ごろ
- 初めて受診した医療機関名(科):○○病院(内科/心療内科/精神科など)
- 受診に至った“きっかけ”(出来事があると書きやすい):
- 例「欠勤が続き会社から受診を勧められた」
- 例「家族に連れられて受診した」
- 例「不眠が悪化し内科を受診した」
- 例「パニックで外出できなくなった」
- 初診時の状態(事実):例「起床が午後」「食事が1日1回」「入浴が週1回」など
- 初診後の対応(分かる範囲で):薬開始/休職指示/紹介状/次回予約など
【B】治療経過(転院・入退院・服薬の変化)
- 転院の流れ(順番):A病院→B病院→…
- 治療の節目:例「薬が増えた」「入院」「デイケア開始」
- 波(双極など):良い時期/悪い時期の実態(反動で寝込む等)
【C】悪化の節目(生活が崩れた“事実”)
- 悪化した時期:○年○月ごろ
- 何ができなくなったか(事実):
- 入浴:週○回に低下
- 食事:○回に低下
- 外出:不可
- 連絡:電話不可
- 援助が必要になった内容:誰が何を代行/同行
【D】現在の状態(本紙は“要約”に留め、詳細は別紙へ)
- 現在の状態(要約・2〜5行):
例「直近1〜2週間は起床が午後で、食事は1日1回。入浴は週1回で家族の促しが必要。電話・インターホンに出られず対外連絡は家族が代行。服薬は自己管理できず家族管理。」 - 詳細:別紙『日常生活状況(生活実態メモ)』参照(提出書類として添付)
コツ:本紙は“時系列の説明”に集中し、生活実態の詳細は別紙で厚く書く。
8-4 【本紙】就労状況を書くときの型(“感情”ではなく“機能低下”)
就労の話は「結果」です。書くなら機能低下で書きます。
就労テンプレ(コピペ用)
- 就労形態:正社員/パート/休職中/退職など
- 勤務日数・時間:週○日、○時間
- 困難(事実):
- 身支度に○時間かかる
- 指示が理解できず、メモが取れない
- 電話が取れない
- 遅刻・欠勤が週○回
- 配慮や調整:業務軽減、配置転換、在宅など
- 結果:休職、退職、出勤困難
8-5 【別紙】日常生活状況(生活実態メモ)テンプレ(提出用)
本紙のD欄で「別紙参照」としたら、次の別紙を作ります。
(診断書の7項目と対応が取れるので、審査側にも読みやすい形です)
別紙の冒頭(固定文)
別紙:日常生活状況(生活実態メモ)
対象期間:直近1〜2週間(○年○月○日〜○月○日)
記載方針:各項目は 頻度/時間/援助/結果 をできるだけ入れる。
1)生活リズム
- 起床:平均○時(最遅○時)/就寝:○時
- 睡眠:○時間、途中覚醒:有/無
- 昼夜逆転:有/無(具体:週○日)
2)適切な食事
- 回数:1日○回(欠食:週○回)
- 内容:例「パン・カップ麺中心」/自炊:可/不可
- 援助:買い物の同行・代行(誰が、週○回)
- 結果:体重変動、栄養の偏り、食べられない日が続く等
3)清潔保持
- 入浴:週○回(シャワーのみ等)
- 洗顔・歯磨き:週○回
- 着替え:同じ服○日続くことがある
- 援助:声かけ・準備(誰が、週○回)
- 結果:皮膚トラブル、口腔トラブル等
4)金銭管理と買い物
- 支払い:期限内にできる/できない(遅延の有無)
- 管理:通帳カードは本人/家族管理
- 買い物:単独可否、人混みでの症状
- 結果:停止、不要契約、衝動買い等
5)通院と服薬
- 通院:単独可否/同行必要(誰が、月○回)
- 予約・連絡:本人可否(電話が取れない等)
- 服薬:自己管理可否、飲み忘れ(週○回)、飲みすぎ
- 結果:中断、症状悪化等
6)他人との意思伝達・対人関係
- 会話:家族以外との会話頻度
- 電話:取れる/取れない(代行の有無)
- インターホン:出られる/出られない
- 結果:手続きが進まない、宅配を受け取れない等
7)身辺の安全保持・危機対応
- 火の管理:可否(不安で調理不可など)
- 戸締り:確認できる/できない
- 危機時:症状悪化時に助けを求められるか
- 結果:ヒヤリハット、事故リスク等
※希死念慮がある場合は「行動」と「安全確保(見守り・受診など)」も併記
8)社会性
- 郵便物:開封できる/放置する
- 予定:立てられる/実行できない(遅刻・忘れ)
- 手続き:本人可否、同行・代行の有無
- 結果:重要書類の見落とし、期限切れ等
9)援助の全体像(ここが強い)
- 援助者:誰が(同居家族・支援者)
- 内容:声かけ/同行/代行/家事/金銭管理
- 頻度:週○回、毎日など
- 援助がないとどうなるか(結果)
8-6 NG例 vs OK例(本紙・別紙どちらでも効く)
例①(対人)
NG:「人が怖い。不安で仕方ない」
OK:「電話は動悸で出られない。役所・病院への連絡は家族が代行。インターホンに出られず居留守が続き、宅配を3回連続で受け取れなかった」
例②(清潔)
NG:「お風呂に入る気力がない」
OK:「入浴は週1回。家族の声かけと準備がないと動けない。準備〜終了まで2時間以上かかる。下着は3日同じものを着ることがある」
例③(就労)
NG:「職場の人間関係が辛くて泣いた」
OK:「身支度に2時間以上かかり遅刻が増加。指示内容が頭に入らず、メモが取れず作業が止まる。電話の着信で動悸が出て受話器が取れず、トイレに避難する時間が増えた」
8-7 整合性チェックリスト(提出前にここだけ見ればOK)
【チェック①】診断書の評価と矛盾していないか
- 診断書で「できる」なのに、別紙で「全くできない」と断言していないか
→ どうしてもズレる場合は「波」「日による差」を事実で説明する
【チェック②】“感情語”だけで終わっていないか
- 「辛い」「不安」だけで段落が終わっていないか
→ 必ず「行動(不行動)」「頻度」「援助」「結果」を入れる
【チェック③】期間が混ざっていないか
- 現在(直近1〜2週間)と過去の節目が混ざっていないか
→ 本紙は時系列、別紙は直近期間、と役割を固定する
【チェック④】援助が書けているか(ここが効く)
- 誰が、週何回、何をしているか
→ 別紙の「援助の全体像」は必ず書く
【チェック⑤】初診日・受診歴が崩れていないか
- 病院名・順番が大きく矛盾していないか
→ 不明な部分は「○年○月ごろ(記憶の範囲)」と書く
第8章の結論:本紙は“時系列”、別紙は“生活実態”で勝つ
- 申立書は、診断書の評価を「生活の事実」で補強する書類
- 本紙に詰め込まず、別紙で日常生活の詳細を厚く書くと読みやすい
- 「頻度/時間/援助/結果」を揃えると審査に届く
第9章 【ケース別】等級を分けるのは“病名”より“生活の事実”
ここまでで、申請の考え方は一本にまとまりました。
- 感情ではなく、生活の事実(頻度・時間・援助・結果)
- 診断書は依頼前のすり合わせが勝負
- 申立書は本紙(時系列)+別紙(生活実態)で読みやすくする
この章では、疾患(うつ、双極、発達など)ごとに、審査に届きやすい“事実の出し方”を整理します。
重要:障害年金は「病名で決まる」わけではありません。
どれだけ日常生活が壊れているかで決まります。
同じ病名でも、書ける事実が違えば、結果も変わります。
9-1 うつ病・双極性障害(気分障害):ポイントは「波」と「反動」
気分障害で重要になりやすいのは、次の2つです。
ポイント①「良い日」の実態(“できているように見える”のが落とし穴)
診察室では話せても、家では崩れている。
このギャップを事実で示します。
- 「通院できる=生活できている」ではない
- 通院のために前日から準備し、帰宅後に反動で寝込む
- “良い日”でも健常時の50%程度で、無理すると数日崩れる
書くべき事実(例)
- 外出できるのは通院の日だけ(月○回)
- 通院前後は○日寝込む
- 家事は週○回しか回らない(ゴミ出し、洗濯など)
ポイント② 双極性障害は「躁が元気」ではない(病的な行動)
躁状態は“調子が良い”ではなく、生活破綻に直結することがあります。
書くべき事実(例)
- 睡眠時間が2〜3時間でも動き回り、その後虚脱で寝込む
- 衝動買い・不要契約・散財
- 対人トラブル(過度な連絡、攻撃性、SNS等)
9-2 発達障害(ASD/ADHD等):ポイントは「能力のアンバランス」と「二次障害」
発達障害は、気分の落ち込みだけで語ると弱くなりがちです。
核になるのは「能力の偏りが生活や社会適応を壊している事実」です。
ポイント① うつのような“気分”ではなく「できない行動」が主役
書くべき事実(例)
- マルチタスクでフリーズし、家事・手続きが進まない
- 予定の管理ができず、忘れる/遅刻が多発
- 書類が開封できず、支払いが滞る
ポイント② 二次障害(適応障害・うつ状態)で生活が崩れている
発達特性そのものより、二次障害で生活が破綻しているケースが多いです。
「特性+二次障害」の結果として生活が維持できないことを、別紙で厚く書きます。
ポイント③ 感覚過敏や対人の困難は“生活への影響”で出す
書くべき事実(例)
- スーパーの騒音でパニック→買い物ができない
- 電話・インターホンが恐怖で出られず、手続きが止まる
- 文字情報の処理が苦手で、役所書類が読めない
9-3 統合失調症圏:ポイントは「症状名」より「生活維持の困難・援助」
この領域は、症状の説明よりも「生活がどれだけ支援を要するか」が通りやすいです。
書くべき事実(例)
- 服薬の自己管理ができず、家族が管理
- 体調悪化時に受診の段取りが組めない
- 対外連絡・買い物・手続きが単独では不可
- 一人暮らしが維持できない(見守りが必要)
9-4 共通で効く“強い事実”ベスト7(疾患を問わず刺さる)
疾患に関係なく、審査側が判断しやすいのは次のタイプです。
- 入浴・清潔が維持できない(頻度で出る)
- 食事が不安定(欠食/買えない/自炊不可)
- 服薬・通院が自己管理できない(援助が必要)
- 電話・インターホンに出られず対外連絡が止まる
- 金銭管理・支払いができず、停止や延滞がある
- 火の管理・戸締りなど安全が不安で、生活の選択が制限される
- 郵便物・手続きが止まり、社会生活が維持できない
これらは「辛い」ではなく「機能の低下」を示す事実で、比較可能です。
別紙(生活実態メモ)に、頻度・援助・結果をセットで書きます。
第9章の結論:あなたの“ケース”に合わせて、事実の出し方を最適化する
- 病名ではなく、生活の壊れ方(事実)で決まる
- 疾患ごとに「伝えるべき事実の型」がある
第10章 【Next Action】今日からできる申請準備チェックリスト(初回相談〜提出まで)
ここまで読んで、「やることは分かった。でも何から?」となるのが普通です。
この章は、迷いを消すための 行動手順書 です。上から順に潰せば進みます。
10-1 まず最初の30分でやること(ここが起点)
① 受診歴メモを作る(初診日の当たりをつける)
- 最初に受診した医療機関名
- 時期(○年○月ごろでOK)
- 転院の順番(分かる範囲)
- 科(内科→心療内科…など)
正確な日付は不要でも、これがないと窓口が一般論になりがちです。
「初診日が分かったらまた来てください」で止まるのを防ぎます。
② 直近1週間ログをつける(ロボット視点)
- 起床・睡眠
- 食事回数と内容
- 入浴・歯磨き・着替え
- 外出の有無
- 服薬(自己管理できたか)
- 電話/インターホン/対人
- 家族の援助(誰が何をしたか)
10-2 初回相談に持って行く最小セット(これで話が進む)
- 基礎年金番号が分かるもの(ねんきん定期便など)
- 本人確認書類
- 振込口座情報(通帳など)
- 受診歴メモ(初診日メモ)
- 直近1週間ログ(できれば)
10-3 窓口の考え方(原則と実務のおすすめ)
制度上、国民年金の原則窓口は市役所・区役所です。
ただし、実務上は次が最もスムーズです。
年金事務所で事前相談 → そのまま同じ担当者で提出まで進める(担当者固定)
次回予約をその場で取り、同じ人を指名できる状況を作る。
年金事務所は年金業務の専門部署で、論点整理が進みやすい。
一方、市役所・区役所は住民票や戸籍などの取得が同じ庁舎でしやすいメリットがあります。
(証明書だけ市役所で取る、という使い分けが現実的です)
≪もっと知りたい!!≫
○この完全ガイドは「制度と書類の全体像」です。
窓口の分岐や電話番号など、地域の動き方は地域別ページが早いです。
10-4 診断書を依頼する前に必ずやること(ここが勝負)
「診断書を書いてください」と言う前に、次の準備をします。
① 生活実態メモ(別紙)を作る
別紙テンプレに沿って、7項目(食事・清潔・金銭・通院服薬・対人・安全・社会性)を埋める。
書き方は必ずこれ:
- 頻度/時間/援助/結果
② 医師に渡すメモを用意する(1枚でOK)
タイトル例:「日常生活の状況メモ(診断書作成の参考にしてください)」
内容は“崩れている事だけ”を書く(「できる」事を書かない)
③ 相談のタイミングは「依頼前」
診断書が出来上がってから「思ってたのと違う」となっても、
一度書いた診断書を大きく修正してもらえる可能性は高くありません。
だから、診断書を依頼する前に準備・相談が望ましいです。
10-5 申立書は「本紙+別紙」で作る(読みやすさ優先)
- 本紙:時系列(発症→初診→治療経過→悪化→現在の要約)
- 別紙:日常生活状況(生活実態メモ)を厚く書く
本紙に生活の詳細を詰め込むと読みにくくなるので、別紙分離が合理的です。
10-6 提出前の最終チェック(落とし穴を潰す)
① 初診日・受診歴の整合
- 病院名、順番、時期が大きく矛盾していないか
② 診断書と別紙の整合
- 診断書が「できる」なのに、別紙で「全くできない」と断言していないか
(波があるなら、波を事実で書く)
③ 援助が書けているか
- 誰が、どの頻度で、何をしているか
- 援助がないとどうなるか(結果)
第10章まとめ:最短ルートはこれ
- 受診歴メモ(初診日の当たり)
- 1週間ログ(ロボット視点)
- 年金事務所で相談(担当者固定で提出まで)
- 診断書依頼前に、生活実態メモを作って医師に渡す
- 申立書は本紙(時系列)+別紙(生活実態)
第11章 【Q&A】よくあるつまずきと対処法(ここで止まらない)
障害年金は、途中で止まりやすいポイントがだいたい決まっています。
この章は「詰まった時の抜け道」集です。
Q1. 初診日が分かりません。相談に行っても意味ありますか?
A. 意味はあります。ただし“受診歴メモ”を作ってから行くと一気に進みます。
初診日が完全に不明だと、窓口では一般論になりやすく、
「初診日が分かったらもう一度来てください」となりがちです。
対処(最低限)
- 初診の病院名(不確かでも候補)
- 時期(○年○月ごろ、転職前後など)
- 転院の順番
これを箇条書きで用意します。
次の一手
- 年金事務所で相談(担当者固定で継続)
- 「初診日を固めるために、次に何の資料が必要か」を確認して動く
≪もっと知りたい!!≫
Q2. 初診の病院が閉院していて、カルテがないと言われました。詰みですか?
A. 詰みではありません。“追える証拠”から初診日に近づけます。
カルテがないケースは珍しくありません。
この場合は、残っている記録で“周辺から固める”考え方をします。
対処(使えることが多い材料)
- 現在の病院の紹介状・診療情報提供書(過去の受診歴が書かれていることがある)
- お薬手帳(開始時期の推定)
- 領収書、予約票、検査結果
- 健康保険の受診記録(分かる範囲)
次の一手
- 受診歴メモを更新し、年金事務所で「初診日認定の段取り」を確認
- 初診日が特定できない場合でも申請できる場合がある(要相談)
≪もっと知りたい!!≫
Q3. 初診が内科で、後から心療内科に移りました。初診日はどっちですか?
A. 原則は“原因となった症状で最初に受診した日”です。
例えば不眠・動悸・体調不良で内科受診→後に精神科、という流れはよくあります。
この場合、内科受診が障害の原因と連続しているなら、内科が初診になることがあります。
対処
- 内科受診時の症状が、現在の傷病と連続しているかを整理
- 受診歴メモに「当時の症状(事実)」を書いておく
次の一手
- 年金事務所で「初診の取り扱い」を確認(担当者固定で進めると楽です)
Q4. 生活は崩れているのに、診断書が軽い(2級っぽくない)です
A. ほとんどは“医師の認識ズレ”です。診断書依頼前のすり合わせが鍵。
診察室では話せてしまう、身だしなみを整えて行けてしまう——
それだけで医師の評価が軽くなることがあります。
対処(最優先)
- 別紙「生活実態メモ」を作り、医師に渡す
- 「診察室だと実態が伝わりにくいのでメモを作りました」と切り出す
次の一手
- 診断書の評価と、別紙の事実が一致するように「材料」を揃える
- “感情”ではなく「頻度/援助/結果」で伝える
≪もっと知りたい!!≫
Q5. 診断書を医師に頼んだ後で、内容が違うと気づきました。書き直してもらえますか?
A. 可能性はありますが、高くはありません。だから“依頼前”が理想です。
一度完成した診断書の大幅修正は、医師側の負担も大きく、難しいことが多いです。
対処
- まず「不足している事実」を別紙で整える(生活実態メモ)
- 医師には「診断書作成の参考として追加メモを作った」と丁寧に渡す
- いきなり修正要求ではなく、「補足資料」を出す形が角が立ちにくいです
次の一手
- 次回以降は必ず「依頼前に生活実態メモ→すり合わせ」をセットにする
Q6. 働いていると不利ですか?(就労中でも可能?)
A. “働いている=不可”ではありません。ただし、生活の崩壊が書けないと弱くなります。
就労がある場合、審査側は「社会生活が成り立っている」と見やすい。
だからこそ、就労の話より先に、生活の土台の崩れを事実で出す必要があります。
対処
- 就労は「感情」ではなく「機能低下(事実)」で書く
- 生活は別紙で厚く(頻度・援助・結果)
次の一手
- できていることも少し書いて“波”を説明(無理している実態を出す)
≪もっと知りたい!!≫
Q7. 家族の援助が多いのに、本人が「自分でやってます」と言ってしまいます…
A. それが一番もったいないです。援助は“等級の材料”です。
援助がある=甘えている、ではありません。
援助が必要な状態であること自体が、生活能力低下の証拠になります。
対処
- 別紙に「誰が、週何回、何をしているか」を具体的に書く
- 例:服薬セット、予約電話代行、買い物同行、金銭管理、声かけ 等
次の一手
- 家族に聞き取りし、「本人が自覚していない援助」も拾う
Q8. 窓口は市役所・区役所ですか?年金事務所ですか?
A. 原則は市役所・区役所(国民年金)ですが、実務上は年金事務所で相談・提出まで進めるのがおすすめです。
理由は2つ。
- 年金業務の専門性が高く、論点整理が進みやすい
- 次回予約をその場で取り、同じ担当者で進めやすい(担当者固定)
市役所・区役所は、住民票や戸籍などを同じ庁舎で揃えやすいメリットがあります。
ただ、申請を前に進めるなら、年金事務所で継続相談→提出まで、が最短になりやすいです。
≪もっと知りたい!!≫
○この完全ガイドは「制度と書類の全体像」です。
窓口の分岐や電話番号など、地域の動き方は地域別ページが早いです。
Q9. 不支給になったら終わりですか?
A. 終わりではありません。まず“どこで負けたか”を特定します。
不服申立としての審査請求や、再請求といった道があります。まずは「なぜ駄目だったか」を考えましょう。
不支給の原因は大きく3つに分かれます。
- 初診日・納付要件など、制度要件で止まった
- 診断書の評価が軽い(材料不足・認識ズレ)
- 申立書と診断書の整合性が弱い(裏付け不足)
対処
- 決定理由(どこが争点か)を整理
- 別紙(生活実態メモ)を作り直し、材料の不足を埋める
- 必要なら専門家に相談し、戦略を立て直す
次の一手
- 「感情」ではなく「事実」を増やす
- 医師の認識ズレを埋める(メモで伝える)
第11章まとめ:詰まったら「材料(事実)」に戻る
- 初診日が曖昧 → 受診歴メモ
- カルテがない → 追える証拠から固める
- 診断書が軽い → 生活実態メモで認識ズレを埋める
- 就労中 → 生活の崩壊を先に出す
- 不支給 → どこで負けたか特定し、材料を増やす
第12章 まとめ:事実を伝えることは、自分を守ること(最後にやること一覧)
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
最後に、いちばん大事なことを一言で言います。
障害年金は「苦しさの競争」ではありません。
あなたの生活がどれだけ崩れているかを、事実として伝える制度です。
「辛い」「不安」「苦しい」——それ自体は本物です。
ただ、審査が判断できる共通言語に翻訳しないと、書類の上では伝わりにくい。
だから、このガイドは一貫してこう言ってきました。
- 感情より事実
- 就労より生活
- 診断書は依頼前のすり合わせが勝負
- 申立書は本紙(時系列)+別紙(生活実態)で読みやすく
12-1 このガイドの結論(3つだけ覚えてください)
① 「辛い」を「生活の事実」に変換する
- 頻度(週○回)
- 時間(○分/○時間)
- 援助(誰が何を)
- 結果(放置すると何が起きる)
この4点が入ると、審査側が判断できる文章になります。
② 就労は“結果”。土台は日常生活能力
仕事の話は大事です。ただ、等級の勝負所では「生活の崩壊」が土台になります。
生活が崩れているから就労も崩れる——この順番で書くのが強いです。
③ 勝負は診断書の前に決まる
診断書を書いてもらってから「思っていたのと違う」となるケースは多い。
でも、診断書の大幅修正は難しいことが多い。
だから、診断書依頼前に生活実態メモを作り、医師の認識ズレを埋めます。
12-2 最終チェックリスト(この順で進めればOK)
Step1:初診日・受診歴の土台を作る
- □ 受診歴メモを作った(病院名・時期・転院順)
- □ 初診日の当たりがついた(完璧な日付でなくてOK)
Step2:生活の事実を集める(ロボット視点)
- □ 直近1週間ログをつけた
- □ 7項目(食事・清潔・金銭・通院服薬・対人・安全・社会性)に整理できる
Step3:窓口で段取りを決める(手戻り最小)
- □ 年金事務所で相談した(原則が市役所・区役所のケースでもOK)
- □ 次回予約をその場で取った(担当者固定ができると楽)
国民年金の窓口は原則市役所・区役所ですが、実務上は年金事務所で相談・提出まで進めるのがおすすめです(専門性+担当者固定)。
Step4:診断書を依頼する前に、医師へ渡す材料を作る
- □ 「生活実態メモ(別紙)」を作った(頻度/時間/援助/結果)
- □ 医師に渡す「メモ」を用意した
Step5:申立書を仕上げる(本紙+別紙)
- □ 本紙:時系列(発症→初診→経過→悪化→現在の要約)
- □ 別紙:日常生活状況(生活実態メモ)
- □ 診断書の評価と矛盾がない(波があるなら波を事実で)
12-3 「次に何をすればいいか」が分からなくなった時の合言葉
迷ったら、これに戻ってください。
「感情」ではなく「行動(不行動)」
「主張」ではなく「頻度・援助・結果」
「一発勝負」ではなく「担当者固定で前に進める」
12-4 最後に:あなたの生活を守るために
自分の「できないこと」を書き出すのは、しんどい作業です。
惨めに感じる人もいます。私もそうでした。
でも、それは「弱さの告白」ではありません。
あなたの生活を守るための、制度上の“証拠集め”です。
どうか、胸を張る必要はありません。淡々とでいい。
今のありのままの生活を、事実として書いてください。
その事実が、あなたの生活を守る盾になります。
≪もっと知りたい!!≫
ここまで読み進めたあなたは、すでに「申請の勝ち筋」を掴んでいます。
あとは、生活の事実(頻度・時間・援助・結果)をきちんと揃えて、診断書と申立書(本紙+別紙)を矛盾なく組み立てるだけです。
もし今、
- 初診日が曖昧で止まりそう
- 診断書が軽くなりそうで不安
- 別紙(生活実態メモ)をどう書けばいいか迷う
- 一度不支給になってしまった
こうした状況なら、早めに「どこが弱点か」を特定して、手戻りを減らすのがおすすめです。
特に、医師に診断書を依頼した後よりも、依頼する前の相談の方が、整えられる幅が大きくなります。
状況整理から一緒に進めたい方は、こちらからご相談ください。
電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。
≪もっと知りたい!!≫
○この完全ガイドは「制度と書類の全体像」です。
窓口の分岐や電話番号など、地域の動き方は地域別ページが早いです。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。