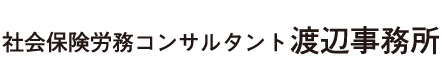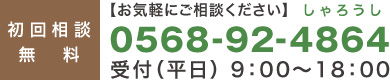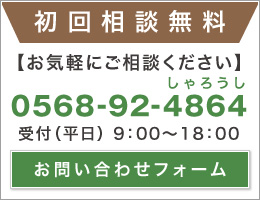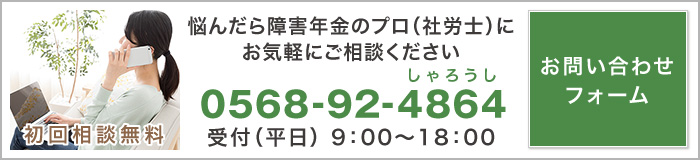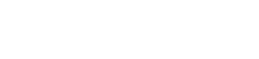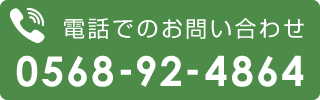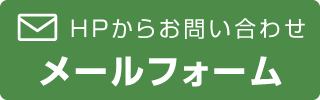精神の障害で「障害年金の等級がよく分からない」「2級と3級の違いをちゃんと知りたい」と悩んでいませんか。
このブログを書いているのは、春日井市を拠点に愛知県全域で障害年金請求を専門にしている社会保険労務士・渡邊智宏です。
私は自分自身、双極性障害(躁うつ病)を経験し、現在も障害厚生年金3級を受給しています。
「患者としての実感」と「社労士としての専門知識」の両方をもとに、精神障害で年金を考えている方の不安や疑問に、できるだけ寄り添ってお答えしたいと思っています。
この記事では、精神の障害年金における2級と3級の“本当の境界線”として、
「一人暮らしが支援なしで成り立つかどうか」という視点から、ガイドラインの考え方と実際の生活のイメージをわかりやすく解説していきます。

障害年金2級と3級の違いとは
精神の障害で障害年金を考えはじめると、必ずと言っていいほどぶつかる疑問があります。
「2級と3級って、どこで線が引かれているの?」
診断名は同じ。薬の量もむしろ自分の方が多い。
それでも、ある人は2級なのに、自分は3級。
あるいは「あなたの状態だと3級相当ですね」と言われてしまう——。
このとき、多くの方がこう考えます。
- 「自分の症状は、そこまで重くないってことなんだろうか?」
- 「もっとつらくならないと2級にはならないのかな?」
しかし、障害年金の等級は、「症状の重さ」だけで決まるわけではありません。
実際の審査で、もっとも重視されているのは、
『日常生活が、どこまで自力で成り立っているか』
という「生活能力」の部分です。
そして、この「生活能力」を分かりやすくイメージする物差しが、
支援なしで一人暮らしが成り立つかどうか
という観点です。
この記事では、障害年金の請求を専門としている社会保険労務士の立場から、
- ガイドラインが考える「2級」と「3級」の違い
- 「一人暮らしできる/できない」をどう捉えればよいのか
- ご自身がどのレベルに近いのかを確認するチェックポイント
- 医師や専門家に、生活の実態をきちんと伝えるコツ
を、できるだけ分かりやすくお話していきます。
精神障害年金の2級と3級:ガイドラインは何を見ているのか
まずは、公式な「ものさし」を軽く押さえておきましょう。
精神の障害で障害年金を請求する際には、
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
という、厚生労働省が示している基準が使われます。
細かく書くと難しくなりますので、ここではざっくりとイメージだけ掴んでください。
詳しくご覧になりたい方は、以下のリンクをどうぞ。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html
2級のイメージ
ガイドライン上、2級は次のような状態です。
- 日常生活が著しく制限されている
- 常に、あるいは頻繁に、誰かの援助が必要な状態
つまり、
「サポートがなければ、生活が回らなくなってしまう」
というレベルです。
3級のイメージ
一方の3級は、
- 日常生活にある程度の制限はある
- ただし、基本的なことはなんとか自力でできる
という状態です。
こちらは、
「時間はかかるし、効率は悪いけれど、ギリギリ自力で生活できている」
というイメージに近いです。
「症状の重さ」より「生活がどこまで自力で回っているか」
ここで重要なのは、
- 2級か3級かは、診断名や薬の量だけで決まらない
- 「どんな場面で」「どの程度」「手助けがないと生活できないのか」が重要
という点です。
同じ「うつ病」という診断名でも、
- 食事もとれず、家賃も払えず、通院も一人ではできない人
と、 - 体調にムラはあるものの、なんとか買い物も支払いもこなしている人
では、「日常生活能力」の評価は大きく変わってきます。
この差を、もっと分かりやすくイメージするためのキーワードが、
「一人暮らしが成り立つかどうか」
なのです。
そもそも「一人暮らしできる」とはどういう状態?
ここで、よくある勘違いを一つ整理しておきます。
「一人で住んでいる」 = 「一人暮らしができている」と考えてしまう方が、とても多いのです。
しかし、ガイドラインが見ているのは、「実際に一人で住んでいるかどうか」ではありません。
ガイドライン的な「一人暮らし」の意味
障害年金の審査で見るべき「一人暮らし」のイメージは、
家族などの支援が完全になくなっても、生命と社会生活を維持できるかどうか
という点にあります。
表現を変えると、
- 家族が急に県外に引っ越してしまった
- あるいは、支援者との連絡が途絶えてしまった
という状況を想像したときに、
「それでも、なんとか最低限の生活を維持できるか?」
ということです。
「支援付き一人暮らし」という実態
たとえば、こんなケースを考えてみてください。
- 住民票上は完全に一人暮らし
- でも実際には……
- 週に2回、親が大量の食料を持ってきて、冷蔵庫を埋めていく
- 家賃や光熱費の支払いは、すべて親が管理している
- 通院の予約や手続きも、親が電話して段取りしてくれている
- 郵便物は封を開けられず、届いたものはそのまま親に渡している
この場合、
「一人で住んでいる」けれど、「一人で暮らせている」とは言いづらい状態
といえます。
これは、私の感覚ではまさに、
“支援付き一人暮らし” = 2級に近い生活実態
です。
逆に、家族と同居しているからといって、必ずしも「援助がある」とは限りません。
- 一緒には住んでいるけれど、家族は仕事で朝から晩まで不在
- 食事の準備・洗濯・掃除などは、ほぼ自分で行っている
という方もいます。
だからこそ、同居か一人暮らしかという「形」だけで判断するのではなく、
「もし本当に一人になってしまったら、生活はどこまで維持できるのか?」
という視点が、2級と3級を考えるうえで非常に重要になってきます。
チェックリスト:2級相当?3級相当?「一人暮らし能力」を自己診断
ここからは、もう少し具体的に、ご自身の「一人暮らし能力」をセルフチェックしてみましょう。
前提として、次のように考えてください。
- いま家族が手伝ってくれている部分は、すべて取り除いて考える
- 「調子が良い日だけできる」のではなく、「平均するとどうか」で考える
- 「できるときもある」ではなく、「できない日が多いかどうか」を意識する
では、生活の場面ごとに見ていきます。
① 食事・買い物
3級に近い状態の例
- コンビニ・スーパーに行くのがつらい日もあるが、体調の良い日にまとめて買い物をするなどして、なんとか食事は途切れない
- 同じものばかり食べてしまう・栄養バランスはあまり考えられないが、「何も食べない日」が続くことは少ない
2級に近い状態の例
- 食欲はあっても、そもそも家の外に出られず、買い物に行けない日が多い
- 冷蔵庫の中身が空っぽのまま、数日〜1週間以上ほとんど何も食べられないことがある
- 消費期限が切れていることに気づかず、傷んだものを食べてしまう
- 調理や片付けに取りかかれず、コンロやシンクに食器・鍋が溜まり続けている
食事と買い物の面で、「支援がなければ何日くらいで行き詰まるか」をイメージしてみてください。
② 金銭管理・家賃・光熱費
3級に近い状態の例
- 支払期限を過ぎてしまうことはあるものの、通帳や請求書を見ながら、自分で振り込みや引き落としの管理ができている
- 銀行やコンビニに行くまで腰が重いが、数日〜1週間程度の遅れで、最終的には入金できる
2級に近い状態の例
- 何をいつ払うのかを整理できず、「支払期日」「支払先」「金額」が把握できない
- 督促状が届いても、自分で対応できずに放置してしまう
- 通帳やキャッシュカードは、家族がすべて管理している
- 「いくらお金が残っているのか」「どのくらい使ったのか」が全くわからない
お金の管理は、生活の土台です。
ここが自力でできない場合、「一人暮らしが本当に成り立つか」という点で、2級に近づいていきます。
③ 郵便物・役所関係の手続き
3級に近い状態の例
- ポストを開けるのはおっくうだが、数日に一度は中身を確認できる
- 封筒を開けて内容を理解し、時間はかかるものの、役所や会社への連絡が自分でできる
2級に近い状態の例
- ポストを開けること自体が怖くて、郵便物がたまってしまう
- 封筒を触るだけで不安が高まり、開封できずに放置してしまう
- 大事な書類や督促状であっても、誰かが開封し、中身を説明してくれないと何もできない
郵便物の管理や役所の手続きは、「社会生活を維持する力」の一部です。
ここがほぼ他人任せの場合、「支援なしの一人暮らし」は難しくなります。
④ 通院・服薬
3級に近い状態の例
- 通院の予定をカレンダーやスマホにメモして、体調と相談しながら、自分で病院に行くことができる
- 薬の飲み忘れはあるが、自分で気づき、「最近飲めていないな」と修正できる
2級に近い状態の例
- 通院日の管理ができず、予約の確認や変更が自分ではできない
- 誰かに付き添われないと、病院に行けない
- 服薬の管理ができず、
- 飲み忘れが続いても自分では気づけない
- あるいは、不安から何度も飲んでしまう
- 薬の残りがなくなっても気づかず、しばらく服薬が途切れてしまう
- オーバードーズをしてしまう
通院・服薬は、病状の悪化を防ぐ「安全装置」です。
ここを一人で維持できない場合、日常生活能力の評価は、2級寄りになっていきます。
⑤ 清潔保持・住環境
3級に近い状態の例
- 掃除・洗濯の頻度は少なく、部屋が散らかっていることは多い
- それでも、なんとか「生活ができないほどではない」状態は保てている
2級に近い状態の例
- 洗濯ができず、着るものがほとんどない状態が何度も続く
- ゴミが溜まり、床が見えない・害虫が出るなど、健康被害が出るレベルになっている
- シャワーや入浴ができず、何日も、時には何週間も身体を洗えない
- 片付けや清掃について考えただけで具合が悪くなり、手を付けられない
部屋の状態は、「生活をどれだけ自力でコントロールできているか」の分かりやすいサインです。
判定のイメージ
上の項目を振り返ってみて、
- 「3級寄りかな」と感じる項目が多ければ、
ギリギリ自力で生活を維持できているタイプ - 「2級寄りだ」と感じる項目が多ければ、
支援がなければ生活が破綻してしまうタイプ
と考えてみてください。
もちろん、これはあくまで自己診断レベルですが、「一人暮らしが成り立つかどうか」という視点で、自分の生活を見直すことが、障害年金の2級・3級を考えるうえでの第一歩になります。
実際には一人で暮らせていない?2級が認められやすい「一人暮らし」の実態
ここからは、少し踏み込んで、
「一人暮らし」と書類上はなっているものの、実態としては2級に近いケース
についてお話します。
「支援付き一人暮らし」の典型例
私が相談を受けていてよく見かけるのは、次のようなパターンです。
- 住民票もアパートの契約も、すべて本人名義
- 障害年金の申請書にも「一人暮らし」と記載
- しかし、生活の中身をよく聞いていくと……
という方です。
詳しく伺うと、たとえばこんな実態が見えてきます。
- 週2〜3回、親が車で来て、
- 食料・飲み物・日用品などを大量に運び込んでくれている
- その日だけまとめてゴミ出しや片付けをしてくれている
- 家賃や光熱費は、すべて親が管理
- 請求書は親のところに届くようにしている
- 本人は口座残高も詳しく把握していない
- 郵便物は、封を開けることができない
- 封筒がポストにたまってしまう
- 親が来たときにまとめて持ち帰り、必要な手続きは親が行っている
- 通院の予約や変更も、親が電話をかけて段取りをしている
このようなケースでは、
「一人で生活している」というよりは、
「周囲の支援がなければ生活が維持できない」状態
といえます。
書類上の「一人暮らし」と、実際の生活能力は切り離して考える
障害年金の審査では、「実際にはどれくらい援助が必要なのか」が非常に重要です。
そのため、
- 「一人暮らしです」とだけ伝えてしまうと、実態より軽く見られてしまう
一方で、「家族・支援者がどんな形で、どれくらい生活を支えているのか」を具体的に伝えれば、
- 2級相当として評価される可能性が出てくる
ということになります。
「一人暮らしの実態」を医師にどう伝えるか
ここまで読んで、
「たしかに、自分の一人暮らしは“支援付き”かもしれない」
と感じた方もいらっしゃると思います。
では、その実態を、どうやって診断書に反映してもらえばよいのでしょうか。
ポイントは、
診察での伝え方
です。
危険な一言:「一人暮らしできています」
診察室で、何気なくこんな会話をしていないでしょうか。
- 医師「最近の生活はどうですか?」
- ご本人「一人暮らしですけど、なんとかやっています」
この一言だけを切り取ると、医師の頭の中には、次のようなイメージが浮かびやすくなります。
「一人暮らしができている → 基本的な生活能力はある → 3級に近いかな」
もちろん、医師もプロですから、もう少し丁寧に見てくださいます。
ただ、限られた診察時間の中で生活の細部まですべて聞き取るのは難しい、という現実もあります。
だからこそ、患者側が、
「一人暮らしの中で、どんな場面で、どれくらい援助が必要なのか」
を、ある程度整理して伝える必要があるのです。
望ましい伝え方:支援の内容を具体的に話す
では、どう伝えればよいのか。
キーワードは、
「これだけの支援がないと、生活が成り立ちません」
です。
たとえば、次のような話し方が考えられます。
- 食事について
- 「いまアパートで一人暮らしをしていますが、
食事は週に2回、母が作り置きの惣菜を持ってきてくれて、
それを温めて食べているだけです。自分一人では買い物に行けません。」
- 「いまアパートで一人暮らしをしていますが、
- お金について
- 「家賃や光熱費、携帯代などは、全部母が通帳を管理して払ってくれています。
自分ではいくら入金されて、いくら出ていっているのか把握できていません。」
- 「家賃や光熱費、携帯代などは、全部母が通帳を管理して払ってくれています。
- 手続きについて
- 「郵便物の封を開けるのが怖くて、ポストにたまってしまいます。
母が来たときに全部持って帰って、中身を確認して、
役所に連絡するのもやってもらっています。」
- 「郵便物の封を開けるのが怖くて、ポストにたまってしまいます。
このように伝えることで、医師の頭の中に、「支援なしでは一人暮らしが成り立たない」という具体的なイメージが浮かぶようになります。
なぜここまで具体的に話す必要があるのか
診断書には、
- 食事
- 清潔保持
- 金銭管理
- 対人関係
- 通院・服薬
など、「日常生活能力」に関する項目が細かく並んでいます。
医師は、診察時の会話やこれまでの経過から、それぞれの項目を「どの程度できているか」評価します。
ですから、
- 普段の診察では、主に「気分の落ち込み」「不安」「眠れない」といった精神症状の話だけ
- 生活の実態については、ほとんど話していない
という場合、
診断書の「生活能力」に関する欄が、実態よりも軽く書かれてしまうリスク
が高まります。
逆に言えば、診察の際にしっかりと生活の実態を伝えておくことで、
「2級に近い生活実態」であることが、診断書にも反映されやすくなる
ということです。
明日から誰も手伝ってくれなかったら?生活崩壊シミュレーションをしてみる
とはいえ、
「自分では当たり前になってしまっていて、どこからが“援助”なのか分からない」
という方も多いと思います。
そこでおすすめしたいのが、
「生活崩壊シミュレーション」
です。
1. 前提条件を決める
紙でもスマホのメモでも構いません。
まずは、こう書いてみます。
「もし明日から、家族も支援者も一切手伝ってくれなくなったとしたら?」
この前提に立って、
- 1日目
- 2日目
- 3日目…
- 1週間後
と、生活を時間軸でイメージしてみます。
2. 項目ごとに「どこで詰まるか」を書き出す
次に、生活をいくつかの項目に分けて考えます。
- 食事(買い物・調理・片付け)
- お金(家賃・光熱費・日用品)
- 通院・服薬
- 掃除・洗濯・ゴミ出し
- 郵便物・役所からの通知への対応
それぞれについて、
- 「自分一人でできるか?」
- 「できないとしたら、具体的にどこで詰まるか?」
を、思いつく範囲で書き出してみてください。
たとえば、
- 食事
- 1日目:冷蔵庫にあるものをなんとか食べる
- 2日目:買い物に行こうとするが、家を出られない
- 3日目:何も食べられず、水だけで過ごす
- 4日目:フラフラして動けなくなる ……など
- お金
- 家賃の支払日を把握していない
- 請求書の封筒を開けられない
- 振込先が分からない
- 通院・服薬
- 病院の予約日を覚えておらず、気づいたら過ぎている
- 薬をいつ飲むのか覚えられない
- 残りが少なくても受診の段取りを組めない
といった具合です。
3. これはそのまま「生活状況メモ」になる
この「生活崩壊シミュレーション」を書き出しておくと、
そのまま、
- 医師に見せるメモ
- 社労士など専門家に相談するときの資料
として使えるようになります。
診察のとき、
「先生、家族が手伝ってくれないと、生活がこうなってしまうと思うんです」
と、このメモを見せながら説明すると、
医師も具体的なイメージを持ちやすくなり、診断書に反映されやすくなります。
結論:大事なのは「どれだけつらいか」ではなく「一人で生活を維持できるか」
ここまで、かなり具体的にお話してきました。
最後に、内容をぎゅっとまとめておきます。
- 精神障害での障害年金の等級は、
診断名や薬の量だけでなく、「日常生活能力」と「援助の必要性」で決まる - 2級と3級の大きな違いは、
「支援なしで一人暮らしが成り立つかどうか」 - 書類上「一人暮らし」であっても、
実態としては、- 食事
- お金
- 通院・服薬
- 掃除・洗濯
- 郵便物・役所の手続き
などの多くを、家族や支援者に頼っている場合、
2級相当の生活実態である可能性がある
- 診察で「一人暮らししています」「なんとかやっています」とだけ伝えると、実態よりも軽く見られてしまうことがある
- 「これだけの支援がないと暮らしていけません」という形で、具体的な援助の内容を医師に伝えることが重要
- そのための準備として、
「生活崩壊シミュレーション」を書き出しておくと役に立つ
障害年金の等級は、決して「もっとつらくならないと上がらない」わけではありません。
「どれだけつらいか」だけでなく、
「支援がないと、生活がどう崩れてしまうか」を、きちんと伝えられているかどうか。
ここが、2級と3級を分ける大きなポイントになっている、ということを、頭の片隅に置いていただければと思います。
「一人暮らしできていると言っていいのか分からない…」と感じたら
最後に、少しだけ、専門家としてお手伝いできることをお話させてください。
実際のご相談では、
- 「自分の状態が2級に当てはまるのかどうか分からない」
- 「家族にどこまで手伝ってもらっているか、人に話したことがない」
- 「どこまでを“援助”として伝えるべきなのか、判断がつかない」
といったお悩みを、とても多くお聞きします。
ご本人にとっては、長年の生活の中で「当たり前」になってしまったことほど、言葉にしづらいものです。
そこで社会保険労務士としては、
- 生活の実態を、ゆっくり丁寧にヒアリングし、
- ガイドラインの項目(食事・金銭管理・清潔保持・対人関係・通院など)に沿って整理し直し、
- 医師に伝えるための「生活状況メモ」の作成をお手伝いする
といった形で、「生活実態の翻訳役」を担うことができます。
また、
- 診断書の内容と、
- ご本人の申立書(病歴・就労状況等申立書)の内容が、
矛盾してしまわないよう、第三者の目でチェックすることも可能です。
「自分の一人暮らしは、本当に“できている”と言っていいのだろうか?」
そんな不安が頭をよぎったときは、どうか一人で抱え込まず、専門家にご相談いただければと思います。
あなたの今の生活を、ガイドラインの言葉に「翻訳」していく作業を、一緒に進めていきましょう。
≪もっと知りたい!!≫
実際の手続きは、初診日の加入年金で窓口が分かれ、予約・持ち物・段取りが必要になります。
次は、名古屋市の入口ナビで「どこに相談し、どう進めるか」を確認してください。
「まずは話を整理したい」という段階でも大丈夫です。状況に合わせて、何から始めるのが最短か一緒に整理します。
電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。