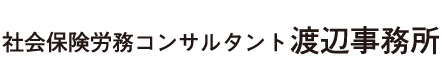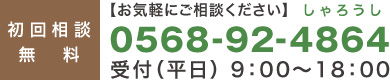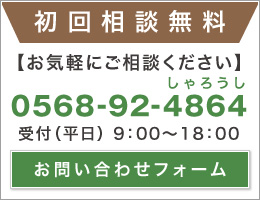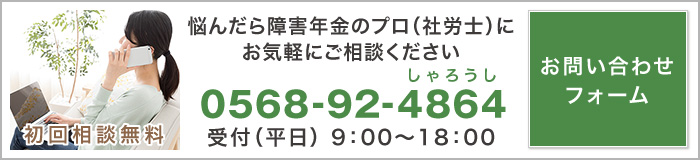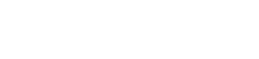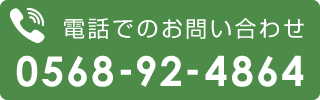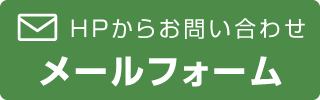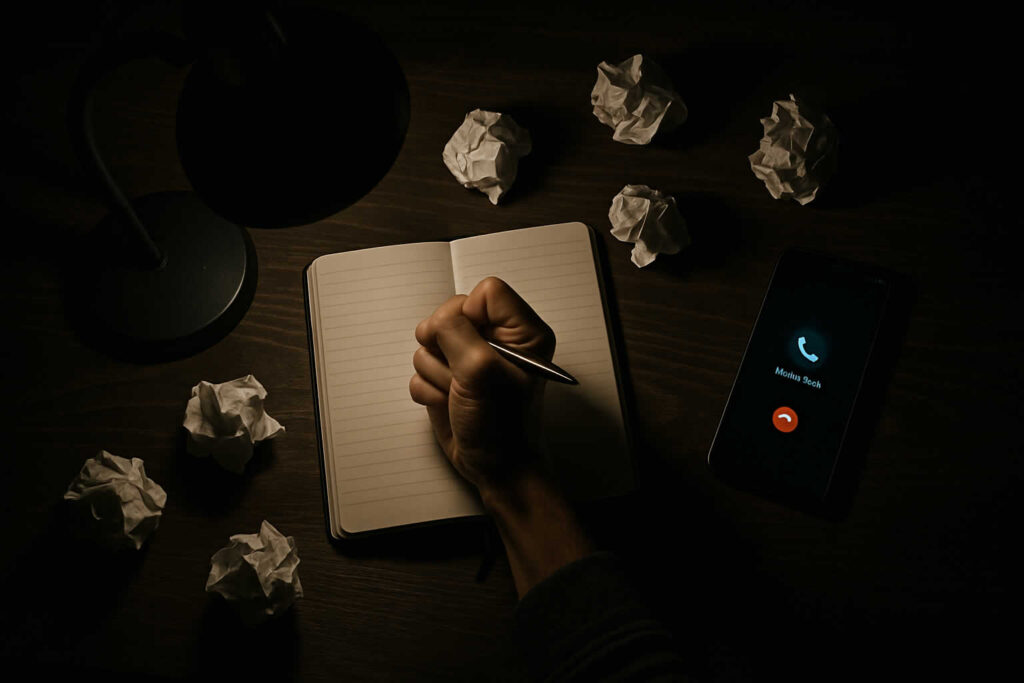
「障害年金の等級は『日常生活』のリアルな姿で決まる」
「だからこそ、その困難を具体的に医師に伝えることが、あなたの未来を左右する」
前回の記事では、診断書の最重要項目である「日常生活能力」のうち、「食事」「清潔保持」「金銭管理」という、生きていく上で根幹となる3つのテーマについて、私の恥ずかしい体験談も交えながら解説しました。
▼前回の記事をまだ読んでいない方はこちらから
【体験談】うつ病の障害年金|診断書「日常生活」のリアルな伝え方① 食事・入浴・金銭管理編
多くの方から「まさに自分のことだと思った」「何を伝えればいいか分かった」という反響をいただき、改めてこのテーマの重要性を痛感しています。
こんにちは。双極性障害(躁うつ病)という精神疾患と向き合いながら、障害年金の専門家として、かつての私と同じように苦しむ方々のサポートをしている社会保険労務士の渡邊智宏です。
さて、今回は「日常生活」解説の後半戦。
前回よりもさらに一歩踏み込み、社会との関わりの中で生じる、より複雑で、より多くの人が悩むであろう4つのテーマを扱います。
- (4)通院と服薬
- (5)他人との意思伝達及び対人関係
- (6)身辺の安全保持及び危機対応
- (7)社会性
「ただ病院に行くだけではダメ?」「人と会えないのは当たり前じゃないの?」
そう感じているあなたの疑問に、当事者だからこそ分かるリアルな視点と、専門家としての客観的な視点の両方から、徹底的にお答えしていきます。
この記事を最後まで読めば、あなたの抱える「見えない困難」を言語化し、医師に正しく伝えるための、強力な武器が手に入るはずです。
〈目次〉
- おさらい:あなたの日常を測る“7つのものさし”
- 【項目④】通院と服薬:「できている」に潜む大きな落とし穴
- 【項目⑤】対人関係:「人と会えない」だけではない、コミュニケーションの質
- 【項目⑥】危機対応:うっかりミスから災害、そして“最悪の事態”まで
- 【項目⑦】社会性:レンタルビデオの延滞から見えた、社会とのズレ
- 結論:最高の診断書は、あなたの「勇気ある告白」から生まれる
おさらい:あなたの日常を測る“7つのものさし”
本題に入る前に、もう一度だけ確認させてください。精神疾患の障害年金の診断書では、あなたの日常生活能力が、以下の7つの項目について、4段階で評価されます。
【日常生活の7つの項目】
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
この評価が、あなたの障害等級を決定づける最重要ファクターです。そして、その評価の質は、あなたがどれだけ具体的に、正直に、ご自身の状況を医師に伝えられるかにかかっています。それでは、後半戦を始めましょう。
【項目④】通院と服薬:「できている」に潜む大きな落とし穴

「定期的に通院できていますか?」
この質問に、あなたはどう答えますか?
おそらく、多くの方が「はい、できています」と答えるのではないでしょうか。特に、うつ病で不眠に悩む私たちにとって、睡眠導入剤は命綱のようなもの。それを手に入れるためには、何が何でも通院しなければなりません。
私自身、引きこもり生活の中で唯一、社会との接点を保っていたのが週に一度の通院でした。だから、この項目については「自分は問題ない」と、ずっと思い込んでいました。しかし、それは大きな間違いだったのです。
障害年金で問われている「通院と服薬」とは、単に「病院に行っているか」「薬を飲んでいるか」という事実だけではありません。その「質」が厳しく問われるのです。
体験談:医師の前で「良い患者」を演じていた私
私は、きちんと予約通りに病院の扉をくぐっていました。しかし、診察室の中での私は、どうだったでしょうか。
医師の前に座っても、自分から積極的に話すことはほとんどありませんでした。「最近どうですか?」と聞かれても、「まあ、変わりないです…」と生返事をするだけ。本当は、夜中に得体の知れない不安に襲われて泣きそうになっていることも、一日中ベッドから出られずに自己嫌悪に陥っていることも、恥ずかしくて、情けなくて、とても言えませんでした。
医師のアドバイスも、右から左へ聞き流すだけ。「早くこの時間が終わらないかな…」と、ただうつむいて座っている。そんな患者だったと思います。
これでは、「通院」という行為の目的である「医師とのコミュニケーションを通じた治療」が、全く成り立っていません。ただ病院という場所に物理的に移動しているだけで、それは「適切な通院」とは到底言えないのです。
あなたの通院はどうでしょうか?
医師との間で、治療に必要な情報のキャッチボールができていますか?
また、通院という行為そのものに困難を抱えている方も多いでしょう。
- パニック発作や不安感で、電車などの公共交通機関に乗れない。
- 薬の影響で集中力が散漫になり、車の運転が危険。
- そもそも外出するエネルギーがなく、家族に送迎してもらわなければ病院に行けない。
- 診察室に一人で入るのが怖く、家族に同席してもらっている。
さらに深刻なのは、予約を守れないという問題です。
「明日は病院の日だ」と分かっていても、当日の朝、鉛のように重い体と心が、どうしても言うことを聞かない。ギリギリになってしまったり、間に合わなかったり、ひどい時には無断でキャンセルしてしまったり…。
もし、あなたが予約の変更や遅刻を繰り返しているのであれば、それは「適切な通院が困難である」ことの、何よりの証拠です。その事実は、カルテには記録されていても、医師が診断書に書く際に意識してくれるとは限りません。「予約を守れないことが多く、ご迷惑をおかけしています」と、あなた自身から伝える必要があるのです。
薬との闘い:オーバードーズと自己判断による断薬
次に、この項目のもう一つの柱である「服薬」についてです。
「薬の管理、できていますか?」と聞かれれば、多くの人は「飲み忘れはないか」「時間を守れているか」を問われていると考えます。もちろん、それも重要です。引きこもり生活で時間感覚が曖昧になり、飲み忘れてしまうことは、私たちにとって「あるある」です。
しかし、精神疾患の服薬管理で本当に問題となるのは、それだけではありません。
「処方通りに飲めていない」という、より深刻な2つのパターンが存在します。
- 処方以上に飲んでしまう(過量服薬)
最も分かりやすいのが、オーバードーズ(OD)です。死にたい気持ちから、あるいは現実から逃避したい一心で、大量の薬を一度に飲んでしまう。いけないと分かっていても、衝動を抑えられない。これは、命に関わる非常に危険な状態です。
そこまでいかなくても、「効きが悪いから」という理由で、処方より多く飲んでしまうことはありませんか?
「睡眠薬を1錠飲んだけど、全然眠れない。もう1錠追加しちゃおう…」
「抗うつ薬の効果が感じられない。少し多めに飲めば、効いてくれるかもしれない…」
このような自己判断による増量は、実は非常にありふれた問題です。
- 自己判断で飲むのをやめてしまう(断薬)
そして、その逆のパターン。これもまた、深刻な問題です。
「この薬、副作用が辛すぎるから飲みたくない」
「昼間まで眠気が残って、頭が働かない」
「そもそも、こんな脳に作用する薬を飲み続けるのが怖い」
様々な理由から、医師に相談することなく、自分の判断で薬を飲むのをやめてしまう。実は、私自身がこのケースにどっぷりと当てはまっていました。
私の双極性障害には、抗うつ薬がうまく効きませんでした。効果を感じないどころか、指が震えるといった副作用ばかりが気になる。薬への不信感から、私は勝手に服薬を中断してしまったのです。しかも、そのことを医師に報告しませんでした。
すると、どうなるか。
医師は、私が処方通りに薬を飲んでいると思っています。それでも効果が出ないから、「薬が足りないのかもしれない」と、さらに薬を増やす。増えた薬を見て、私はますます怖くなり、飲むのをやめる…。
まさに、治療の悪循環です。半年や1年、勝手に断薬し、いよいよまずいと思って再開する。そして、またしばらくしてやめてしまう。そんなことを、私は何年も繰り返していました。
このように、「通院と服薬」という短い言葉の中には、非常に多くの、そして深刻な問題が隠されているのです。
「通院と服薬」6つのチェックリスト
あなたの状況を整理するために、以下のリストで自己チェックしてみてください。
□ 1. 通院の自立性:
一人で、公共交通機関や自家用車を使って、問題なく病院まで行けますか?(家族の送迎や付き添いが必要ではありませんか?)
□ 2. 医師との対話:
診察の場で、ご自身の症状や生活の困りごとを、具体的に医師に伝えることができていますか?
□ 3. 予約の遵守:
予約した日時に、遅刻やキャンセルをすることなく、通院できていますか?
□ 4. 服薬の管理:
薬の飲み忘れや、飲む時間を間違えることはありませんか?
□ 5. 過量服薬:
処方された量以上に、薬を多く飲んでしまうことはありませんか?(オーバードーズの経験はありませんか?)
□ 6. 自己中断:
医師に相談せず、ご自身の判断で薬を飲むのをやめてしまったことはありませんか?
【項目⑤】対人関係:「人と会えない」だけではない、コミュニケーションの質
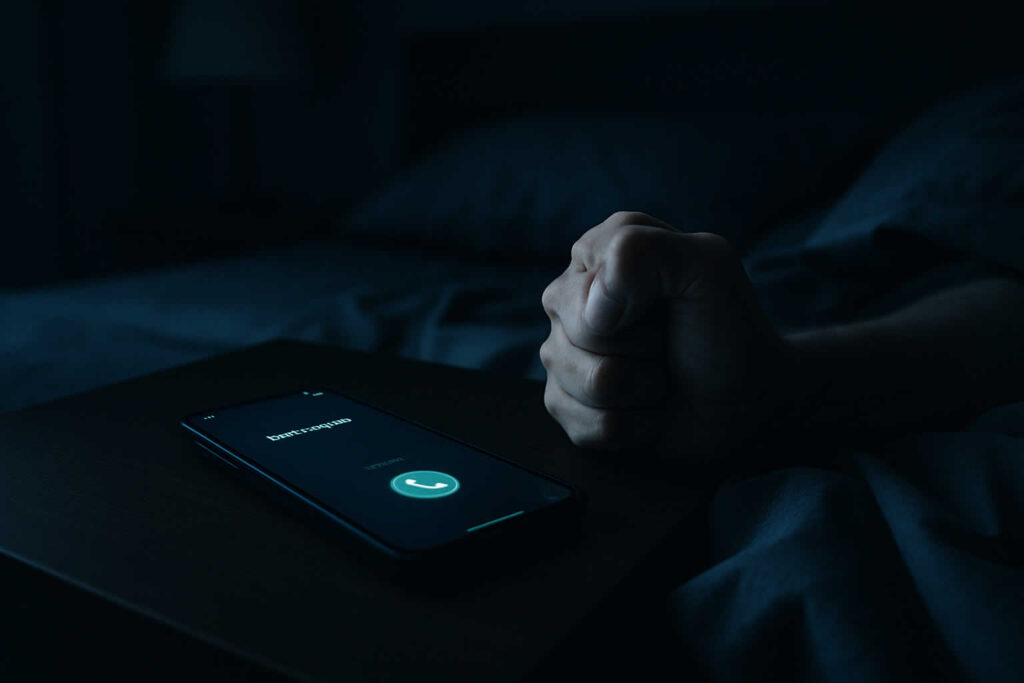
「他人との意思伝達及び対人関係」。一言で言えば、コミュニケーション能力です。
これは、引きこもりがちな私たち精神疾患の当事者にとって、最も厳しい項目の一つと言えるでしょう。
「人と会うのが億劫」「誰とも話したくない」
これは、うつ状態の基本症状です。人と会う回数が極端に減っている。それだけでも、この項目で困難を抱えていることは明らかです。
しかし、この項目で問われているのは、コミュニケーションの「量」だけではありません。その「質」もまた、重要な評価ポイントとなります。
体験談:あらゆる関係から逃げ続けた引きこもり時代
例によって、私のケースをお話しします。
先ほどから何度も話している通り、私は完全な引きこもりでした。誰かと会話するという行為そのものが、ほとんど存在しない日々。定期的に話す相手は、週に一度会う医師と看護師だけ。何日も声を発しないことも珍しくありませんでした。
- 友人との関係:
もともと、親しい友人と話すこと自体に大きな問題はありませんでした。しかし、病状が悪化してからは、自分から連絡を取る気力は全く湧かない。友人から電話がかかってきても、話すのが億劫で、出ずに無視してしまう。そんなことを繰り返すうちに、次第に連絡は来なくなりました。 - 元職場との関係:
退職後も、引継ぎなどの用件で、元職場から頻繁に連絡がありました。その電話が、私には耐えきれないほどのストレスでした。最終的には、主治医に相談し、「本人への直接の連絡は控えるように」という内容の診断書を書いてもらい、関係をシャットアウトしました。 - 家族との関係:
意外に思われるかもしれませんが、私は家族との会話が最も苦手でした。近しい関係だからこそ、自分の惨めな現状を打ち明けられない。心配をかけたくないという思いと、理解してもらえないかもしれないという恐怖。一人暮らしを諦めて実家に戻ってからも、家族とのコミュニケーションはほとんどありませんでした。 - 社会との関係:
一人暮らしの時は、電話は基本的に無視。宅配便や来客があっても、居留守を使うのが当たり前。社会とのあらゆる窓を、自ら固く閉ざしていたのです。
こうして振り返ると、我ながら徹底的に人との関わりを避けていたな、と改めて感じます。
あなたの場合はどうでしょうか?
コミュニケーションの問題は、単に「人と会わない」だけではありません。
- 意思伝達の質の問題:
人と話していても、自分の言いたいことがうまく言葉にできない。相手の言っていることの意味が、すんなり頭に入ってこない。あるいは、人の言うことを何でも鵜呑みにしてしまい、簡単に騙されてしまう。 - 集団行動の問題:
1対1なら何とか話せるけれど、3人以上の集団の中に入ると、途端に居場所がなくなり、一言も発せなくなる。忘年会やパーティーのような、大勢の人が集まる場所は、耐えられないほどの苦痛を感じる。 - 約束の問題:
友人と会う約束をしても、当日になると気分が落ち込み、どうしても家から出られなくなる。申し訳ないと思いながらも、ドタキャンを繰り返してしまう。
このように、コミュニケーションの困難は、様々な形で私たちの生活に現れるのです。
「対人関係」7つのチェックリスト
ご自身のコミュニケーションについて、以下の視点から見つめ直してみてください。
□ 1. 交流の頻度:
家族以外の人と、会って話したり、電話したりする機会はありますか?(週に1回未満、月に1回未満など)
□ 2. 連絡への応答:
電話がかかってきた時に、出ることができますか?LINEやメールに目を通し、返信することができていますか?
□ 3. 意思の伝達:
会話の中で、ご自身の考えや気持ちを、相手に分かりやすく伝えることができていますか?
□ 4. 話の理解:
相手の言っていることを、集中して聞き、正しく理解することができていますか?
□ 5. 集団への適応:
複数人がいる場に参加し、その中で過ごすことができますか?
□ 6. 約束の遵守:
他人との約束(時間や内容)を守ることができていますか?(ドタキャンを繰り返していませんか?)
□ 7. 適切な距離感:
相手に対して、過度に馴れ馴れしくなったり、逆に極端によそよそしくなったりせず、適切な距離を保つことができていますか?
【項目⑥】危機対応:うっかりミスから災害、そして“最悪の事態”まで

「身辺の安全保持及び危機対応」。
この項目は、パッと見ただけでは、何を聞かれているのか分かりにくいかもしれません。私も、この項目を説明する時には、いつも少し戸惑います。
これは、大きく2つのことを問われています。
- 安全保持: 普段の生活の中で、うっかりミスなどから、ご自身の安全を危険に晒していませんか?
- 危機対応: 何か予期せぬトラブルが起きた時に、適切に対応し、乗り越えることができますか?
体験談:前方不注意で起こした追突事故
まず「安全保持」について、最も分かりやすい例は自動車の運転です。
うつ病の症状や薬の副作用で、集中力や判断力は著しく低下します。私も、病状が悪化してすぐの頃、自動車事故を起こしてしまいました。渋滞の中で、ボーッとしていて前の車が止まっているのに気づくのが遅れ、追突してしまったのです。幸い、軽い事故で済みましたが、一歩間違えれば大惨事になっていたかもしれません。
運転をしない方でも、
- 道を歩いていて、車や自転車にぶつかりそうになる。
- 料理中、ガスの火を消し忘れる。
- 家の鍵をかけ忘れて外出してしまう。
- 電車でうっかり乗り過ごし、知らない駅まで行ってしまう。
このような「うっかり」や「ヒヤリハット」の経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。これらは、集中力や注意力が低下していることの、明確なサインです。
そして、この「安全保持」の究極的な問題として、自殺企図があります。
常に死ぬことを考えている「希死念慮」から、実際に手首を切ったり、薬を大量に飲んだりする「自殺未遂」まで。ご自身の命を危険に晒す行為は、この項目で最も重く評価されるべき点です。
「助けて」が言えますか?危機に瀕した時の対応能力
次に、「危機対応」についてです。
これは、トラブルが「起きてしまった後」の対応能力を問うています。
先ほどの私の事故の例で考えてみましょう。
事故を起こしてしまった後、私たちは多くの対応を迫られます。負傷者の確認と救護、警察への連絡、相手との連絡先交換、保険会社への報告…。パニック状態の中で、これらを冷静に、的確にこなせるでしょうか。
私たちが病気によって判断力を失っているとき、その場で思考停止してしまい、同乗者や周囲の人に全てを任せてしまう、ということは十分に考えられます。
この「対応力」の中でも特に重要なのが、「困った時に、誰かに助けを求められるか」という点です。
事故の時に保険会社に電話するのも、道に迷った時に交番で尋ねるのも、一種の「助けを求める」行為です。しかし、対人関係に困難を抱えていると、この簡単なはずの行為が、途端に難しくなります。
最も身近で深刻なのは、お金の問題でしょう。
働けなくなり、収入が途絶える。いずれ生活が立ち行かなくなることは分かっているのに、誰にも相談できず、問題を先延ばしにしてしまう。そして、家賃や公共料金の督促状が届いてから、ようやく事の重大さに気づく…。
困った時に「助けて」と言えるかどうか。これは、私たちが社会で生きていく上で、極めて重要な能力なのです。
この危機対応能力が、最も極端な形で試されるのが、災害時です。
地震や台風が起きた時、あなたは一人で自分の命を守る行動がとれるでしょうか。
- 情報収集: ニュースや防災無線に注意を払い、危険が迫っていることを察知できるか。
- 判断: 家に留まるべきか、避難所に行くべきか、適切に判断できるか。
- 行動: 避難すべき時に、ためらわずに行動に移せるか。
- 避難所生活への適応: 大勢の人がいる避難所で、精神的な負担に耐えながら生活できるか。
ある方は、災害が起きたら、それに流されて死んでしまえばいい、と考えたそうです。自殺は能動的な行為だからハードルが高い。でも、災害死なら、何もしなければいい。そう思うほど、生きる気力を失っていたのです。
「危機対応」とは、まさに「生き抜く力」そのものを問うている、と言えるのかもしれません。
「危機対応」6つのチェックリスト
少し重い話になりましたが、ご自身の状況を客観的に評価するために、以下のリストを参考にしてください。
□ 1. 不注意による危険:
集中力の低下などから、事故や怪我につながりそうな「ヒヤリハット」体験はありませんか?(運転、歩行、火の元など)
□ 2. 自殺念慮・自傷行為:
死にたいと考えたり、実際に自分自身の体を傷つけたりしたことはありませんか?
□ 3. トラブル発生時の対応:
予期せぬトラブル(事故、急な体調不良など)が起きた時、一人で冷静に対応できますか?
□ 4. 援助希求:
困った時、家族や友人、公的機関などに「助けてほしい」と相談することができますか?
□ 5. 災害への備えと対応:
自然災害などが発生した際、情報を収集し、避難などの適切な行動を一人でとれると思いますか?
□ 6. 危険の予測:
危ない場所や状況を避けたり、危険を予測して事前に対策をしたりすることができていますか?
【項目⑦】社会性:レンタルビデオの延滞から見えた、社会とのズレ
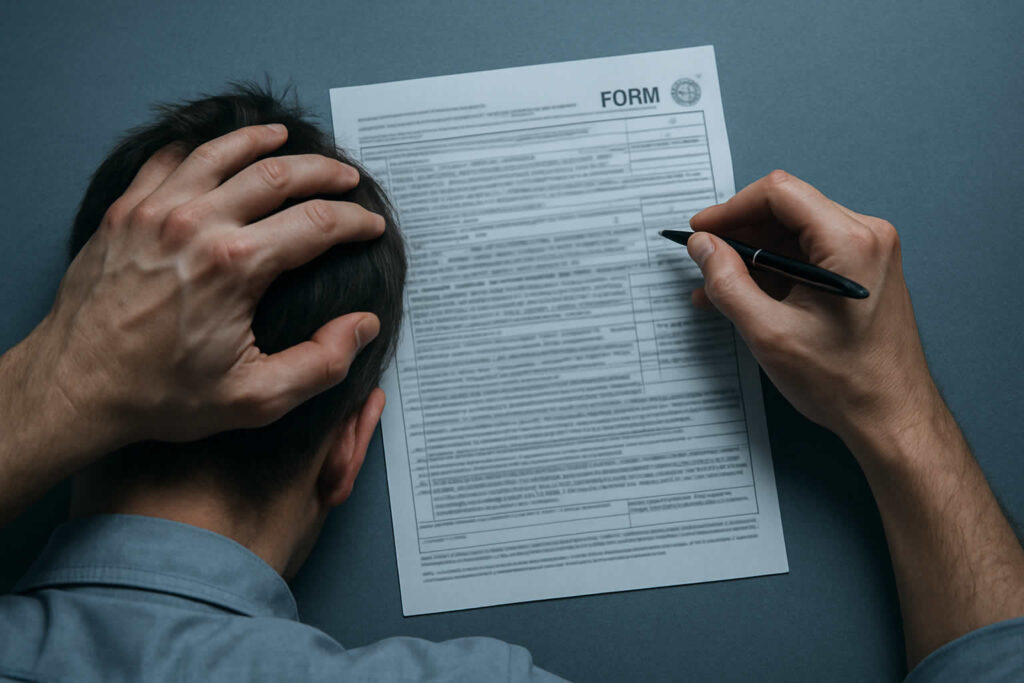
いよいよ最後の項目、「社会性」です。
この言葉も、非常に範囲が広く、何を指しているのか分かりにくいですよね。「社会性がない」と聞くと、何か突飛な行動をする人を想像してしまい、「自分はそこまでではない」と思ってしまうかもしれません。
しかし、診断書で問われている「社会性」は、もっと身近な問題を指しています。診断書の注釈には、「銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か。また、社会生活に必要な手続きが行えるか」とあります。
つまり、社会のルールや仕組みを理解し、それに沿って必要な手続きや行動を、一人で遂行できるか、ということです。
ここでも問題になるのは、「やるべきこと」が分かっていても、気力や体力がなく、行動に移せないという点です。
例えば、毎年更新が必要な自立支援医療の申請。期限が迫っていると分かっていても、どうしても役所に行くことができず、期限が過ぎてしまった…。私も、そんな経験があります。
また、うつ病や発達障害の特性として、文字や文章を読むのが困難になることがあります。書類を読んでも、内容が全く頭に入ってこない。どこに何を書けばいいのか理解できない。こうなると、手続きそのものが物理的に不可能になってしまいます。私も、調子が悪い時は、本を読んでも同じ行を何度も読み返すだけで、全く内容が理解できない、ということがよくありました。
体験談:1万円の延滞料金が教えてくれたこと
この「社会性」という曖昧な言葉を、私が身をもって理解した、忘れられない出来事があります。それは、レンタルビデオ屋での一件です。
調子が良い時に、見たい映画を数本借りました。問題は、1週間後の返却日です。その日、私は絶不調のどん底にいました。ベッドから動けず、ビデオを返しに行くなど、到底不可能です。
「明日、行こう」
そう思って、一日、また一日と先延ばしにする。気づけば、1ヶ月が経っていました。
いよいよまずいと思い、重い体を引きずって店に行くと、店員から告げられた延滞料金は、1万円を超えていました。
たかがレンタルビデオの延滞です。しかし、この些細な失敗の中には、
- 社会のルール(返却期限)を守れない。
- やるべきこと(返却)を行動に移せない。
- 問題を先延ばしにして、事態を悪化させる。
といった、私の「社会性」における様々な問題が凝縮されていたのです。
あなたの「日常の困りごと」は全て「社会性」の問題かもしれない
私がこの経験から学んだのは、「社会性」とは、これまでの6項目に当てはまらなかった、あらゆる日常の困りごとや失敗談の受け皿になる、ということです。
例えば、郵便受けの管理。
引きこもっていると、郵便物を取りに行くことすら億劫になります。取りに行っても、仕分けができずに放置してしまう。その中に、公共料金の督促状や、重要な手続きの案内が含まれているかもしれません。たかが郵便物の処理ですが、これができないことで、社会的な不利益を被る可能性があるのです。
あなたが日常生活の中で、「これ、できなくて困ってるんだよな」「こんな失敗しちゃったな」と感じていることはありませんか?
一見、些細で、障害年金の評価とは関係ないように思えることでも、それが積み重なれば、「社会生活を円滑に送ることが困難である」ことの、有力な証拠となるのです。
そして、文字通り、社会との繋がりそのものも、この項目で評価されます。
この病気は、友人や職場との関係を、根こそぎ奪っていくことがあります。あなたは今、社会との繋がりを持っていますか?一週間のうちに、誰かと会話をする機会はありますか?誰とも話さず、社会から隔絶した生活を送っているとすれば、それは「社会性」に大きな問題を抱えている、と言えるでしょう。
「社会性」5つのチェックリスト
最後の仕上げとして、ご自身の生活を以下の視点から総点検してみてください。
□ 1. 公的手続き:
役所での手続き(自立支援医療の更新、住民票の取得など)や、銀行での金銭の出し入れを、一人で行うことができますか?
□ 2. 書類の理解と作成:
公的な書類や手紙を読み、内容を理解し、必要な箇所に記入することができますか?
□ 3. 日常生活のルール遵守:
ゴミ出しのルールを守る、約束の時間を守るなど、社会生活を送る上での基本的なルールを守れていますか?
□ 4. 社会との繋がり:
家族以外に、定期的に交流のある友人や知人はいますか?社会的に孤立していませんか?
□ 5. その他の困りごと:
上記の項目以外で、日常生活や社会生活の中で、病気が原因で「できなくて困っていること」や「失敗してしまったこと」はありませんか?(些細なことでも構いません)
結論:最高の診断書は、あなたの「勇気ある告白」から生まれる
ここまで、7つの項目について、非常に長く、そして詳細に解説してきました。
考えれば考えるほど、多くのことを聞かれている、と感じたのではないでしょうか。ぱっと聞かれて、その場で即座に答えられるような内容ではない、ということも、お分かりいただけたと思います。
もし、あなたが何も準備せずに病院へ行き、医師から「日常生活はどうですか?」と聞かれたとして、これら全ての事柄を、悔いなく伝えきることができるでしょうか。おそらく、難しいでしょう。
だからこそ、私は強くお勧めします。
時間をかけて、ご自身の生活を振り返り、紙に書き出してみてください。
箇条書きのメモで構いません。「こんなこと、関係ないかな?」と思うような些細なことでも、ためらわずに書き出してみましょう。書いているうちに、忘れていた記憶や、気づかなかった困難が、次々と思い浮かんでくるはずです。
そうして作り上げた「あなたの日常の記録」は、最高の診断書を作成してもらうための、何より強力な資料となります。
医師は、科学者です。根拠のないことは書けません。しかし、逆に言えば、患者からの具体的な証言という「根拠」があれば、それに基づいて診断書を書いてくれる可能性は、飛躍的に高まります。
あなたの状況を、あなた以上に知っている人はいません。
恥ずかしい過去や、情けない自分と向き合うのは、辛い作業かもしれません。しかし、その勇気ある「告白」こそが、医師の心を動かし、あなたの未来を支える、正当な評価へと繋がっていくのです。
≪もっと知りたい!!≫
実際の手続きは、初診日の加入年金で窓口が分かれ、予約・持ち物・段取りが必要になります。
次は、名古屋市の入口ナビで「どこに相談し、どう進めるか」を確認してください。
「まずは話を整理したい」という段階でも大丈夫です。状況に合わせて、何から始めるのが最短か一緒に整理します。
電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。