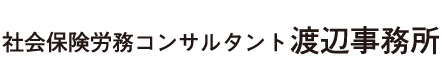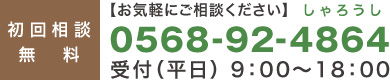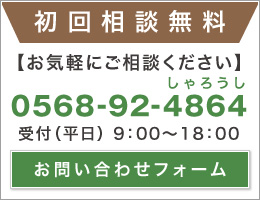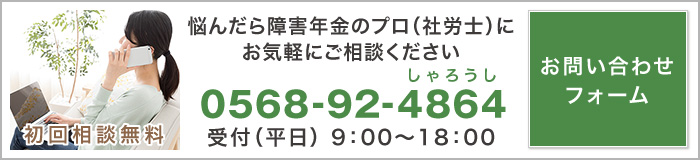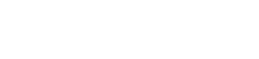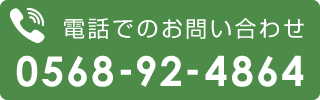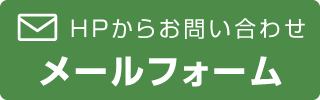「子どもの頃に発達障害の傾向を指摘されたことがある」
「大人になってからADHDと診断され、その後にうつ病(適応障害・双極性など)になった」
「昔の受診歴があるせいで、初診日がめちゃくちゃ古くなるかもしれないと言われた」
もしあなたが今、こうした状況で障害年金(特に精神)を検討しているなら、この記事は役に立ちます。
障害年金は、“初診日(いちばん最初に医師にかかった日)”が土台です。
ところが精神の分野では、病歴のつながり方によって初診日が過去へ遡ってしまうことがあります。
そして初診日が遡ると、
- もらえる年金の種類が変わる
- 納付要件で不利になる
- 古い病院の証明が取れず詰む
など、現実的にキツい問題が起きやすいです。
そこで出てくるのが、「社会的治ゆ(しゃかいてきちゆ)」という考え方。
ざっくり言うと、「いったん社会生活が安定していた期間があるなら、法律上は“治った扱い(リセット)”にできる可能性がある」というロジックです。
この記事では、
- なぜ初診日が遡るのか
- 初診日が遡ると何が困るのか
- その回避の方向性として「社会的治ゆ」がどう使われるのか
- 認められる目安と、集めたい材料
を、順番が唐突にならないように整理して解説します。
※注意:この記事は一般的な考え方の解説です。実際の可否は個別事情(病歴・就労・治療状況・資料の残り方)で変わります。
この記事で分かること
- 「社会的治ゆ」とは何か(何を“リセット”できるのか)
- 初診日が遡る仕組み(相当因果関係)
- 初診日が遡ると困ること(3つ)
- “遡り”を回避する方向性と、その中で社会的治ゆが出てくる位置づけ
- 社会的治ゆが認められる目安(期間・治療・就労など)
- 主張を通すための材料(証拠)と、申立書での書き方の方向性
- 愛知で実際に手続きを進める時の導線(主柱ページへの案内)
≪もっと知りたい!!≫
第1章 まず前提|「社会的治ゆ」は何を解決するための考え方?
社会的治ゆは、いきなり使う“裏技”というより、困っている状況(=初診日が遡って不利になる)を回避するための1つのロジックです。
ポイントはここです。
- 障害年金の審査では、病気が「別」か「一体」かが問題になる
- 一体扱いになると、後の病気の初診日が、前の病気の初診日へ遡ることがある
- その“遡り”が不利になりやすい
- そこで「いったん区切れる(リセットできる)」という発想が必要になる
- その代表が「社会的治ゆ」
つまり社会的治ゆは、
「遡りが起きそう」→「不利」→「なんとか区切れない?」
この流れの中で出てくる、回避策の位置づけです。
第2章 なぜ起きる?|相当因果関係で「初診日が遡る」仕組み
障害年金の世界には、相当因果関係という考え方があります。
簡単に言えば、
「前の病気がなければ、後の病気は起こりにくかった」
と医学的・社会通念上判断される場合、2つの病気を一連のもの(ひとつの流れ)として扱う、というルールです。
たとえば身体だと、糖尿病→合併症、のような分かりやすい因果関係があります。
精神の分野でやや厄介なのは、発達特性(ASD/ADHDなど)→社会適応の困難→二次障害(うつ・適応障害・不安など)という流れが、審査ロジックとして“つながりやすい”ことです。
この「つながる」判定がされると、何が起きるか。
- いまのうつ病で初めてメンタルクリニックに行った日が“初診日”ではなく
- 子どもの頃の発達相談(療育・児童精神科)などの受診日が“初診日”として扱われる
こうして、初診日が過去へ遡ることがあります。
第3章 初診日が遡ると何が困る?(ここがまず腹落ちポイント)
ここは大事なので、結論から言います。
初診日が遡る=不利になる可能性が一気に上がる
(もちろん逆に有利になる場合もありますが、実務では“困る”ことが多いです)
困る代表例は3つです。
困ること①:もらえる年金の種類・金額が変わる可能性
初診日の時点で加入していた年金で、原則として窓口や年金の種類が変わります。
- 初診日が 厚生年金(第2号)/第3号 にある → 障害厚生年金の可能性
- 初診日が 国民年金(第1号)/未加入が絡む → 障害基礎年金中心の扱い など
初診日が過去へズレると、「本来は厚生年金のはずだったのに…」というズレが起き得ます。
(※20歳前傷病扱いになる等、別の論点が出ることもあります)
困ること②:納付要件で詰む(昔の未納が響く)
障害年金は「保険」なので、原則として保険料の納付要件が見られます。
初診日が昔に遡ると、
「その当時、未納が多かった」
「免除が入っていない」
などで、納付要件の論点が不利になりやすいです。
困ること③:証明できず詰む(カルテ廃棄・閉院)
初診日を証明するのは、基本的に資料勝負です。
でも、初診日が10年前・15年前・子ども時代…となると、
- 病院が閉院
- カルテが保存期間経過で破棄
- そもそもどこに通ったか記憶が薄い
が起きやすい。
結果として、「初診日を証明できず、請求が進まない」という最悪の詰まり方をします。
ここまでのまとめ
初診日が遡ると困るのは、要するに、
- 年金の種類が変わる
- 納付要件が厳しくなる
- 証明が取れず止まる
この3つが同時に起き得るからです。
ここまで読んで「じゃあどうすれば…」となると思います。
次章で、“遡り”への向き合い方(回避の方向性)をいったん整理します。
第4章 じゃあ、どう回避する?|“初診日の遡り”への考え方は2つある
初診日が遡りそうなとき、現実の打ち手は大きく2つです。
方向性①:初診日を徹底的に固める(証明の戦い)
つまり、
「結局いちばん最初はどこ?」
を徹底的に確定し、証明する方向です。
この方向性が必要になるのは、
- 初診日が曖昧
- 受診歴が飛んでいる
- “もっと前に受診あり”が出そう
などのケース。
この領域は、別記事でしっかり手順化しています。
≪もっと知りたい!!≫
方向性②:過去と今を「分ける」ロジックを作る(主張の戦い)
「過去の受診は確かにある」
でも
「その後、長い期間、普通に学校・仕事・生活ができていた」
なら、法律上は“いったん治った扱い”として区切れないか?
この発想が、社会的治ゆです。
つまり社会的治ゆは、
「遡ると困る」→「区切れないと詰む」→「区切る理屈(=社会的治ゆ)」
という流れで登場します。
では、ここからようやく「社会的治ゆそのもの」に入ります。
第5章 社会的治ゆとは?|“一度治った扱い”で初診日を切り替える考え方
社会的治ゆを一言でいうと、
「一定期間、治療を必要とせず(または軽微で)、社会生活を安定して送れていたなら、法律上は“一度治った”とみなして、初診日を切り替えられる可能性がある」
という考え方です。
ここで重要なのは、医学的な完治ではありません。
あくまで年金の実務として、社会生活の安定(就労・就学・生活)が強く見られます。
そして、社会的治ゆが認められると、何が変わるか。
- 過去の病気と、今の病気を「一連」として扱わず
- 途中でいったん区切って
- 今の悪化・再発の受診日を「新しい初診日」として主張する余地が出る
つまり、相当因果関係で“つながりやすい”ケースでも、
「途中でいったん社会的に回復していた(だから区切れる)」
という理屈で、初診日の遡りを止めることを狙います。
第6章 社会的治ゆが認められる目安(期間・治療・就労)
社会的治ゆは、誰でも簡単に認められるわけではありません。
審査側に「本当に区切れる状態だった」と納得してもらう必要があります。
よく見られる目安を、ざっくり整理します。
目安①:一定の期間が空いている
明確な法律の年数があるわけではありませんが、実務上は年単位で見られます。
よく言われる目安として「5年」などが出ますが、ここはケースで動きます。
大事なのは、単に年数だけでなく、中身(生活の安定の質)です。
目安②:治療・服薬が中断している(または軽微)
原則として、
- 通院が途切れている
- 服薬がない
が強い材料になります。
ただし、実務では
- “経過観察レベル”
- ごく少量で安定
などのグレーゾーンもあり得ます。
ここは「どの程度の治療だったか」を丁寧に整理します。
目安③:就学・就労が安定している(最重要になりやすい)
ここがいちばん強いです。
- 一般雇用で、長期に勤務
- フルタイムに近い形で継続
- 大きな配慮なしで回っていた
などは、社会的治ゆの主張を支える柱になりやすい。
逆に、
- 断続的な短期離職
- 強い配慮が常態化
- 生活が常に不安定
だと、主張が弱くなることがあります。
目安④:日常生活が安定している
仕事だけでなく、生活がある程度回っていたかも見られます。
- 生活リズム
- 対人関係
- 金銭管理
- 家事や通院の自己管理
など、「社会生活の安定」を支える情報が材料になります。
注意:条件を満たせば自動で通る、ではない
社会的治ゆは“主張の技術”です。
「治ってたよね?」ではなく、
「この期間は社会生活が安定していた」を、資料と整合性で積み上げます。
第7章 ケースで理解|よくあるパターン別の判断ポイント
ここからは典型例でイメージを作ります。
ケースA:子ども時代に発達特性で受診 → 成人後にうつ
このケースは、相当因果関係でつながりやすいです。
ただし、子ども時代の受診後に、
- 長期間、精神科受診なし
- 学校生活が安定
- 社会人として就労が安定(数年単位)
があるなら、社会的治ゆの主張を検討する余地が出ます。
ケースB:昔少し通院 → 何年も受診なし → 再発
このタイプは、社会的治ゆのストーリーが作りやすいことがあります。
鍵は「何年も受診していなかった期間の生活がどうだったか」です。
ケースC:受診は続いているが、就労は長く安定していた
ここが難所です。
受診が続いていると「治ゆと言えるの?」となりやすい。
ただし“内容”が軽微で、就労が安定しているなど、主張の組み立て次第のケースもあります。
このあたりは、申立書と資料の整合性が勝負になります。
≪もっと知りたい!!≫
〔病歴・就労状況等申立書(設計図)〕作成中
第8章 証拠の集め方|“主張”を通す材料を揃える
社会的治ゆは、「言ったもん勝ち」ではありません。
審査側が納得できる材料があるほど強いです。
強い材料になりやすいもの(例)
- 就労の継続を示すもの
- 在籍証明、雇用契約、給与明細、勤務証明、出勤記録 など
- 就学の継続を示すもの
- 卒業証明、成績証明、在学証明 など
- 受診中断(または軽微)を示す経緯整理
- いつからいつまで通院が途切れていたか
- 投薬がどの程度だったか
- 生活の安定を示す事情
- 周囲の支援の有無、生活が回っていた状況(客観的に)
申立書での書き方の方向性(超重要)
社会的治ゆの主張は、申立書の中で「流れ」として見せます。
- (過去)子ども時代の受診の内容・回数
- (区切り)その後、治療が不要になった/受診が途切れた
- (安定期)学校/就労/生活が安定していた事実(期間と形)
- (再発)何がきっかけで、どのように崩れ、再受診に至ったか
この“区切りと安定”が、社会的治ゆの芯です。
≪もっと知りたい!!≫
第9章 実務の注意点|やりがちな失敗を先回りで潰す
ここ、地味ですが超大事です。
失敗①:「初診日、これでOK」と早合点して後から崩れる
精神の初診日は、資料の読み込みが甘いと後で崩れます。
たとえば 受診状況等証明書 の「初診日欄」だけ見て安心してしまうケース。
経過欄に
- 「以前に他院受診あり」
- 「紹介で受診」
- 「以前より同様症状があり受診」
などがあると、「もっと前があるよね?」となり得ます。
この点は別記事でチェックリスト化しています。
≪もっと知りたい!!≫
失敗②:医療機関への聞き方が甘い
単に「初診日を教えてください」だと、
その病院の初診日だけ返ってきて、他院があるのに気づけないことがあります。
確認するなら、
- 他院からの紹介がないか
- 以前の受診歴が記載されていないか
まで聞くのが安全。
口頭説明が難しい時は、費用はかかりますが、やはり受診状況等証明書を取るのが確実です。
失敗③:「社会的治ゆでいけるはず」と思い込み、材料が足りない
社会的治ゆは、材料が弱いと通りません。
「安定していた期間の就労の裏付け」が薄い、
「治療が継続していたのに説明がない」
などで崩れます。
“主張”より先に、まず材料の棚卸しが大事です。
≪もっと知りたい!!≫
第10章 次にやること|あなたの状況別・読む順番(愛知の導線)
ここから先は、「あなたが今どこで詰まっているか」で読む順番が変わります。
当てはまるところだけでOKです。
① 初診日が曖昧/転院が多い/昔の受診がありそう
まずは初診日を固める手順を先に。
≪もっと知りたい!!≫
② 申立書・診断書まで含めて“全体設計”を知りたい
社会的治ゆの主張は、申立書の設計が重要です。
≪もっと知りたい!!≫
③ 愛知でどこに相談し、どう進めるか(窓口・予約・持ち物)
手続きの窓口は原則「初診日の加入年金」で分かれますが、実務上は年金事務所で事前相談→担当者固定→そのまま提出までがスムーズなことが多いです(国民年金のケースでも相談・提出まで進められる場合があります)。
一方、市役所・区役所は住民票や戸籍を同じ庁舎で揃えやすいメリットがあります。
≪もっと知りたい!!≫
まず全体の入口はここ。
〔愛知県版(窓口の分岐・予約・準備)〕
④ 名古屋市・春日井市の人(市別で運用・連絡先まで整理したい)
≪もっと知りたい!!≫
まとめ|「遡ると困る」からこそ、“区切るロジック”を知っておく
社会的治ゆは、精神の障害年金で起きやすい
「初診日が遡って不利になる問題」に対して、
“区切れる可能性”を作るための考え方です。
ただし、これは雰囲気で押し切る話ではなく、
- どれだけ安定していたか
- どんな治療状況だったか
- 就労・就学の裏付けがどれだけあるか
を、資料と整合性で積み上げる話になります。
もし「自分のケースはどっち方向で行ける?」が曖昧なら、
まずは状況の棚卸しが一番早いです。
まずは無料チェックリストで“争点の棚卸し”をしてください
≪もっと知りたい!!≫
社会的治ゆが論点になる人は、たいてい
- 初診日の候補が複数ある
- 受診歴が飛んでいる
- 就労の安定期がある
- でも資料の出し方が分からない
という状態になりがちです。
そこで、最初にやるのは「整理」です。
「まずは話を整理したい」という段階でも大丈夫です。
状況に合わせて、何から始めるのが最短か一緒に整理します。
電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。
運営者情報
- 監修:社会保険労務士 渡邊智宏
- 対応地域:名古屋市中心+愛知県全域
- お問い合わせ:〔フォームURL〕/〔電話:0568-92-4864〕
更新履歴
- 初版:2025年11月14日
- 最終更新:2026年1月28日

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。