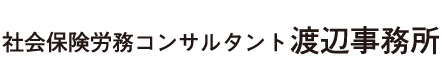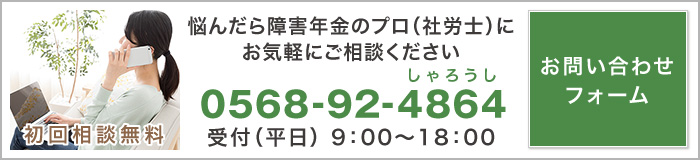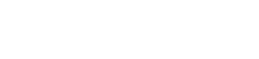「なぜ、この仕事をしているのですか?」
ご相談に来られたお客様から、時々、そう尋ねられることがあります。その問いに答えることは、私の人生そのものを語ること。それは、一度は社会からドロップアウトし、絶望の淵をさまよった一人の男が、いかにして再び立ち上がり、「かつての自分」と同じように苦しむ誰かのための光になるという使命を見つけたかの物語です。
こんにちは。愛知県春日井市で、うつ病や双極性障害など、精神疾患の障害年金を専門とする社会保険労務士の渡邊智宏です。そして、あなたと同じように、双極性障害(躁うつ病)という病と共に生きる一人の当事者でもあります。
この記事は、単なる私の経歴紹介ではありません。
もしあなたが今、病によって光を見失い、社会から取り残されたような深い孤独の中にいるのなら。この物語は、他の誰でもない、あなたのための物語でもあります。
どうか、少しだけ。私の、そして「あなたの」物語にお付き合いください。
〈目次〉
- 【第1章】失われた光:仲間と追いかけた夢、そして燃え尽きた心
- 【第2章】終わらないトンネル:退職、引きこもり、そして“最後の砦”の崩壊
- 【第3章】かすかな光:「社会保険労務士」という一本の蜘蛛の糸
- 【第4章】使命の発見:寄り添う、ではない。あなたの痛みを、私は「知っている」
- 結論、そしてあなたへ:絶望は、未来への武器になる
【第1章】失われた光:仲間と追いかけた夢、そして燃え尽きた心

若き日の挑戦と、手酷い洗礼
平成12年8月、私は新卒以来勤めてきた会社を退職しました。理由は、今振り返れば典型的な、しかし当時は逃げ出すことしか考えられなかった、激しいパワハラと過酷な労働環境でした。休みはなく、帰宅はいつも深夜。上司からの執拗な叱責と人格否定的な暴言が、若い私の心を少しずつ蝕んでいきました。
「このままでは、壊れてしまう」
その一心で下した、苦渋の決断は退職でした。しかし、不思議なことに、この経験が直接、今の病気に繋がったわけではないのです。半年もすると、ストレスから解放された心は回復し、再び社会復帰を志す気力が湧いてきました。
公務員試験に挑戦したり、知人の会社でお世話になったり・・・。紆余曲折の末に私が選んだのは、「起業」という、最も挑戦的な選択肢でした。会社員時代の知人と共に、Web関連の会社を立ち上げたのです。
希望に燃えていました。技術力のある協力会社とタッグを組み、自分たちは営業と管理に専念する。完璧な計画のはずでした。しかし、現実は非情です。その協力会社の技術力に、致命的な欠陥があることが判明。事業の根幹が、もろくも崩れ去りました。
行き詰まりは、人間関係をも蝕みます。社内の空気は急速に悪化し、4人いたはずの創業メンバーは、気づけば私を含め2人だけになっていました。
売るべきものがない。仲間もいない。途方に暮れた私たちは、生き残るために、自分たちでWeb制作の技術を1から学ぶことを決意します。デザインだけは外注し、それ以外は全て内製化する。悪戦苦闘の末、なんとか食べていけるだけの売上は立つようになりました。しかし、それは自転車操業のような、苦しい日々の始まりでもありました。
避けられなかった挫折、そして心の穴
経済的に苦しい状況は、数年続きました。そして、ついにその時が訪れます。私が手塩にかけてきたWeb制作事業は、私自身ごと、別の会社に移籍(事実上の事業売却)することになったのです。
起業家の端くれから、再び一人のサラリーマンへ。
今思えば、これこそが、私の心の歯車が狂い始める、決定的な瞬間でした。
売上が乏しいとはいえ、それは仲間と悪戦苦闘しながら、ゼロから育て上げてきた、我が子のような会社でした。それを手放した時の喪失感は、私の心に、ぽっかりと大きな穴を開けました。
仕事をすることは、生き抜くための「戦い」だった。それが、ただ漫然と時間を過ごしていれば給料がもらえる「作業」に変わってしまった。目標を失った心は、いわゆる「燃え尽き症候群」のような状態に陥っていました。
忍び寄る心の闇、そして不本意な「宣告」
この喪失感が、私の精神を静かに、しかし確実に蝕んでいきました。
追い打ちをかけるように、移籍先の会社での人間関係がこじれてしまったのです。
最初に現れたサインは、朝、目が覚めた瞬間に襲ってくる、強烈な拒絶感でした。
「会社に行きたくない」
いいえ、もっと正確に言えば、「行けない」のです。体が鉛のように重く、心が「もうダメだ」と悲鳴を上げる。起きた瞬間に、出勤できない、と強く感じてしまったのです。
そうして、会社を休む日が増えていきました。
2日連続で欠勤した後、出社した私を待っていたのは、上司からの「メンタルクリニックへ行ってこい」という、冷たい命令でした。
当時の私は、それが適切な配慮であるとは到底思えませんでした。「なぜ自分が・・・」という強い不信感と屈辱感。しかし、逆らうことはできず、不本意ながらクリニックの門をくぐりました。
そして、下された診断。
「うつ状態です」
平成18年の秋。それが、私の長い闘病生活の始まりでした。
当初は、その診断を受け入れられませんでした。しかし、症状は日に日に悪化していく。会社に行けない日が増え、家にいても、どうしていいか分からない。ただ、得体の知れない強い不安感だけが、四六時中、私を支配するようになっていきました。
もはや、自分の病気を認めざるを得ませんでした。
【第2章】終わらないトンネル:退職、引きこもり、そして“最後の砦”の崩壊

光の差さない部屋で考えたこと
そんな不安定な生活の中、会社から「正社員からアルバイトにならないか」という提案を受けます。「その方が休みやすいだろう」という、一見、優しさに見える言葉の裏に、「もう君は必要ない」という冷たい響きを感じ取った私は、退職を決意しました。
「これで、全てのストレスから解放される。きっと、すぐに楽になる」
そう、信じていました。
しかし、現実は、あまりにも残酷でした。会社を辞めたその日から、私の気分は奈落の底へと急降下していったのです。重しが外れるどころか、さらに重い鉛を心に抱え込むことになりました。
なぜか。
おそらく、「社会人である」という、社会と繋がる最後の拠り所を失ったことへの、精神的な反動だったのでしょう。そして、毎日決まった時間に起きて出社するという生活習慣が失われたこと、その急激な環境の変化自体が、私の心に大きなストレスを与えていたのかもしれません。
ここから、何年にもわたる、暗い引きこもり生活が始まりました。
毎日、襲い来る強烈な不安感。
何もする気が起きない、底なしの無気力感。
理由もなく、突然胸が締め付けられ、泣きたくなる衝動。
ただ、布団にくるまり、その嵐が過ぎ去るのを耐えるしかない。そんな日々でした。
当時は、その感情の波にどう対処していいか分からず、泣ける映画をわざわざ観て無理やり涙を流してみたりと、無駄な試行錯誤を繰り返していました。
収入ゼロという地獄、そして魂の告白(カミングアウト)
ただ、そんな暗闇の中にも、救いはありました。
これまでの人生で築いてきた、友人・知人という名の財産です。喫茶店を開業した友人は、毎日昼食を食べさせてくれました。同じ時期に同じ病気を患った友人は、「辛いよな」と、ただ黙って話を聞いてくれました。学生時代の友人は、気分転換にと、何度も私を外へ連れ出してくれました。
彼らのおかげで、私は完全な孤立からは、かろうじて免れていました。
しかし、うつ病という病は、本当に厄介なものです。そんな彼らの優しさすらも、時には耐えがたいストレスに感じてしまうのです。
電話が鳴るだけで、心臓が跳ね上がる。
「会おう」という誘いが、重いプレッシャーになる。
誰かと繋がることで救われながら、その繋がりそのものが辛い。このアンビバレントな葛藤は、経験した者にしか分からないかもしれません。
そんな生活を支えていた、最後の生命線。それが、健康保険から支給される「傷病手当金」でした。給料の約6割。働けなくても、最低限の生活を維持できる、唯一の収入源です。
最長で1年6ヶ月。
療養を始めた当初、それは永遠にも感じられる長い時間でした。「これだけあれば、きっと治る」と、本気で信じていました。
しかし、症状は一向に改善しない。むしろ、悪化していく。
1年6ヶ月という月日は、あっという間に過ぎ去りました。
「傷病手当金が、切れる」
その事実が、さらなるストレスとなって私にのしかかります。
収入が、ゼロになる。
アパートの家賃が、払えない。
万事休す。ついに私は、アパートを引き払い、実家に戻ることを決意しました。
これまで、病気のことは両親に伏せていました。すぐに治るつもりだったし、何より、うつ病で苦しむ情けない姿を、親に見せる勇気がなかったのです。
しかし、もう、そんなプライドを保っている余裕はありませんでした。
ある日、実家に帰り、両親の前で、全てを打ち明けました。
「病気で、働けなくなった。収入もない。だから、家に帰らせてほしい。助けてほしい」
何を言われるだろうか。根掘り葉掘り聞かれるだろうか。大騒ぎされるだろうか。
様々な不安が、頭をよぎりました。
しかし、両親の反応は、私の想像とは全く違うものでした。
「そうか。分かった。早く帰ってこい。生活のことは、心配するな」
ただ、それだけでした。
あれこれと事情を説明しなくても、ただ受け入れてもらえた。その事実が、どれほどありがたかったか、今でも鮮明に覚えています。
【第3章】かすかな光:「社会保険労務士」という一本の蜘蛛の糸

社会復帰への渇望と、高すぎる壁
こうして、実家での引きこもり生活が始まりました。
生きていくことへの直接的な不安はなくなりました。しかし、それと引き換えに、新たな地獄が始まりました。
「自分の名前で、1円もお金が入ってこない」という、耐えがたい現実です。
給料であれ、傷病手当金であれ、「自分の名義」で振り込まれる収入があるうちは、かろうじてプライドが保てます。しかし、それがゼロになると、まるで自分の存在価値そのものが失われたような、底知れぬ不安に襲われるのです。
「自分は、生きていていいのだろうか」
そんな自問自答を繰り返す、無為な日々。
しかし、そんな暗闇の中でも、時間は流れ、薬が効き、少しずつ変化が訪れました。病名は、うつ病から「双極性障害」に変わっていました。
一年かけて、薄紙を一枚ずつ剥がしていくような、遅々とした歩み。それでも、一年前の自分と比べれば、ほんの少しだけ、マシになっている。そんな小さな改善の兆しが、見え始めたのです。
そして、自然と「社会復帰」という言葉が、頭をよぎるようになりました。
とはいえ、気分が落ち込む日が少なくなった、という程度です。フルタイムで働ける状態には、ほど遠い。長いブランクのある履歴書。失われた自信。
「もう、普通の会社員に戻るのは無理だ」
当時の私は、障害者雇用という選択肢すら、頭にありませんでした。
運命の「戦友」との出会い
そこで、私が目を向けたのが、「フリーランス」という働き方でした。
幸か不幸か、一度は起業した経験もある。自分でできる仕事を、自分でできる範囲でやる。それしかない、と。
そのためには、「手に職」が必要です。
私が選んだのは、「社会保険労務士」という資格でした。実は、以前、起業がうまくいっていなかった頃に、一度だけ考えたことがあったのです。その時の、古びたテキストが、本棚の隅で私を待っていました。
「もう一度、これに賭けてみよう」
資格専門学校への通学は、週に2回、1回3時間。それでも、引きこもりだった私には、大きな挑戦でした。まずは、休まずに通うこと。そこから始め、少しずつ勉強のペースを掴んでいきました。
そして、一年後。試験の結果は、ギリギリの合格でした。
何も成し遂げられなかった自分が、久しぶりに掴んだ、小さな成功体験。それは、失いかけていた自信を、少しだけ取り戻させてくれました。
合格後、一年間の研修を経て、愛知県春日井市の自宅で、私は開業の日を迎えます。
しかし、それはゴールではなく、新たなスタートでした。
開業当初は、仕事などありません。同期の社労士たちが、精力的に活動し、次々と契約を取っていくのを、眩しい思いで眺めていました。「自分は病気を抱えている。焦るな」と言い聞かせながらも、心のどこかで感じる焦燥感。
そんな中、私の人生を決定づける、大きな出会いがありました。
同期開業組の一人。彼は、ギランバレー症候群という難病を患い、手足に障害を抱えていました。そして、その経験をバネに、「障害年金を専門にする」と、固く決意していたのです。
衝撃でした。
自分自身の障害を、弱みではなく「武器」にする。
その彼の姿は、自分の進むべき道を、一筋の光のように照らしてくれました。
「自分も、双極性障害という、大きな病気を経験している」
「この経験こそ、障害年金の仕事に活かせるのではないか?」
自分と同じ境遇の人間がいる。その発見は、何よりの心の支えとなりました。
【第4章】使命の発見:寄り添う、ではない。あなたの痛みを、私は「知っている」

負の経験が「価値」に変わった瞬間
自分の進むべき道が見えてからは、迷いはありませんでした。
障害年金の専門家として、私は自分の経験を、積極的に語るようになりました。
そして、驚くべきことが起こります。
ご相談に来られたお客様、特に、私と同じようにうつ病などの精神疾患を患っている方から、感謝の言葉をいただくようになったのです。
「先生の話を聞いて、救われました」
「同じ経験をしている人に話せただけで、心が軽くなりました」
もちろん、障害年金を受給できることは、何より重要です。しかし、それ以上に、「自分の苦しみを理解してもらえた」という事実に、お客様は価値を感じてくださったのです。
私の、暗く、誰にも話せなかったはずの、負の経験。
それが、ただ話すだけで、誰かの役に立つ。
「自分の人生の“闇”が、誰かの“光”になる」
その事実に気づいた時、私は、これまでの人生が全て肯定されたような、魂が震えるほどの感動を覚えました。苦しかったあの日々は、決して無駄ではなかった。お客様から「救われた」と言われるたびに、私自身もまた、救われていたのです。
なぜ私は「寄り添う」と言わないのか
この経験を通して、社会保険労務士としての私の、確固たるスタンスが決まりました。
同業の社労士は、よく「お客様に寄り添います」という言葉を使います。もちろん、それは素晴らしい姿勢であり、決して否定するものではありません。
しかし、私は、あえてその言葉を使いません。
なぜなら、「寄り添う」という言葉には、どこか「他人事」の響きがあるように感じてしまうからです。
私は、あなたの苦しみを、「他人事」だとは到底思えません。
だから、私はこう言います。
「あなたのその痛み、私も“知っています”。だから、同志として、戦友として、一緒に立ち向かいましょう」と。
自分自身が、あの暗闇の中を歩いてきたからこそ、できる関わり方。
机上の知識ではない、血の通った言葉で、あなたと話がしたい。
これこそが、神様が私に与えてくれた、唯一無二の使命なのだと、今は確信しています。
結論、そしてあなたへ:絶望は、未来への武器になる
私が今、この仕事をしている理由は、たった一つです。
かつての私のように、暗闇の中で独り震え、自分の価値を見失いかけているあなたを見つけ出し、その隣に立ちたいのです。
障害年金は、単にお金をもらうための制度ではありません。
「自分の名前」で振り込まれる収入がある。その事実が、失われた自尊心を回復させ、もう一度、自分自身を肯定するきっかけになります。収入がないという苦しみ、どうしようもない無力感。私も、痛いほど味わってきました。
私の経験が、あなたが障害年金という助けを手にするための、一つの糸口になればと願っています。
そして、その申請という行動を、ぜひ私と一緒に起こしてほしいのです。
私の全ての経験は、あなたと出会うためにありました。
「あなただけではない」
「私も、その痛みを、知っている」
だから、一緒に、未来への一歩を踏み出してみませんか。
あなたの絶望は、決して無駄にはなりません。それは、あなたの人生を、もう一度始めるための、最も力強い武器になるのですから。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。