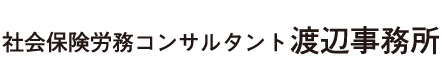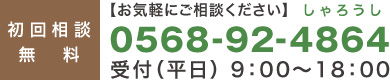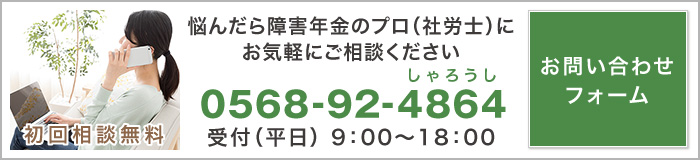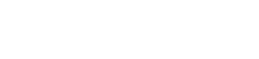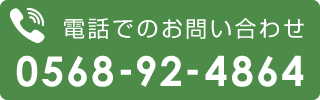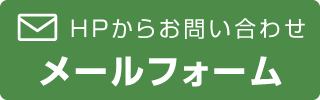「もう限界だ…。でも、生活のために、仕事を辞めるわけにはいかない」
「周りには元気なフリをしているけど、本当は毎日、心をすり減らしながら出勤している」
あなたは今、そんな風に一人で痛みを抱え、無理をして笑顔の仮面を被っていませんか。
こんにちは。双極性障害(躁う-病)の当事者として絶望の淵をさまよい、現在は愛知県春日井市で障害年金を専門とする社会保険労務士として活動している渡邊智宏と申します。
かつての私も、あなたと全く同じでした。先の見えない不安の中、「働き続ける」ことの苦しさと、「働かなければならない」というプレッシャーの、出口のない板挟みになっていました。
この記事では、「働きながら障害年金を受給する」という選択肢が、いかにあなたの心と生活を守るための賢明な戦略であるか。そして、その先にある新しい働き方の可能性について、私自身の赤裸々な体験と専門家の視点の両方から、徹底的に解説していきます。
障害年金は、仕事を辞めるためだけの制度ではありません。あなたが、あなたらしく働き続けるための、何より力強い「お守り」になるのです。
〈目次〉
「もう限界だ…。でも、生活のために、仕事を辞めるわけにはいかない」
「周りには元気なフリをしているけど、本当は毎日、心をすり減らしながら出勤している」
あなたは今、そんな風に一人で痛みを抱え、無理をして笑顔の仮面を被っていませんか。
こんにちは。双極性障害(躁う-病)の当事者として絶望の淵をさまよい、現在は愛知県春日井市で障害年金を専門とする社会保険労務士として活動している渡邊智宏と申します。
かつての私も、あなたと全く同じでした。先の見えない不安の中、「働き続ける」ことの苦しさと、「働かなければならない」というプレッシャーの、出口のない板挟みになっていました。
この記事では、「働きながら障害年金を受給する」という選択肢が、いかにあなたの心と生活を守るための賢明な戦略であるか。そして、その先にある新しい働き方の可能性について、私自身の赤裸々な体験と専門家の視点の両方から、徹底的に解説していきます。
障害年金は、仕事を辞めるためだけの制度ではありません。あなたが、あなたらしく働き続けるための、何より力強い「お守り」になるのです。
〈目次〉
- 【結論】うつ病で働きながらでも、障害年金はもらえます。ただし・・・
- 【私の体験談】「働くこと」に絶望し、再び希望を見出すまで
- 【専門家解説】なぜ「働いている」と不利になる?審査官が見ている“5つのポイント”
- 【最重要】「出勤できている ≠ 問題なく働けている」この違いをどう伝えるか
- あなたの未来を守る“3つの働き方”という選択肢
- まとめ:あなたの“働き方”に合わせた、最適な申請戦略を一緒に考えましょう
【結論】うつ病で働きながらでも、障害年金はもらえます。ただし・・・
まず、あなたの最大の疑問にお答えします。 結論から言えば、うつ病などの精神疾患で働きながらでも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。実際に、働きながら受給している方は、たくさんいらっしゃいます。 しかし、ここには非常に重要で、デリケートな注意点があります。 それは、請求において「あなたの働き方の“実態”を、いかに正しく、そして戦略的に伝えるか」という、専門的な技術が不可欠になる、ということです。 安易に「働いています」とだけ伝えてしまうと、「なんだ、働けるくらい元気なんだな」と判断され、不支給という厳しい結果に繋がる危険性が非常に高いのです。【私の体験談】「働くこと」に絶望し、再び希望を見出すまで
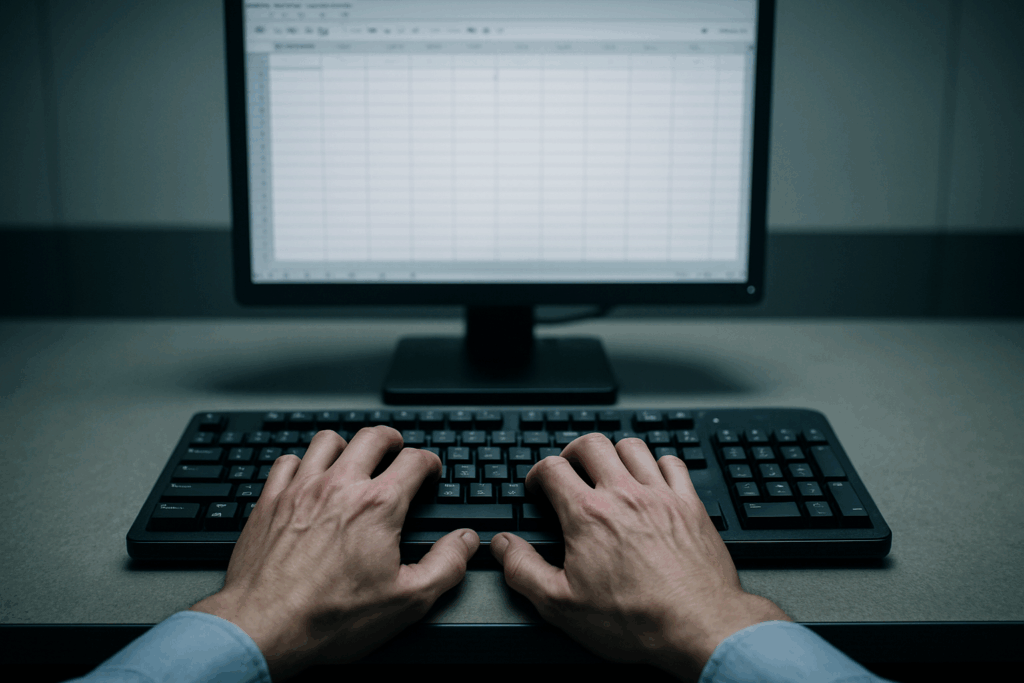 本題に入る前に、少しだけ、私の話をさせてください。
なぜなら、これからお話しする制度の解説は、この私の原体験と深く結びついているからです。
本題に入る前に、少しだけ、私の話をさせてください。
なぜなら、これからお話しする制度の解説は、この私の原体験と深く結びついているからです。
うつ病と診断されても、辞められなかった会社
私自身もかつて躁うつ病(双極性障害)と診断され、働けなくなるという経験をしました。病気になった当初は、うつ傾向が強く、働く事がとても辛い状況にありました。しかし、うつ病と診断されたからといって、すぐに仕事を辞めるわけにはいきません。生活は、仕事の給料で成り立っている。その大前提がある以上、「辞める」という選択肢は、現実的ではありませんでした。 それに、当時はまだ、この病気がこれほど長く続くものだとは思っていませんでした。「少し休めば、また元通りに働けるはずだ」という、今思えば甘い希望的観測を抱いていたのです。 しかし、病状は待ってくれません。朝、目が覚めた瞬間に襲ってくる、絶望的な倦怠感。「もう今日は、仕事に行けない・・・」そう思いながらも、必死に体を起こし、会社へ向かう。しかし、どうしても耐えられない日もある。そんな日は、「体調不良」を理由に欠勤する。気づけば、欠勤日はどんどん増えていきました。出社しても、強い不安感で仕事に全く集中できない。そんな日々が続いた結果、私は上司に呼び出されました。 「正社員から、アルバイト待遇にならないか」 自由に休まれては困る。アルバイトなら、出勤日を調整しやすいだろう。体調が戻ったら、また正社員に戻ればいい。 一見、温情にも聞こえるその提案が、私には「戦力外通告」のように響きました。しかし、冷静に考えれば、会社側の言い分も分かります。いつ休むか分からない人間を雇い続けるリスク。そして、私自身も、頻繁に休むことで周囲に迷惑をかけているという罪悪感に、押しつぶされそうになっていました。 「もう、この会社にしがみつくのはやめよう」 そう思った日、ちょうど通院日だったので、医師に相談しました。すると、「一旦、休職して仕事から離れることを勧めます」と言われ、そこで初めて「傷病手当金」という制度の存在を知ったのです。働かなくても、一定期間、収入が確保される。その事実が、私の心を決めました。 「一旦、仕事を辞めよう。療養に専念し、元気になったら、また社会復帰すればいい」 そう、単純に考えていたのです。3日でクビに・・・失われた「働く自信」
実際に退職し、傷病手-当金を受給しながらの療養生活が始まりました。しかし、生活は苦しいまま。社会復帰への焦りだけが募っていきました。 退職から1年ほど経ったある日、知人から「税理士事務所で、簡単なデータ入力のアルバイトをしないか」と声をかけられました。病気のことも知ってくれているし、単純作業なら無理なくできるかもしれない。一縷の望みをかけて、私はその仕事を引き受けました。 しかし、それは、私の「働く自信」を完全に打ち砕く、決定的な出来事となりました。 いざ仕事を始めてみると、簡単なはずの作業が、全く進まないのです。 分からないことにぶつかると、途端に思考が停止し、手が固まってしまう。隣の人に聞けば済む、ただそれだけのことができない。頭の中を、不安と焦りだけがぐるぐると駆け巡る。 自分でも愕然とするほど、仕事ができないのです。 そして、働き始めてから、わずか3日後。 私は呼び出され、「明日から、来なくていい」と、静かに告げられました。 不思議なことに、その言葉を聞いた瞬間、私は心の底から「ホッとした」のです。 こんな状態で働き続けることへの耐えがたい罪悪感から、ようやく解放された。クビにしてくれて、助かった。本気で、そう思いました。 この経験で、私は働くことにすっかり臆病になり、その後、何年にもわたる完全な引きこもり生活へと、沈んでいくことになったのです。私が選んだ「自営業」という道と、障害年金3級の現実
数年の時が経ち、少しずつ病状が改善してきた頃、私は再び社会復帰を考え始めました。そして選んだのが、今の仕事である「社会保険労務士」です。 なぜ、この仕事を選んだのか。 理由は、「自営業」だからです。 良くなったとはいえ、体調の波は激しい。「今日は動けない」という日が、頻繁にありました。決まった時間に、毎日出社するサラリーマンは、もう絶対に無理だという自覚がありました。- 仕事の量を、自分でコントロールできる。
- 働く時間を、自分の裁量で決められる。
【専門家解説】なぜ「働いている」と不利になる?審査官が見ている“5つのポイント”
 さて、私の体験談からも分かるように、「働きながら」の申請は非常にデリケートです。では、なぜ「就労」の事実は、審査でそれほど厳しく見られるのでしょうか。
それは、障害年金の等級が、「労働がどれくらい制限されるか」という基準で、明確に定義されているからです。
さて、私の体験談からも分かるように、「働きながら」の申請は非常にデリケートです。では、なぜ「就労」の事実は、審査でそれほど厳しく見られるのでしょうか。
それは、障害年金の等級が、「労働がどれくらい制限されるか」という基準で、明確に定義されているからです。
- 障害厚生年金3級: 労働が著しい制限を受ける程度のもの
- 障害厚生年金2級: 労働によって収入を得ることができない程度のもの
①雇用形態:正社員とアルバイト、その意味の違い
正社員か、パート・アルバイトか、あるいは障害者雇用か。これは、あなたの労働強度を測る最初の指標です。私の例で言えば、「正社員からアルバイトへ」という会社からの提案は、責任の重さや拘束時間の観点から、労働能力が低下していることを示す一つの材料になります。②勤務状況:タイムカードに映らない「実態」
週何日、1日何時間の勤務か。これは基本ですが、それだけではありません。頻繁な遅刻や早退、欠勤はないか。時短勤務をさせてもらっていないか。雇用条件の数字だけでは見えない「実態」が重要です。私が正社員時代に欠勤を繰り返していた事実は、フルタイムで働ける能力がなかったことの証明になります。③業務内容:責任の重さと、必要なサポート
責任の重い仕事か、単純作業か。他の人の助けなしに、一人で業務を完遂できているか。私が税理士事務所で挑戦した「単純なデータ入力作業」ですら遂行できなかった事実は、私の就労能力が著しく低下していたことを示す、何よりの証拠でした。④収入:給与額が示す労働能力
同じ職場で、同じような仕事をしている健常者と比べて、給与額に差はないか。著しく低い場合は、それ相応の働きしかできていない、と判断される材料になります。⑤職場の配慮:特別なサポートはありますか?
病気のことを職場に伝え、業務量を減らしてもらったり、定期的な面談があったりといった、特別なサポートを受けているかどうかも非常に重要です。これらは、あなたが「配慮なしでは働けない」状態であることを示します。【最重要】「出勤できている ≠ 問題なく働けている」この違いをどう伝えるか
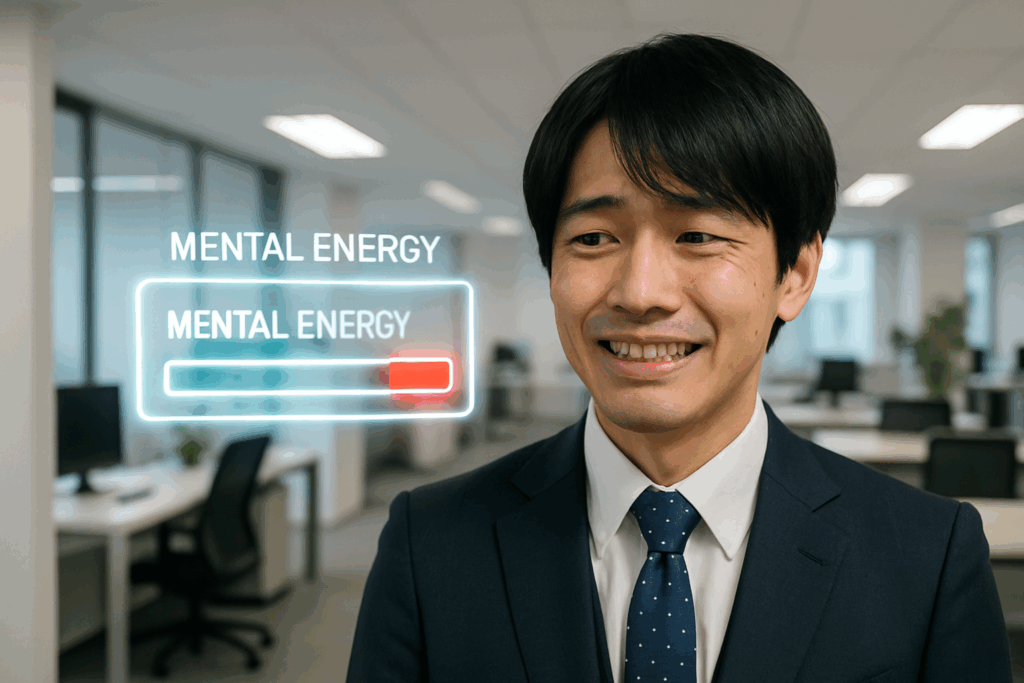 ここまで、審査でチェックされる客観的なポイントを解説しました。しかし、これだけでは不十分です。
当事者である私が、あなたに最も強くお伝えしたい、この記事の核心。それは、
「会社に出勤できている」という事実と、「問題なく働けている」という状態は、全くの別物だということです。
審査官に伝えなければならないのは、タイムカードや給与明細といった数字の裏に隠された、あなたの「見えない努力」と「ギリギリの状態」なのです。
ここまで、審査でチェックされる客観的なポイントを解説しました。しかし、これだけでは不十分です。
当事者である私が、あなたに最も強くお伝えしたい、この記事の核心。それは、
「会社に出勤できている」という事実と、「問題なく働けている」という状態は、全くの別物だということです。
審査官に伝えなければならないのは、タイムカードや給与明細といった数字の裏に隠された、あなたの「見えない努力」と「ギリギリの状態」なのです。
- 出勤前の現実: 毎朝、鉛のように重たい身体と戦い、吐き気と闘いながら、なんとかギリギリで玄関のドアを開けているのではないですか?
- 勤務中の現実: 落ち込んだ気分の中、周りに悟られないよう必死に笑顔の仮面を被り、ボーッとする頭でミスのないよう、人の何倍も神経をすり減らしていませんか?
- 帰宅後の現実: 仕事で全てのエネルギーを使い果たし、家に帰った途端に倒れ込み、食事も入浴もできず、ただ泥のように眠るだけの日々を送っていませんか?
- 休日の現実: 平日の無理がたたり、休日は一日中ベッドから出られず、ただ回復のためだけに時間を費やしてしまっていませんか?
あなたの未来を守る“3つの働き方”という選択肢
障害年金を受給することは、ゴールではありません。 それは、あなたがこれからの人生を、より自分らしく、穏やかに生きていくためのスタートラインです。年金という経済的な基盤を得ることで、あなたの働き方の選択肢は、大きく広がります。選択肢①:「今の職場」で働き方を変え、年金というお守りを手に入れる
もし、あなたが今の職場を辞めたくない、あるいは辞めることが難しいと考えているなら、「働き方を見直す」ことを条件に、現在の仕事を続けながら障害年金3級を目指す、という道があります。 ここで重要なのは、「これまで通り無理をして働き続ける」のではない、ということです。 そのままの状態で請求しても、「問題なく働けている」と判断され、不支給になる可能性が非常に高いからです。 目指すべきは、会社と相談し、あなたの病状に合わせた「特別な働き方」を実現すること。そして、その「配慮された状態」を客観的な事実として示し、障害厚生年金3級の基準である「労働に制限がある状態」だと認めてもらうことです。 ▼会社に相談・交渉すべき「働き方の見直し」具体例- 勤務時間の短縮: フルタイム勤務から、時短勤務(例:1日6時間勤務など)に切り替えてもらう。
- 業務内容の変更: 責任の重い部署や、顧客対応が多い部署から、より負担の少ない単純作業や後方支援の部署へ異動させてもらう。
- 労働日数の調整: 週5日勤務から、週3~4日勤務など、出勤日を減らしてもらう。
- 在宅勤務の活用: 通勤の負担を減らすため、在宅勤務が可能な日を設けてもらう。
- 明確なサポート体制の確立: 定期的な上司との面談、業務の指示を一つひとつ明確にしてもらう、困った時にすぐに相談できる担当者を決めてもらうなど、職場内でのサポート体制を文書などで明確にしてもらう。
選択肢②:「障害者雇用」で、2級を目指し心と生活を再建する
選択肢①でお話しした「今の職場で働き方を変える」というアプローチ。これを、さらに一歩進め、より強固な会社のサポート体制と、国の制度に則った形で実現するのが、「障害者雇用」という働き方です。 会社との個別の交渉による配慮は、担当者や上司の異動によって、いつ覆されるか分からないという不安が残るかもしれません。それに対し、障害者雇用は、「障害のある社員を、特別な配慮をもって雇用する」ことが、会社側の“義務”として法律で定められている制度です。 つまり、あなたが必要とするサポートが、個人の善意や温情ではなく、会社の正式な制度として保障されるのです。 この「障害者雇用」という選択は、障害年金の申請においても、極めて大きな意味を持ちます。- メリット: 会社側があなたの病状を理解し、合理的配慮(時短勤務、業務量の調整、通院への配慮など)を制度として提供してくれます。そして、この「十分な配慮がなければ働けない」という客観的な事実が、障害年金2級(労働によって収入を得ることができない状態)に該当する可能性を、大きく引き上げるのです。一般雇用でフルタイム勤務をしながら2級を目指すのは至難の業ですが、障害者雇用であれば、その道が現実的な選択肢として開かれます。
- 当事者としての視点: 障害者雇用に切り替えるには、障害者手帳の取得が必要であり、自分の病気をオープンにし、「障害者」であるという事実をご自身が受け入れるという、大きな心理的ハードルがあります。これは、決して簡単な決断ではありません。相応の覚悟が必要になるでしょう。 しかし、それによって得られるメリットは計り知れません。障害者雇用による給与に、障害年金2級という手厚い経済的基盤を加えることで、生活の安定度は飛躍的に向上します。何より、病気への理解がある職場で、再発のリスクを抑えながら安心して働き続けることができる。それは、あなたの人生を本格的に再建するための、最高の環境と言えるのではないでしょうか。
選択肢③:「自営業」という、私が選んだ道
会社という組織に合わせるのが難しいと感じるなら、私自身がそうであったように、「自営業(フリーランス)」という道もあります。- メリット: 自分の体調の波に合わせて、働く時間や量を完全にコントロールできます。これは、生活リズムが不規則になりがちな私たちにとって、何物にも代えがたいメリットです。
- 専門家としての注意点: ただし、自営業は「働けている」と判断されやすく、障害年金の審査では不利になる可能性も否定できません。だからこそ、私のように「どのような業務を、どれくらいのペースで、どのような制約の中で行っているか」という実態を、専門家の視点から客観的かつ論理的に説明する技術が、より一層重要になるのです。
まとめ:あなたの“働き方”に合わせた、最適な申請戦略を一緒に考えましょう
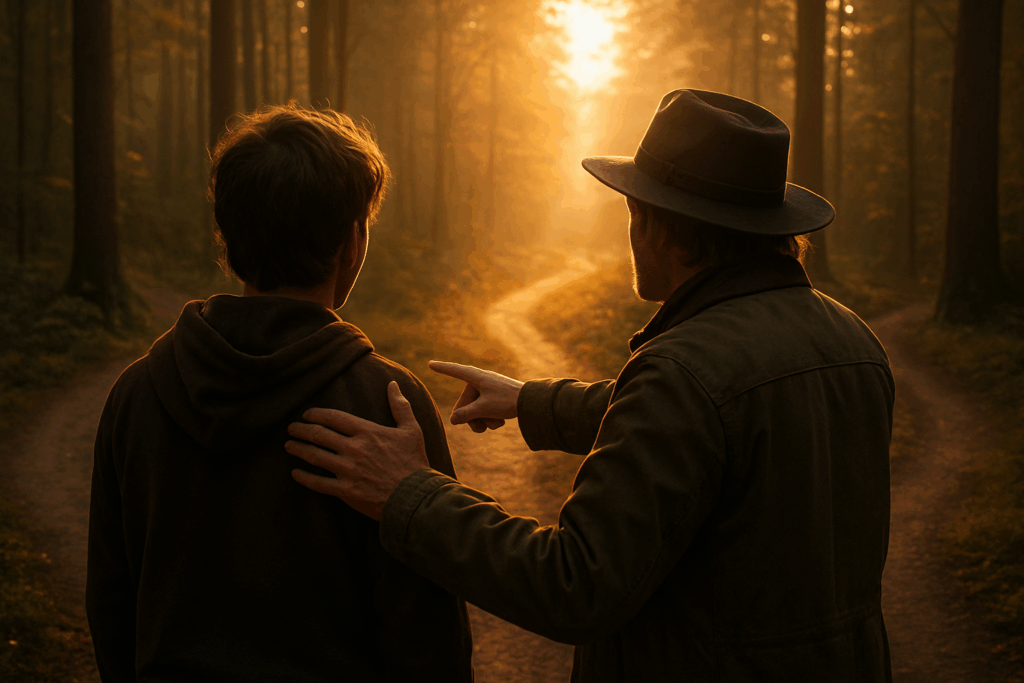 ここまで、「働きながら障害年金をもらう」ための、3つの具体的な選択肢についてお話ししてきました。
この記事を読んで、あなたはただ「もらえる可能性がある」というだけでなく、それがあなたの未来を主体的に選び取るための、極めて戦略的な選択であることを、ご理解いただけたのではないでしょうか。
改めて、3つの戦略を整理してみましょう。
ここまで、「働きながら障害年金をもらう」ための、3つの具体的な選択肢についてお話ししてきました。
この記事を読んで、あなたはただ「もらえる可能性がある」というだけでなく、それがあなたの未来を主体的に選び取るための、極めて戦略的な選択であることを、ご理解いただけたのではないでしょうか。
改めて、3つの戦略を整理してみましょう。
- 戦略A:【防衛策】今の職場で働き方を変え、障害年金3級という「お守り」を手に入れる。 会社と交渉し、勤務時間や業務内容に明確な「制限」を設けてもらう。今の生活基盤を守りながら、心のセーフティーネットを構築する、最も現実的な選択肢です。
- 戦略B:【再建策】「障害者雇用」に切り替え、障害年金2級という「経済基盤」を築く。 会社の制度として、あなたの障害への配慮を確約してもらう。心身の安全を最優先にしながら、より手厚い経済的保障を得て、人生を本格的に再建していくための、最も強力な選択肢です。
- 戦略C:【自律策】「自営業」として、自分のペースで働き、障害年金3級で生活を補強する。 私自身がそうであったように、働く時間も量も、すべて自分の裁量で決める。自由と責任の中で、病と共存しながら自分らしい生き方を模索する、最も主体的な選択肢です。
≪もっと知りたい!!≫
○このあと迷わない:完全ガイドへ戻る ○次の一手を決める:無料チェックリスト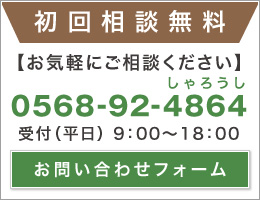
電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。
○春日井市版はこちら ○名古屋市版はこちら ○年金事務所の予約(公式)
愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。