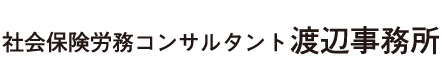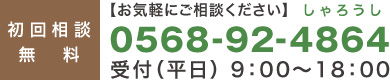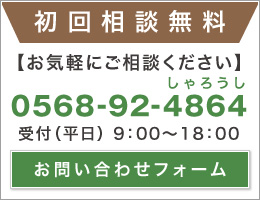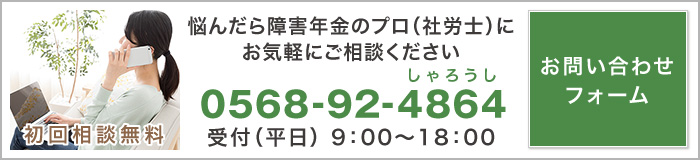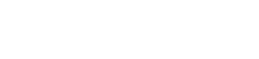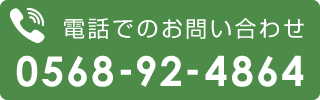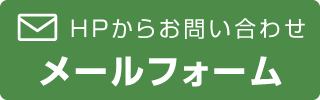〈目次〉
- はじめに:心の病気の「重さ」はどう測られるのか?
- 【結論】等級を決める2つのものさし:「日常生活」と「就労」
- ものさし①:「日常生活」を評価する“7つのチェックリスト”
- ものさし②:「日常生活」を“全体として”評価する5段階評価
- 【核心】あなたの等級が決まるメカニズム:「等級の目安」を読み解く
- 等級に影響する最重要ファクター:「就労」の壁
- 【最重要】等級を左右する「診断書」の真実
- まとめと次回予告
はじめに:心の病気の「重さ」はどう測られるのか?
「障害年金をもらえるなら、できるだけ手厚い等級で認定してほしい」
そう願うのは、病気と闘う誰もが抱く、切実な思いでしょう。経済的な安心は、心の安定に直結します。しかし、いざ申請を考えたとき、大きな疑問が頭をよぎります。
「うつ病や双極性障害の『重さ』って、一体どうやって判断されるんだろう?」
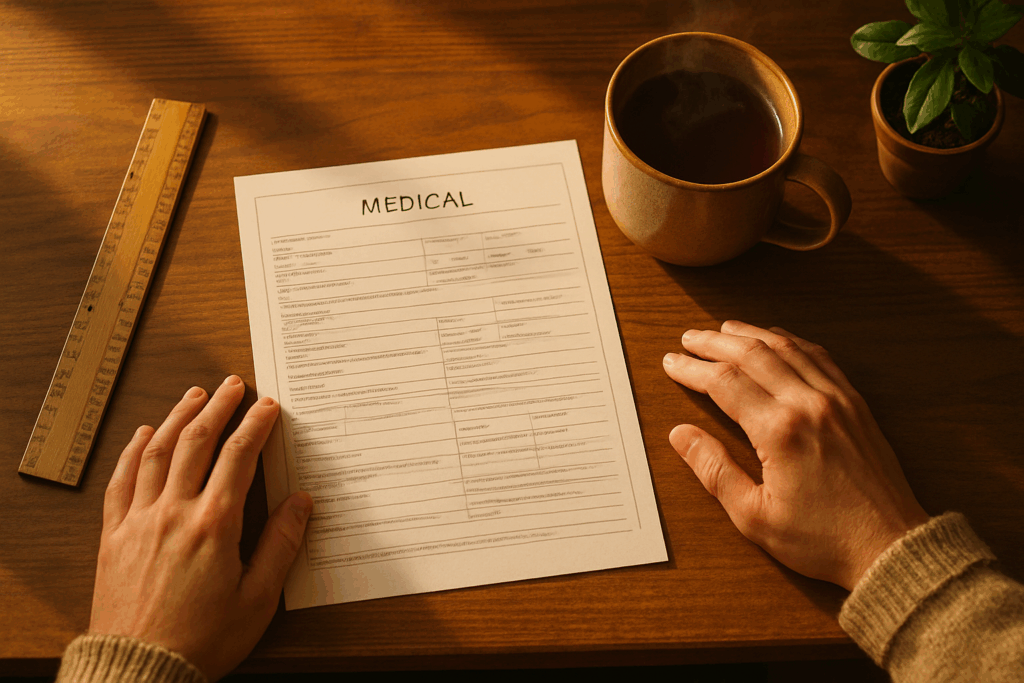
例えば、身体の障害であれば、ある程度は客観的な指標を想像しやすいかもしれません。「腕を失ったら何級」「関節がこれ以上曲がらなければ何級」といったように、目に見える形で基準が示されています。内科的な病気でも、「血液検査のこの数値が基準を超えたら」「レントゲン写真でこの所見が見られたら」というように、科学的なデータに基づいた判断がなされます。
では、私たちの抱える精神疾患の場合はどうでしょうか。
心の痛みは、外見からは分かりません。血液検査やMRIで「気分の落ち込み度」を測定することもできません。がんのように「ステージいくつ」といった、世界共通の明確な判定基準があるわけでもありません。
もし今、誰かに「あなたの病気の重さを、客観的な根拠をもって説明してください」と言われたら、あなたはどう答えますか?
「自分では、もう何もできないくらい辛い。だから一番重いはずだ」
「でも、世の中にはもっと大変な人がいるかもしれない。そう思うと、自分は中くらいなのかな…」
このように、自分の感覚に頼るしかなく、答えに窮してしまうのではないでしょうか。知り合いに病状を説明しようとしても、その辛さを裏付ける「根拠」を示すのは、驚くほど難しいことに気づかされます。この「客観的な根拠のなさ」こそが、精神疾患を抱える私たちが社会から理解されにくい、大きな要因の一つなのかもしれません。
しかし、ご安心ください。障害年金の世界には、この目に見えない心の病気の重さを測るための、明確な「ものさし」が存在します。そして、その「ものさし」が何を測ろうとしているのかを正しく理解することこそが、あなたが正当な評価を受けるための、何より重要な第一歩となるのです。
こんにちは。精神疾患の当事者として辛い日々を乗り越え、現在は障害年金を専門とする社会保険労務士として活動している者です。
この記事では、かつての私のように、先の見えない不安の中で「自分の状態が正しく評価されるのだろうか」と悩んでいるあなたのために、精神疾患の障害年金の等級がどのように決まるのか、その全貌を、どこよりも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
この記事を最後まで読めば、審査官が何を見ているのか、そして、あなたが正当な等級を得るために「今すぐ何をすべきか」が、明確に見えてくるはずです。
【結論】等級を決める2つのものさし:「日常生活」と「就労」
さっそく結論からお伝えしましょう。精神疾患の障害年金の等級を決定する上で、審査官が用いる「ものさし」は、大きく分けて2つしかありません。
- 日常生活能力: 日常生活を送る上で、どれくらい他者の助けが必要か?
- 就労能力: 労働によって、どれくらい収入を得ることができるか?
この2つの視点、特に「日常生活にどれだけの支障が出ているか」という点が、精神疾患の等級判定において、他のどんな要素よりも重視される、最重要キーワードとなります。
審査官は、あなたの心の中を直接覗くことはできません。だからこそ、あなたの「辛さ」や「苦しみ」が、日々の生活や仕事といった「具体的な行動」にどのような影響を及ぼしているのか、その「結果」を見て、病状の重さを客観的に判断しようとするのです。
これから、この2つの「ものさし」が、具体的にどのようにあなたの状態を測り、等級という結果に結びついていくのか、そのメカニズムを一つひとつ丁寧に解き明かしていきましょう。
ものさし①:「日常生活」を評価する“7つのチェックリスト”
まず、最も重要となる「日常生活能力」の評価についてです。
「日常生活」と一言で言っても、その範囲は非常に広いですよね。審査では、この曖昧な「日常生活」を、より客観的に評価するために、私たちの生活を7つの具体的な場面に分解して見ていきます。
これは、実際に医師が記入する診断書に記載されている公式なチェックリストです。
【日常生活の7つの場面】
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持(入浴、洗面、着替えなど)
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬(自己管理ができるか)
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応(突発的な出来事への対応など)
- 社会性(社会的な手続き、公共施設の利用など)
審査官は、この7つの項目一つひとつについて、「他者の助けがどれくらい必要か」という観点からあなたの状態を把握し、等級を判断していくのです。
「食事ができる」の本当の意味とは?

この7つの項目を見て、「あれ?ほとんどできている気がするな…」と感じた方もいるかもしれません。しかし、ここでの「できる」という言葉は、私たちが日常的に使う意味とは少し、いや、かなり異なります。
その違いを理解するために、1番目の「適切な食事」を例に、深く掘り下げてみましょう。
障害年金の審査における「適切な食事ができる」とは、単に「お箸が持てるか」「食べ物を口に運べるか」といった物理的な動作のことではありません。それは、「食事」という行為を取り巻く一連のプロセス全体を、一人で、自発的に、そして適切に遂行できるか、ということなのです。
少し想像してみてください。私たちが「食事をする」までには、実に多くのステップが存在します。
- ステップ1:意欲と計画
まず、「お腹が空いたな、何か食べよう」という意欲が湧かなければなりません。そして、「今日は何を食べようか?」と献立を考える必要があります。うつ病の症状が重いと、この最初の「意欲」そのものが失われ、食事への関心が全くなくなってしまうことも少なくありません。 - ステップ2:準備と調達
次に、冷蔵庫の中身を確認し、足りないものがあれば買い物に行く必要があります。お店まで行き、商品を選び、レジで支払いをする。この一連の行動には、想像以上のエネルギーと判断力が必要です。 - ステップ3:調理
家に帰ったら、買ってきた食材を使って調理をします。野菜を洗い、切り、火を使って煮たり焼いたりする。複数の作業を同時に進める「段取り力」も求められます。 - ステップ4:摂食
そしてようやく、実際に食事をとる段階です。しかし、ここでも「適切に」という点が問われます。一日中何も食べなかったり、逆に過食に走ってしまったり、甘いものやインスタント食品ばかりで栄養が極端に偏っていたりする場合、「適切な食事」とは言えません。 - ステップ5:後片付け
最後に、食べ終わった食器を洗い、キッチンを後片付けする。この最後のステップをこなす気力が残っているかも、重要な評価ポイントです。
どうでしょうか。単に「食事」と言っても、これほど多くの複雑な行動が連鎖しているのです。障害年金の審査では、この一連の流れを「一人だけで」「誰の助けも借りずに」「きちんと」できるかどうか、という厳しい視点で見ているのです。
他の6項目、例えば「身辺の清潔保持」であれば、お風呂に入る気力が湧くか、季節に合った服を選べるか。「金銭管理」であれば、計画的にお金を使えるか、公共料金の支払いを忘れずに行えるか、といったように、すべて同じ考え方で評価されます。
あなたのレベルはどれ?「できる」を測る“4段階評価”
そして、この7つの項目それぞれについて、医師はあなたの状態を以下の4段階で評価し、診断書にチェックを入れることになります。
- (問題なく)できる
- 自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
- 自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
- 助言や指導をしてもできない、若しくは行わない
1番の「問題なくできる」と、4番の「全くできない」は、比較的イメージしやすいかと思います。問題は、多くの方が該当するであろう、2番と3番の違いです。
この二つを分けるキーワードは、ズバリ「自発性」です。つまり、「自分からやろうと思えるか、行動に移せるか」が決定的な違いとなります。
先ほどの「食事」の例で、もう一度考えてみましょう。
- レベル2の状態とは?
自分から「お腹が空いたからご飯を作ろう」と思えるし、行動にも移せる。しかし、調理の途中で手順がわからなくなってパニックになったり、何を作っていいか決められずに立ち尽くしてしまったりして、時々、家族に「次はこれをしたら?」と助けてもらう必要がある状態。これがレベル2です。行動のきっかけは「自分」にあります。 - レベル3の状態とは?
そもそも自分から「ご飯を食べよう」という意欲が全く湧かない。何時間もベッドから出られず、食事のことなど考えもしない。しかし、家族が「ご飯できたよ、ここに座って。さあ、一口食べてみよう」と根気強く促し、手取り足取りサポートしてくれれば、なんとか食事をすることができる状態。これがレベル3です。行動のきっかけは「他人」にあります。
この「自発性」という、非常に微妙でありながら決定的な違いを、医師に正しく理解してもらうことが、適正な等級を得る上で極めて重要になるのです。
ものさし②:「日常生活」を“全体として”評価する5段階評価
7つの項目を個別に評価する4段階評価とは別に、もう一つ、あなたの状態を評価する「ものさし」が診断書には存在します。
それは、「日常生活能力の程度」を、より大きな視点から全体として評価する、5段階評価です。
これは、先ほどの7項目のような細かい分類はせず、「日常生活」や「社会生活」という、より広い範囲での活動能力を、他者からの「援助」がどれくらい必要かという観点で評価するものです。
ここで「日常生活」と「社会生活」という、似たような言葉が出てきましたね。
- 日常生活とは、食事や入浴、家の中での活動といった、主に個人的な身の回りの活動を指します。
- 社会生活とは、会社や学校に行く、友人との付き合い、地域活動への参加など、他者や社会と関わる活動を指します。
この5段階評価では、より広い意味での「社会生活」まで含めて、あなたの能力を総合的に判断します。
【日常生活能力の程度(5段階評価)】
- 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
- 精神障害を認め、社会生活には、助言や指導を必要とする。
- 精神障害を認め、社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。
- 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。
- 精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできないため、常時援助を必要とする。
レベル1は援助が不要な状態、レベル5は身の回りのこと全般に常時援助が必要な状態です。この5段階評価は、あなたの状態を大局的に捉えるための、もう一つの重要な指標となります。
【核心】あなたの等級が決まるメカニズム:「等級の目安」を読み解く
さて、ここまで2つの「ものさし」を見てきました。
- 7項目 × 4段階 の個別評価
- 1項目 × 5段階 の総合評価
では、これらの評価が、最終的に「障害等級1級、2級、3級」という結果に、どのように結びついていくのでしょうか。ここが、あなたが最も知りたい部分だと思います。
審査の現場では、これら2つの評価を組み合わせて等級を判断するための、「障害等級の目安」という、いわば「判定表」のようなものが使われています。
ものすごくザックリと、感覚的な目安をお伝えすると、以下のようになります。
- 7項目評価で、「レベル2(時に援助が必要)」が多い → おおむね3級の可能性
- 7項目評価で、「レベル3(援助があればできる)」が多い → おおむね2級の可能性
- 7項目評価で、「レベル4(援助があってもできない)」が多い → おおむね1級の可能性
- 5段階評価で、「レベル2~3」 → おおむね3級の可能性
- 5段階評価で、「レベル3~4」 → おおむね2級の可能性
- 5段階評価で、「レベル5」 → おおむね1級の可能性
より正確に言うと、審査官はこれら2つの評価を機械的に組み合わせて、等級の目安を判断しているのです。
「等級の目安」の表を公開!
少し専門的な話になりますが、実際に審査で使われている「等級の目安」の表をご紹介します。これを見れば、そのメカニズムが一目瞭然となります。
【精神の障害に係る等級判定ガイドライン(障害等級の目安)】
|
7項目の平均 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.0~1.4 |
非該当 |
非該当 |
3級 |
3級 |
2級 |
|
1.5~1.9 |
非該当 |
3級 |
3級 |
2級 |
2級 |
|
2.0~2.4 |
3級 |
3級 |
3級 |
2級 |
2級 |
|
2.5~2.9 |
3級 |
3級 |
2級 |
2級 |
1級 |
|
3.0~3.4 |
3級 |
2級 |
2級 |
1級 |
1級 |
|
3.5以上 |
2級 |
2級 |
1級 |
1級 |
1級 |
〈表の見方〉
- まず、「7項目×4段階評価」について、各段階を点数化します。(1:できる=1点、2:時に援助=2点、3:援助あれば=3点、4:できない=4点)
- 7項目の点数を合計し、7で割って平均点を出します。これが表の縦軸になります。
- 次に、「日常生活能力の程度(5段階評価)」の段階数を、そのまま表の横軸とします。
- 縦軸(平均点)と横軸(5段階評価)が交差するマスに書かれているのが、あなたの等級の目安となります。
【具体例】
例えば、あなたの診断書が以下のような評価だったとします。
- 7項目評価の平均点が「3.0」だった。
- 5段階評価が「3」だった。
この場合、表の「3.0~3.4」の行と、「3」の列が交差するマスを見ると、「2級」と書かれています。つまり、あなたの状態は、この判定表上では「障害等級2級に相当する可能性が高い」と判断されるわけです。
目安はあくまで目安。総合的な判断が下される理由
「なるほど、この表で決まるのか!」と、少し安心されたかもしれません。しかし、ここで非常に重要な注意点があります。
それは、この表はあくまで「目安」であり、この表の結果が100%あなたの等級になるわけではない、ということです。
審査では、この「等級の目安」を基本としながらも、診断書に書かれたその他のあらゆる情報を考慮に入れて、最終的な等級が総合的に決定されます。
例えば、判定表では「2級相当」という結果が出ても、診断書の他の部分に、「天気の良い日は散歩に出かけている」「友人と時々会って話をしている」といった、比較的「元気」だと判断されかねない記述があった場合、等級が3級に下がったり、不支給になったりする可能性も出てくるのです。
では、この「等級の目安」以外に、審査官が特に重視する要素とは何でしょうか。それが、冒頭で述べたもう一つの「ものさし」である「就労」の状況なのです。
等級に影響する最重要ファクター:「就労」の壁
思い出してください。障害年金の等級を決める2つのものさしは、「日常生活能力」と「就労能力」でした。ここまで解説してきた「等級の目安」は、主に「日常生活能力」を評価するものです。
そして、この目安で導き出された等級が妥当かどうかを判断するために、審査官はあなたの「就労」の状況を厳しくチェックします。
なぜなら、障害年金の認定基準には、就労能力について以下のような明確な定義があるからです。
- 1級: (日常生活が極めて困難なため、就労は想定されていない)
- 2級: 労働によって収入を得ることができない程度のもの
- 3級: 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
この定義を見れば一目瞭然ですね。
もし、判定表で「2級相当」という結果が出ていたとしても、あなたが一般企業でフルタイム勤務をしていたらどうでしょうか。審査官は「労働によって収入を得ることができている。2級の定義には当てはまらない」と判断し、等級を3級や不支給に変更する可能性が極めて高いのです。
これが、「日常生活」の評価が2級レベルでも、働いているというだけで2級が認められにくい、いわゆる「就労の壁」の正体です。
2級を目指すのであれば、最低条件として、
- まず、日常生活能力が「2級相当」であること(必要条件)
- その上で、就労能力も「労働によって収入を得られない」状態であること(十分条件)
この2つの条件を両方クリアする必要がある、と考えるのが現実的です。
「働いている=元気」ではない!正しい伝え方
では、「少しでも働いていたら、もう2級は絶対に無理なのか?」というと、必ずしもそうではありません。大切なのは、その「働き方の中身」です。
例えば、
- 体調が悪く、週に2~3日、1日数時間の短時間勤務しかできない。
- 常に上司や同僚からの特別な配慮(業務量の調整、頻繁な休憩、指示の単純化など)がなければ、仕事を続けることができない。
- 欠勤や早退が多く、安定した勤務が全くできていない。
このような状況は、3級の定義である「労働に制限がある」状態に当てはまります。たとえ働いていたとしても、その実態が「普通の働き方」とはほど遠いことを、診断書や申立書で具体的に示すことができれば、3級に認定される可能性は十分にあります。
一番避けたいのは、「働いている」という事実だけが一人歩きし、「この人は元気で問題なく働けている」と誤解されてしまうことです。
障害者雇用という選択肢が持つ大きな意味
ここで、特に知っておいていただきたいのが「障害者雇用」という働き方です。
もしあなたが障害者雇用枠で働いている場合、一般雇用とは異なり、会社側があなたの障害を理解し、特別な配慮を提供していることが前提となります。そのため、障害者雇用で働いているという事実は、一般雇用の場合よりも、障害の重さを示す有力な材料として考慮される傾向があります。
ガイドラインにも、「障害者雇用制度を利用した就労については、2級の可能性を検討する」と明記されています。
これは、社会復帰を考える上で、非常に大きな意味を持ちます。
例えば、うつ病で退職し、障害年金2級を受給できるようになったとします。その後、体調が少し安定し、「もう一度働きたい」と思ったとき、いきなり一般雇用でフルタイム復帰するのは、再発のリスクも高く、非常にハードルが高いでしょう。
しかし、そこで「障害者雇用」という選択肢を検討するのです。
障害者雇用であれば、無理のないペースで、配慮のある環境で働くことができます。そして、たとえ働き始めたとしても、障害年金2級または3級を受給し続けられる可能性が残ります。
障害者雇用の給与は、一般的に低く抑えられがちですが、そこに障害年金を加えることで、「安定した収入」と「ストレスの少ない労働環境」を両立させ、再発のリスクを抑えながら、着実に社会復帰への道を歩むことができるのです。これは、長期的な視点であなたの人生を立て直すための、非常に賢明な戦略の一つと言えるでしょう。
【最重要】等級を左右する「診断書」の真実
ここまで、等級判定のメカニズムと、日常生活や就労の重要性について解説してきました。そして、これら全ての情報が、たった一つの書類に集約されます。
それが「診断書」です。
あなたの等級は、この診断書に何が書かれているかで、ほぼ全てが決まると言っても過言ではありません。7項目評価も、5段階評価も、就労状況も、すべてはこの診断書に基づいて判断されます。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
医師はあなたの「日常生活」を知らない
考えてみてください。普段の診察時間は、5分か10分程度ではないでしょうか。その短い時間で、あなたは医師に何を話していますか?
「最近、気分が落ち込んでいて…」
「夜、よく眠れなくて…」
「薬を調整してほしいのですが…」
おそらく、症状や薬に関する話が中心で、「家で食事が作れなくて困っています」「お風呂に入るのが週に1回になってしまいました」「お金の管理ができず、支払いを滞納してしまいました」といった、具体的な日常生活の困りごとまで、詳しく話す機会はほとんどないはずです。
つまり、医師は、あなたの日常生活のリアルな実態を、ほとんど知らないのです。
それにもかかわらず、医師は診断書の7項目評価を記入しなければなりません。情報がない中で、医師はどうするでしょうか。患者さんの様子や、わずかな会話から「おそらく、これくらいだろう」と推測して書かざるを得ないのです。
その結果、あなたの本当の状態とはかけ離れた、実態よりも「軽く」見えてしまう診断書が出来上がってしまう危険性が、常に存在します。
「これだけはやって!」納得のいく診断書を書いてもらうための秘策
では、どうすればいいのでしょうか。答えはシンプルです。
「こちらから、医師に正確な情報を提供する」
これしかありません。医師も人間です。そして、科学者でもあります。診断書という公的な書類を作成する上で、「本人の証言」というエビデンス(証拠)は、非常に重要な参考資料となります。
「でも、診察中にそんなに長く話す時間はない…」
その通りです。だからこそ、「書面にして渡す」のです。
A4用紙1枚で構いません。診断書の作成を依頼する際に、あなたの日常生活の状況をまとめたメモを一緒に渡すのです。これは、驚くほど効果があります。私の経験上も、「こういう資料があると、非常に助かる」と言ってくださる医師は、年々増えています。
では、具体的に何を書けばいいのでしょうか。
一番のおすすめは、この記事で解説した「日常生活の7つの項目」に沿って、ご自身の状況を具体的に書き出すことです。
- (1)適切な食事:
- 週に何回、自分で調理できているか。
- 食事の内容は偏っていないか(インスタント食品や菓子パンばかりなど)。
- 家族に食事の準備をしてもらっているか。
- (2)身辺の清潔保持:
- 入浴やシャワーの頻度はどれくらいか。
- 同じ服を何日も着続けていないか。
- 部屋の掃除や片付けができているか。
このように、7項目それぞれについて、「できる/できない」だけでなく、「どれくらいの頻度で」「誰の助けを借りて」「どんな状態か」を、できるだけ具体的に書き出してみましょう。
この「情報提供」という一手間が、あなたの本当の苦しみを医師に伝え、実態に即した、納得のいく診断書を書いてもらうための、最も重要で効果的なアクションなのです。
まとめと次回予告
今回は、精神疾患の障害年金の等級がどのように決まるのか、その全体像と基本的な考え方について、詳しく解説しました。
▼今回の最重要ポイント
- 等級は「日常生活」と「就労」の2つの「ものさし」で決まる。
- 特に「日常生活の7項目」で、どれだけ他者の助けが必要かが重要。
- 「できる/できない」の判断基準は、「自発性」がカギ。
- 等級判定の土台となる「診断書」には、あなたのリアルな生活状況を、こちらから情報提供することが不可欠。
少し難しい話も多かったかもしれませんが、審査の仕組みを知ることで、あなたが今何をすべきかが見えてきたのではないでしょうか。
そして、納得のいく診断書を書いてもらうためには、7つの項目がそれぞれ「何を聞こうとしているのか」を、より深く理解しておく必要があります。
【次回予告】
次回のブログでは、いよいよ「日常生活の7項目」の一つひとつを、徹底的に深掘りして解説していきます。それぞれの項目で、具体的にどのような点が評価されるのか。それを知ることで、あなたは医師に渡す「メモ」を、より的確に、そして効果的に作成できるようになるはずです。
障害年金の申請は、あなた自身の人生を取り戻すための、大切な一歩です。焦らず、一つひとつ、着実に進んでいきましょう。
≪もっと知りたい!!≫
実際の手続きは、初診日の加入年金で窓口が分かれ、予約・持ち物・段取りが必要になります。
次は、名古屋市の入口ナビで「どこに相談し、どう進めるか」を確認してください。
「まずは話を整理したい」という段階でも大丈夫です。状況に合わせて、何から始めるのが最短か一緒に整理します。
電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。